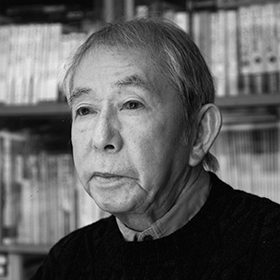
――ひとりひとりの個の生は、こういう私化された小さな小宇宙の複合体であり、その複合体を鞏固な統一物と見せかけているものがもろもろの文化的観念的構築なのである。そして思想とは文学とはつねに、個的な日常の規定から、そのうえにそびえ立つ文化的観念的構築を批判するいとなみである。*1
――もちろん、思想的抽象の一定レベルでは、このような〈地方〉をサイクルとする一生も、〈都〉で過される現代風な勤め人の一生も、その包含する意味は全く等価でしかない。だが、少なくともここには視圏にかかわる想像力の問題が生じるはずである。陸を走る動物と海にひそむ生きものとが、世界をおなじふうに見ているはずがないように、都で一生を過す人間と、田舎で一生を終える人間に、世界がおなじものに見えているはずはない。 *2
――闇から闇に流れる流星のような人生もあれば、いつ生まれ死んだともわからぬ苔のような人生もある。 *3
● “最後の人”の主体
結局のところ、渡辺京二は“最後の人”になるのでしょう。何の。いわゆる思想史的知性の。
「九州に住む在野の思想史家」――彼自身これをよしとするかどうかは別にして、これが彼、渡辺京二に対する世間一般の認識としての、まず最大公約数といったところでした。*4
この国の母語を環境とした、時期的には先の戦争が終わって後、高度経済成長の豊かさに後押しされて出現した、良くも悪くもそれまでとは様相の異なる新たな大衆社会状況と、そこに宿ったその他おおぜいのリテラシーに支えられた読書市場を介して可視化されていったひとつの〈知〉のありかた。それをどう呼ぶべきか、立場により、また考え方によりさまざまにあり得るのでしょうが、とりあえずここでは仮に、思想史的知性と呼んでおきましょう。*5
この思想史的知性というのは、同時に匿名的でもあります。何を言う、知性は個人に宿るもので、何よりそのような個の主体によって表現されるものだ、と叱られるかも知れません。しかし、不思議なことに、ここで言う匿名的とはそのような主体としての輪郭確かさと、なぜかうっかりと共存する、できるようなものでもあるらしいのです。
それまでは、知る人ぞ知るという言い方がしっくりなじむような書き手であり、いわゆるジャーナリズムの表層に華やかに現われることのまずないまま、九州に蟠踞する渡辺京二の名前を一躍、全国区のものにしたと言っていい『往きし世の面影』をここ何年もの間、ある講義の場を介して学生たちと共に読むことをしてきて、そのような思想史的知性のひとつの典型、ひとりの生身の個体が生の過程をくぐりながらそのように結晶していった果実として、この書き手のある本質を自分の裡に結像することが少しはできるようになった気がしています。 *6
それは、個々の仕事においてというよりも、そのような仕事を生み出してきたこの人自身の現実との距離感、対象との間合いの制御の仕方から、おそらくは日常の人づきあいなどに至るまで、生きる上での方法意識に関わってくるもののようです。その時その時の興味や関心、とりあげる主題などはさまざまであっても、それらの背後に確かに通底しているある意識の水準。それは単にその書き手個人の資質や個性、人となりといった生身の現実に紐付けられた表層においてというよりも、書き手としての営みそれ自体の背後に結果的に埋め込まれてゆくことになっていった背骨のような見えない部分において初めて認められるようなもので、俗な言い方をすれば生き方やスタイルなどと言って通り一遍に片づけられてしまうかもしれないようなものでもあるのでしょう。しかし、それはひとりこの人だけのものでなく、この国のある種の知性の習い性として、半ば伝統として継承されてきているものでもあるらしい。
間違いなくひとつの個体であり、その意味で一人であると同時に、しかしなぜか匿名性をもその裡に内包した個。そして、それらが共にある条件や環境の下にゆるやかに共有している静かな、声高にならない〈知〉のありよう。おそらくは、柳田國男と彼が夢見たかつての民俗学が合焦しようとした「常民」的な知性の土壌から晶出されるある知性のかたちとして、その造型をゆっくりと可能にしていったのであろうこの人の背骨に宿った方法意識のことを、いま、自分の確信の届く範囲でとりあえず、たとえ素描的にでも言葉にしておきたいと思います。 *7

●● 『逝きし世の面影』の重心
『逝きし世の面影』の初版は1998年に葦書房から出されました。元になったのは1980年10月から85年に5月にかけて、110回にもわたってあるお寺で行なわれた連続講義とされています。*8 それが文字の原稿としてかたちになっていったのは、1995年から『エコノミスト』(毎日新聞社)に「われら失いし世界――日本近代素描Ⅰ」という題目で始めた連載からでした。ただし、この連載は「序章」「第1章」のあと「第2章」の途中で中断したそうなのですが、それらをもとにさらにふくらませたものが、『逝きし世の面影』となった、というのが彼自身による説明です。
「私はずっと売れぬ本の著者であった。それでよいと思っていた。ときには選書になったり文庫化されたりして、部数が万の台に乗ることもなかったわけではないが、私が本筋と思っている著書はだいたい初刷三千、重版なしというのが常態だった。ところがこの本は売れた。ひとつにはそれは、一文の得にもならぬのにことあるごとにこの本を推賞して下さった方が何人もあったからだと思う」*9 という彼自身のはにかみがちな釈明は、しかし言葉通りに受けとるわけにはいきません。
葦書房版『逝きし世の面影』は、一般の読書市場に流れるいわゆる人文書としてはかなり分厚い、そして値段も高い、まずは大著と言っていいものでした。当時すでにそれら人文書の市場は縮小し、そのような本がたくさん売れる環境ではなくなっていた。にもかかわらず「売れた」その理由には、誰それにほめられたからとか、どこそこの媒体に紹介されたからとか、そのような表層の世俗的な事情だけではない何かがあったはずです。それは何だったのか。思うにそれは、そこで論じられている主題を本来ならばまず受け止めるべき本邦の「論壇」ジャーナリズムのありようが、戦後の過程でそれまで成長してきた人文書の市場の縮小が露わになってきたことで、そこに宿っていた世間一般その他おおぜいの読み手らのリテラシーによる下支えを失って閉じ始めていたこと、そしてそれゆえにその自閉に対する「外部」として、本質的な批評性を伴うテキストとして彼の書いたものが作用したのだと思います。 *10
全部で14章から構成されているこの仕事は、そのはじめの一歩、第1章にかけられた重心の低さと、それゆえに与えられることになった初発の起動力の大きさに励まされて、読み進めるに従いなめらかな「おはなし」として加速され、読み手の「読み」の水準に従い流れてゆきます。*11 周知のように、これは近世末から明治初期にかけてこの国を訪れた外国人たちの手による当時の見聞や観察の記録を、彼が改めて読み直してゆくことで成り立っている、その意味では素朴な資料の羅列とその解読の上に立った仕事です。また、主にその微細な細部や断片に合焦されながら並べられ賞翫されてゆくそれら資料にしても、もとはすでに日本語に翻訳され刊行されたものや、邦訳されていなくても国内の大学図書館などのしかるべき場所に所蔵されているもので、敢えてあっさり言い放つならば、手間と時間さえかければそれらに接することは彼でなくともできるようなものだったかも知れません。まして、彼は大学や研究所に所属する正規の学者や研究者ではなく、言葉本来の意味での「在野」の書き手でしかなかった。そんな彼がものしたこの仕事に望外に「売れた」という結果が伴ってきた何か隠された理由があり得たとしたら、それら資料を「読む」という営みそれ自体が結果的に証明していた独自性、他でもない彼、渡辺京二というひとりの読み手を介して発動されたその「読み」と、それを支えた部分に関わるものだっただろうということです。
「日本近代が古い日本の制度や文物のいわば蛮勇を振った精算の上に建設されたことは、あらためて注意するまでもない陳腐な常識であるだろう。だがその精算がひとつのユニークな文明の滅亡を意味したことは、その様々な含意もあわせて十分に自覚されているとはいえない。十分どころか、われわれはまだ、近代以前の文明はただ変貌しただけで、おなじ日本という文明が時代の装いを替えて今日も続いていると信じているのではなかろうか。つまりすべては、日本文化という持続する実体の変容の過程にすぎないと、おめでたくも錯覚して来たのではあるまいか。」 *12
冒頭、このように調子の高い宣言から始まり、そして、「実は、一回かぎりの有機的な個性としての文明が滅んだのだった。それは江戸文明とか徳川文明とか俗称されるもので、十八世紀初頭に確立し、十九世紀を通じて存続した古い日本の生活様式である。(…)文化は滅びないし、ある民族の特性も滅びはしない。それはただ変容するだけだ。滅びるのは文明である。つまり歴史的個性としての生活総体のありようである。ある特定のコスモロジーと価値観によって支えられ、独自の社会構造と習慣と生活様式を具現化し、それらのありかたが自然や生きものとの関係にも及ぶような、そして食器から装身具・玩具にいたる特有の器具類に反映されるような、そういう生活総体を文明と呼ぶならば、十八世紀初頭から十九世紀にかけて存続したわれわれの祖先の生活は、たしかに文明の名に値した。」と、まずこの仕事に挑むに際しての自身の立ち位置と構想について、彼は臆せずくっきりと説明しています。そして、「それを教えてくれるのは実は異邦人観察者の著述なのである」と言い、近世末期から明治初期にかけて来日した外国人たちの見聞とその記述に依拠してそれらの構想を実現してゆくことを言明します。
その上で、「文化」と「文明」の違いを、彼が意図する意味と内実によって繰り返し何度も強調してゆく。この「文明」こそが、彼の明らかにしたかった「逝きし世」としての日本の、ある本質です。
「異邦人たちが予感し、やがて目撃し証言することになった古き日本の死は、個々の制度や文物や景観の消滅にとどまらぬ、ひとつの全体的関連としての有機的生命、すなわちひとつの個性をもった文明の滅亡であった。」 *13
「問題は個々の事象ではなく、それらの事象を関連させる意味の総体なのだ。(…)文化は生き残るが、文明は死ぬ。(…)事物に意味を生じさせる関連、つまりは寄せ木細工の表わす図柄がまったく変化しているのだ。新たな図柄の一部として組み替えられた古い断片の残存を伝統と呼ぶのは、なんとむなしい錯覚だろう。」 *14
「同じことは民族の特性についてもいえる。(…)ある民族の特性とある文明の心性とは、一見わかちがたく絡みあっているにせよ、本来は別ものである(…)死んだのは文明であり、それが培った心性である。民族の特性は新たな文明の装いをつけて性懲りもなく再現するが、いったん死に絶えた心性はふたたび戻ってはこない。たとえば昔の日本人の表情を飾ったあのほほえみは、それを生んだ古い心性とともに、永久に消えさったのである。」 *15
眼に映じやすいモノやコト、具体的な形象だけではない。「民族的心性」といった言い方で、いわゆる文化論的な脈絡では変わることのない伝統の一部として想定されることの多かったそれら内面的な、外側からは観察しにくい領域についても、彼の「文明」からは除外されます。なぜなら、それら心性も「文明」という後ろ楯、それを支えていた文脈との関係でようやくかたちになっていたものと考えるから。そして何より、それら心性が昔も今も変わらず連続的に現在まで存在していると自明に考えたがる、日本語環境における言語空間の習い性そのものに対しての根本的な疑義があるから。それはそのような自明の連続性を前提に想定される「文化」ではない。「文明」はある条件の下で滅びるし、また二度と再生されることもない。
そのような意味で、彼は歴史を、それも自分自身が属している文化の過去の来歴としてのそれを、連続の相においてではなく不連続の相において、もっとはっきり言えば断絶の相においてとらえようとします。そのような「異なる」ものとして、〈いま・ここ〉と決定的に「違う」ものとして見る。つまり「異文化」として、自分の属する自文化の過去の来歴を見ようとする。そのような認識を支える根拠として、文化人類学が介在してきます。 *16
「滅んだ古い日本文明の在りし日の姿を偲ぶには、私たちは異邦人の証言に頼らねばならない。なぜなら、私たちの祖先があまりにも当然のこととして記述しなかったこと、いや記述以前に自覚すらしなかった自国の文明の特質が、文化人類学の定石通り、異邦人によって記録されているからである。」 *17
いささか唐突に文化人類学が持ち出されてくるあたり、当時の知的なモードが反映されているといった情況的な事情も透けて見えなくはない。*18 だが、ここで重要なのは、彼が目論でいる歴史の叙述とは、そのように「歴史」を異文化として見ようとする視点に立脚していること、しかしなおそれが、文化的な脈絡としては今も自らの否応なく属する自文化の過去としての歴史でもあること、という相反しながら同居するこのふたつの要件において、ひとまず彼、渡辺京二の方法意識をその入口で明快にあらわしていることです。*19
とは言え、これだけならば特に目新しいものでもない。人文社会系の領域における文化人類学由来と言ってもいい相対化の視線とそれに伴う視野の拡張は、何も日本語環境の言語空間だけでなく、大きく言えば19世紀から20世紀にかけての世界的な思潮でもありましたし、この場の文脈に沿って日本語環境に限って焦点深度を絞ったところでも先の大戦後、いわゆる社会史的な方向での歴史と文化の複合を全体史・社会史的な視点からとらえようとする試みとして行われてきた。その限りでなら、時代のモード、知的な流行の内側でいくらでも生み出されてきたそれら新しい〈知〉の意匠に忠実な試みのひとつに過ぎなかったかも知れません。 *20
けれども、彼の方法意識の独自性は、単なる文化人類学的な認識の歴史への適用というだけでなく、その上でさらに次のような方向での相対化、書き手としての自分自身がその裡に埋め込まれてある日本語環境を前提とした言語空間の〈いま・ここ〉に対する相対化≒異化をもまた、平然とおこなってみせるところにあります。
「しかし、幕末・明治初期の欧米人の日本見聞記を、在りし日の日本の復元の材料として用いようとするとき、私たちはただちに予備的な検討を強いられる。つまり日本の知識人には、この種の欧米人の見聞記を美化された幻影として斥けたいという、強い衝動に動かされてきた歴史があって、こういう日本人自身の中から生ずる否認の是非を吟味することなしには、私たちは一歩も先に進めないのが実情といってよい。」 *21
自らがとらえようとしている対象、客体に対する相対化≒異化と共に、主体とそれを取り巻く環境に対する相対化≒異化も同等におこなうこと。それは対象に内在している歴史性に気づくと共に、そのように気づこうとする主体もまた同様に逃れられずにいる自らの歴史性についても自明のままに放置しておかない、そのような峻厳とも言える主体としての知的誠実さにまでつながってゆきます。*22
「つまり古い日本を賞賛されることに抵抗をおぼえる心的機制は、けっして戦後の産物ではないのだ。だが当時の日本知識人が歩もうとしていた進歩と強国への道は、今日の彼らの末裔にとっては恥ずべき過去のひとつにすぎない。日本の美化を拒否するという心的機制自体、ひとつの進化の歴史をもつのである。」 *23
このあと、当時の「論壇」ジャーナリズムにとって流行りの意匠のひとつであったサイードの「オリエンタリズム」を引き合いに出しながら、それを単なるモードとしてしか使い回せなくなっている日本語環境での書き手たちの言説の構造をまるごととして明るみに出してゆくくだりの淡々とした、しかし眼のさめるような快刀乱麻の批評性については原著にあたっていただくのが一番でしょうから詳述しません。*24 ただ、この場で問題にしたいのは、なぜ彼がそのような器の大きな方法意識を持つに至り、そしてこの『逝きし世の面影』という仕事の冒頭からいきなりこのような全面全力展開の覚悟で、書き手としてのほぼ全ての重心をこの一点にいきなりかけたかのようなたたみかけ方をするに至っていたのか、そしてそれがなぜ彼に可能だったのか、ということです。

●●● 「思想史」の内実
再度、確認しておきましょう。わが国の戦後の言語空間において、思想史という言い方は、何も学問的なタテ割りの住民登録として輪郭確かな専門性を自明の前提にしたものでもなく、歴史や文化、社会、心理など、いずれ人間を軸にした領域を横断するゆるやかな人文社会系、それこそ戦後のわが国の出版市場での人文書の間尺に幸福にも宿り得ていた読み手のリテラシーを介した、ある種の知性の質をあらわすものでした。*25
そのような意味での「思想史家」である彼が、自己の知的形成過程をふりかえって引き合いに出すのが吉本隆明と谷川雁であり、橋川文三です。
「私が橋川さんの文章を読むようになったのは、昭和三十二、三年頃だったかと思う。ちょうど吉本隆明さんや谷川雁さんの文章に接し始めたのとおなじ頃であった。この三人はいわば私が末弟だとすると長兄にあたる世代の人びとで、日本が戦いに敗れたとき、すでにいっぱしの大人としての判断がもてた人たちだった。」 *26
橋川だけではなく、いやそれ以上に、吉本と谷川についてはさらに前のめりに語る彼の文章も、いくつも認められます。*27 それらには単なる読者というだけでなく、生きていくつかの局面で実際に彼らと行き会う経験をしていたことも挿話として、あるいは印象として含まれていたりもするのですが、しかしそのようなこととは別に、彼らの書いたものを彼が彼自身の「読む」を介しながら、思想に足つけた書き手としての渡辺京二であろうとし続けていたことが、いずれもよくわかるものになっています。 *28
「私は雁さんを知って今年で二十二年になるが、その間彼と行動をともにしたり身近に暮したりしたことがあったわけではなく、ましてや彼のとりまきだったことなど一度もない。彼との関係をひとことで要約すれば、それは遠望する関係だった。(…)だが、私はこの人から確実な恩恵を受けている。その自覚においては私おそらく何人にも劣らない。私は生涯で巨人というべき人をふたり見たと思う。ほかのひとりはもちろん吉本さんである。このふたりが自分に対してもっている意味について今や私は弁別するところがあるけれども、ただ共通なのは彼らが私より一級も二級も上の人だという実感である。これは何よりも文章の手ごたえからわかることであって、こういう感覚はこのふたり以外にたえて感じたことがない。」 *29
「昭和三十三年になって私ははじめて雁さんの詩集を読んだ。『大地の商人』である。ウームと私は思った。ざらにはいないほんものの詩人だということがわかったのである。なおこの年は私がはじめて吉本隆明さんの本を買って読んだ年でもある。『原点が存在する』を読んだのは翌三十四年だったと思う。この年私は家族を熊本において単身東京に出ていたが、おなじ下宿の友人と雁さんの文体について議論して記憶があるから、文体についてだけいうならかなりいかれかけていたのである。」 *30
「吉本隆明・谷川雁はまだ歴史として叙述しうるような思想家ではない。私個人にとってそうであるばかりでなく、今日のわれわれの思想的水位にとって、彼らはまだ歴史的なレヴェルにおいて客観化することができないような思想家として存在し続けている。」 *31
これだけ抜き出せば空虚な惹句、よくある凡庸な、それら読書市場で広く読まれるようになった書き手に必然的にあらわれる信者的な読者の手による、ためにする称揚の和讃と片づけられかねないかも知れませんが、そうではない。彼は「ある思想家が歴史として客観化しうる段階にあるかどうかということは、彼が思想的生産を続けているか否かによっては判定することができない」と言います。思想とは本質的にその時代その情況も含めた「歴史的構造」に根拠を持つものでなく、むしろそのような時代的根拠を支配するものである。だから、彼らの思想的な仕事は「たとえそれが十年前に書かれたものであっても、そのように歴史として叙述することは不可能である。それは、彼らの思想が時代的根拠を支配しきろうとする思想であり、歴史的な既知の文脈におさまらぬ、いわば時代の歴史的構造から超出しようとする思想家だからである。」 歴史的構造、言い換えれば自分自身もまたその裡に抱かれ生きている〈いま・ここ〉のまるごとについて、しかしその内側からそれを超えてゆき得るような思考のありよう、それこそが思想の思想たる所以なのだ、と。 *32
なるほど、このような認識に立つ以上、ものを考える際のその客体としての対象がこちら側の自分とは別の水準の現実にあるとは思わないでしょうし、その考えた結果についてもまた同じでしょう。彼にとっての思想とは、そのような射程距離で考えられるはずのものらしい。そして、そのように思想を実践しようとする際、吉本や谷川などと同じように、彼もまた「民衆」ととりあえず呼ばれてきたような形象を、彼の言う歴史的構造を超えてゆくための足場にしてきたようです。 *33
まだ若い頃に書いた「民衆論の回路」という、今からすると若書きかも知れない、でもその分みずみずしい自省の気配にあふれた文章で、彼はそのような形象が実体を伴って眼前に現われた瞬間をいくつか、印象的に描いています。たとえば、彼が結核を患い療養所に入った時に出会った三人のひとりで、隣りのベッドにいたSという十歳ほど年上の「ひどい気むずかし屋というので看護婦たちの敬遠の的となっている」青年のはなし。
「彼は死ぬ数ヶ月前に、私にヘーゲルの『小論理学』をくれた。開いてみるとそれにはいたるところに傍線が引かれていた。その引きぐあいをみると、彼がこの難解な哲学書をおよそ自己流に読破したことがよくわかった。彼はこの哲学書をその理論構成をたどって教養的に理解しようとつとめたのではなく、ただ自分にひきつけて気に入ったところを読んだのである。そのようにしてこの文庫本二冊のヘーゲルを読みとおしたのである。(…)庶民とはこういう本の読みかたをするものだな、と私は思った。私はこのとき民衆と教養ないし知識との関係について、本質的な理解の端緒に立っていたはずである。」 *34
民衆論というかたちで「民衆」を語る、そのことが何かひとつの正義として持ち回られるような情況がまだあった頃のことです。その真只中で彼は「今日では民衆論というテーマは、懐疑とはにかみを知らぬよほど無神経な知性か、あるいはいつまでも感傷と錯誤のぬるま湯につかりつづけようとする薄弱な精神にふさわしい、うすよごれたテーマにまで落ちこんでしまったような気がする」と言挙げし、「少なくとも私には、民衆論という正面切ったかたちで自分の主題を展開することに対する根深い嫌悪がある」と明言しています。しかしそれでもなお、「私はこのテーマからのがれることはできない。これまでのがれることができず、これからものがれられない」と言い、先にあげたような挿話、おそらくは彼にとっての「大衆の原像」であったような邂逅や記憶をちりばめながら、吉本隆明を引き合いに出しつつ「大衆の原像についてのこのような観点は、もとより孤立した恣意的な直観としてのべられているのではなく、人間の観念的上昇の極限と、生活的存在の最下限のあいだにひろがる幻想の総過程についての、およそ徹底的な考察のなかに根拠づけられている。だがこれをひとつの直観としてうけとってみても、われわれは戦後三十年の思想的経験がこの一点に修練せざるをえないことをなっとくできるのである」と結論づけています。*35その程度に彼もまた当時、吉本の「大衆の原像」という言葉に何がしかの意味を見出していたのであり、その限りにおいてまた、当時の読書市場におけるその他おおぜいの匿名の人文書読者のひとりでもありました。 *36

●●●● 「おりる」と「往還」
吉本隆明の「大衆の原像」は、谷川雁の「工作者」と共に、戦後の日本語環境に依拠した言語空間において、良くも悪くも同時代の思想的水圧が最大限にかけられる切羽になっていたことは、今さら言うまでもないでしょう。それらをめぐって生み出された数々の著作や文章、発言などはすでに種々膨大なものになっていますし、それらを元にさらに二次的、三次的な言及、引用、参照の系は未だに紡ぎ出されています。
このような系の形成とその転変は、いわゆる学会などのアカデミズムにおいてはそれぞれの領域に枠取りされた範囲での「業績」の蓄積とその上に立った「議論」「対論」というやりとりの応酬として、そしてまた論壇や文壇などのジャーナリズムにおいても同様に「批評」や「評価」といったラベルを伴いながら、同じく蓄積とその上に立った定番の安定した評価が形成されてゆく過程として、いずれも一般に理解されていると思われます。
けれども、その時代の情報環境とそれらを可能にする技術的基盤を前提にして成り立つ言語空間の内側で、それらが言わばエコーチェンバー的な効果をもたらし始めるあたりの事情は、読書市場を介して一定以上の読者に読まれるようになった知名度の高い書き手の仕事を素材として考える場合に、無視できない偏差としてあらわれるもののようです。これもまた、読書市場の大衆化が進展してゆくことで必然的に起こってくる現象ではあるのでしょうが、概ね60年代半ばあたりから少しずつ顕在化してきて、70年代から80年代にかけて本格的に全面化していった印象があります。それこそ柳田國男をめぐる評価の高まりとブームとまで呼ばれたような現象などもその初期の事例であり、同様に吉本隆明であれ谷川雁や橋川文三、あるいは鶴見俊輔などであれ、いずれそういう情報環境と読書市場において「広く読まれるようになってしまった」書き手の読まれ方とそれらの系に宿っていった「評価」というのは、そういうエコーチェンバーが形成されていった過程をも同等に対象化しながら複線的に「読む」ことを駆使できるだけの、同時代の情報環境を動態的に見ることのできるリテラシーが実装されていないと、単なるチェンバー内の凡庸な劣化相互コピーを粛々と生み続けるだけになってゆく。そのような〈いま・ここ〉をその内側からそのものとして見ることができるようになるためにこそ、同時代の情報環境に知らぬうちに埋め込まれて稼動するようになっているらしいこれらの系から距離を置く、方法的に「おりる」という意識が必要になってきます。
彼はこの「おりる」ことを自身の方法として実践してきた。少なくとも現在の地点から彼の仕事をその来歴と共に振り返ってみた時に、たとえ結果的にそうなったものにせよ、背骨のようにそれが一貫してあることが看てとれます。
けれども、その背骨を方法意識として形成していった過程と引き換えに、時代はその情報環境と共にまたひとつ、別の不連続、いや、もしかしたらすでに断絶になりつつあるかも知れない相を、〈いま・ここ〉の眼前に呈しつつありました。
「だが、何と遙かなところまで来てしまったことだろう。吉本、谷川、橋川と名前がなつかしくも浮び上がってくるような、ある時代的な問題設定、竹内好、花田清輝、平野謙といった彼らよりひとつ上の世代の設定に挑戦しながらなおかつ土俵を共有していたような問題の枠組は、いったいどこへ消え去ったのだろうか。思えば彼らの思想的ないとなみは、大正末年から昭和三十年代まで続いたわが国近代のある思想的局面の最後の輝きにほかならなかった。」 *37
ちょうど同じ時期、他の場所では「大正末期から昭和三十年代までは、思想的にはひとつの時期と見ていい」という自身の時代認識を前置きしながら、「いまの若者に、私たちに常識となっている思想的問題設定がまったく通じないようになっている」とも言っている。
「四十年代の前半、大学闘争が吹き荒れたころまでは、若者と私たちは話が通じていた。つまり当時の反逆的な若者たちは、ポーズはいくら過激であったとしても、たとえば「人民に奉仕する学問」といったスローガンひとつ見てもわかるように、はなはだ古典的な問題提起を行っていたのである。状況の全面的な転換は四十年代の後半に訪れたようだ。それがちょうど、高度成長による社会構造と大衆意識の変革が一段落ついた時期であったことはいうまでもない。」 *38
1985年、『逝きし世の面影』の第1章のあの書き手としての全体重をそこにかけたかのような重心の低さをもたらすことになったらしい「ポストモダン」的言説が、おりから持ち回られるようになっていた情報資本主義だの高度消費社会だのという目新しい意匠に飾りつけられながら「論壇」ジャーナリズムの舞台を席巻していた、そのほぼ真っ只中と言っていい時期です。
この後、「むろんその局面とは、マルクス主義と近代的自我の観念によって領導された特殊な史的プロセスであり、その終焉をもたらしたのは個人を超えた時代の力とせねばならない」と簡潔に言い切ってみせる彼は、高度経済成長とその「豊かさ」が昭和30年代以降のこの国の社会にもたらした変化について、「個」の側に立つことでひとまず肯定的にとらえる立場に軸足を置いています。*39 と同時に、自分もまたそのような時期の思想的局面において人となり、「豊かさ」を介して現前化した不連続の気配をはらんだその後を生きながらものを考え、書いてきたひとりであることもまた自覚している。しているからこそ、そのような“最後の人”のひとりとしての自覚からもう一度、「おりる」を方法とした主体の、“最後の人”としての命脈についても省みなければならなくなっていたはずです。思えば、あの第1章に至る下ごしらえは、期せずしてすでにこの時期、彼のまわりで始まっていたと言っていいでしょう。
その「おりる」におそらく通じてくるような身の処し方、処世の仕方について、同じ80年代の半ば頃、他ならぬ吉本隆明はこんなことを言っていました。
「つまり表現には往き還りということがあって、往く表現と還る表現というのがあって、往く道だけはさっきの社会的なメカニズムや制約が授けるだろうとおもいます。だからそういう、自己制約というか、社会的条件のなかに自分が不可避的に這入り込んだら、そういう状態を肯定しろっていうのです。往く道では肯定しちゃえ、絶対否定するなってかんがえるのです。多分、すべての反体制的な表現者とぼくが違うのはそこだとおもうのです。(…)社会メカニズムの直截性によってピックアップされて出てゆくこと、これは絶対に肯定せよ、それは往く道だけはプラスになるんだ、ということなんです。だが、還る道ではマイナスに作用して、風俗化を受けるってことは間違いないということなんです。往く道の限度までゆくとね、現代社会のメカニズムは表現者を風俗化させ駄目にするという働きしかしないんです。だからこそ、還れなければならない。還る、ということが現代の表現の、大事な問題なんです。(…) ただ往きっぱなしになるっていうこともある。本来は還る道に来るところを、往きっぱなしになるとこれは風俗化するとおもう。だからね、還る道にさしかかるときに、表現に全体的な課題が現れることになるだろうってことなんです」 *40
吉本のこの発言は、当時のいわゆる「ポストモダン」的状況においての大衆文化の位置づけと、それを考える主体の立ち位置についての考察を、彼なりに懸命に続けて悪戦していた頃のものです。「表現者にとっての現代」というタイトルがつけられていますが、拙速で雑なつくりの発言集といった造りの本に収められたものなので、前後の脈絡や発言の背後にある含みなどはそのままではうまく引き出せない憾みが正直、ある。けれども、ここでの「往還」という言い方に託された彼の方法意識は、ここで語ろうとしてきた渡辺京二の「おりる」と基本的に通底しているはずのものです。そしてそれは、コミットメントとデタッチメント、といった枠組みだけで平板に、構築的戦術的にのみ語られているふしのある、いわゆるフィールド・ワークや取材、現地調査の類の営みについての方法意識の今日的な情報環境における実践的な更新の試みとも、どこかで地続きになってゆくようなもののようにも思えます。
「現在」という水準に敢えて引き出され、そこに往こうとすることは、しかし同時にデタッチメントに等しい「おりる」過程もまたどこかで想定されておかないことには、必ずコミットメントの果てにそもそもの目的から見失われてしまい、ついには「自分」が何者であるか、その「自分」によって何を表現しようとしていたのかまでもわからなくなる奈落へと自ら落ち込んでゆく危険性がある。ここでの吉本は親鸞を引き合いに出してこの「往還」という言い方をしているのですが、しかし、そこに当時、直感的にせよ感得されていたであろうこの「還る」過程の重要性は、単に表現者が〈いま・ここ〉に立ち位置を確保しようとする場合のことだけでなく、ある主体が自分も含めてそこに属している〈いま・ここ〉の現実にコミットしてゆこうとしてゆく際の、しかしその後いずれ行なうことになるはずの表現との関係で計測しておかねばならないある関数について自覚し、方法化してゆくことの必要を、期せずして言明したものになっています。
渡辺京二の、殊に彼が「逝きし世の面影」に至る仕事の過程で一貫して彼自身の方法としてあたかもある節操を守るかのごとく保ち続けていたように見えるものもまた、このような「還る」過程の重要性を十分に意識した「おりる」という方法意識でした。そう言えば、彼が『逝きし世の面影』のもとになったという連続講演会を行った寺も浄土真宗の寺でしたが、そのことと彼のこの「おりる」方法意識との関わりの可能性については、また別の機会に考えてみたいと思います。

*1:渡辺京二「地方という鏡」、「地方という鏡」、『地方という鏡』所収、葦書房、1980年、p.259。
*2:渡辺京二「編集後記」、『暗河』創刊号、葦書房、1973年、P.142。
*3:山松ゆうきち「松五郎伝」、『にっぽん自転車王』所収、日本文芸社、1990年、p.105。
*4: 平川祐弘「解説――共感は理解の最良の方法である」、『逝きし世の面影』平凡社ライブラリー、2005年。ただ、彼自身は「私は自分を分類すれば書生とでもいうほかないことを十分承知」して「生涯書生以外の何ものでもありたくない」と、早い時期に言ってはいる。(「情況という空間」、『伝統と現代』40号、1976年7月。『日本コミューン主義の系譜』所収、葦書房、1980年。『新編 小さきものの死』(渡辺京二評論集成Ⅱ)再録、葦書房、2004年、p.151,152)
*5: 「思想史」と言った場合に一般的に想起されるような、学術的な世界観でのある立ち位置や住所といった意味ではなく、戦後のわが国の大衆社会化に伴い形成されていった読書空間――出版や図書流通に携わる業界で「人文書」と称されていたような領域を中心とした書籍と、それを求めていった読者のリテラシーとの相互性の裡に成り立った読書市場がもたらした、主に「歴史」や「文化」「社会」などを足場にした大衆的な〈知〉のありようを意識した名づけ方である。「史」とはいうものの、これもいわゆる歴史ではなく、民俗学的思考を裡に包含した歴史文化的な志向性をその本質とした知性という意味もあること、言い添えておきたい。「思想史」という言い方は何も学問的なタテ割りの住民登録としてではなく、歴史や文化、社会、心理などを横断するゆるやかな人文社会系、それこそ出版市場での「人文書」の間尺に宿り得たある種の知性の質をあらわすものである。
*6:2008年度より本学人文学部で開講してきた「和の精神史」という講義において、この『逝きし世の面影』をテキストとして受講生と共に毎年、講読を続けてきている。実際の講義に際して、質疑応答からレポートや試験答案などを介して応答し、ただでさえ逼塞しがちなご当地の研究環境において、折に触れ刺戟や補助線を与えてくれた社会人学生も含めた学生諸君に、この場を借りて深く感謝しておきたい。
*7:民俗誌・エスノグラフィーにおける記述から発して、日本語を母語とする環境においての文化や歴史、社会や思想、文学などにゆるやかにまたがる領域での散文的な記述と文体の来歴という、自分にとっては学生時代このかたの古い、しかし未だ常に更新され続けている新しい問いに連なる問題意識の一端であることは言い添えておきたい。
*8:「ひとつのきっかけが、真宗寺というお寺で、日本近代史の題目で月二回話をするようになったことにあるのは確かだ。これは一九八〇年十月から一一〇回続いて、八五年五月に打ち止めとなった。」(「あとがき」(初版時のもの)『逝きし世の面影』平凡社ライブラリー版、2005年、p.581。) 「一九八〇年代の後半から九〇年代の前半にかけて、私は全くではないけれど、ほとんど文章の業を断っていた。(…) この期間私は真宗寺というお寺で、「日本近代史講義」「人類史講義」というふたつの長期連続講義を行い、さらには人間学研究会なるものを組織し、毎月二回の読書会を催していて、これが私の当時の知的活動のすべてといってよかった。」(「あとがき」『日本近代の逆説』(渡辺京二評論集成Ⅰ)所収、葦書房、1999年、p.478。)
*9:「平凡社ライブラリー版 あとがき」、註5に同じ、p.585。
*10:この見立てが当を得ているかどうかの判断は、この場の行論でだけ決められるものではないだろうし、そのための今後の作業の心づもりもそれなりにあるつもりではある。ただ、当時そのように一般的な読書市場から疎外され、自閉を始めていた「論壇」ジャーナリズム――そしてそれは「学界」アカデミズムともすでに癒着し、複合するようになっていて、それまでのジャーナリズムとアカデミズムという問いの立て方自体がすでにもう〈いま・ここ〉から置いてゆかれるようになって久しかった――の言語空間に対して、それらを疎外した側の世間一般その他おおぜいの人文書読者たちの「読み」の側に期せずしてシンクロする部分があったからこそ、彼のこの仕事が情況的に響いたという見立ての〈リアル〉については、個人的な記憶としてもある確かさと共に言い添えておきたい。そのような彼の視点や立ち位置が輪郭を整えてゆくに際しては、70年代後半から80年代にかけて『西日本新聞』紙上で続けていた地元の同人誌についての月評の仕事の経験が重要な触媒になっていたのは間違いない。 「私はこの手の雑誌を三十年前に見たことがある。つまりこれは、火焔壜時代の日共文化政策が奨励したあの生活記録サークル誌の再現なのだ。つまりわれわれの戦後とは、かつて生活記録を書いていた文化的大衆が小説を書くようになっていた進化のことなのだ。」(「地方という鏡」、『地方という鏡』所収、葦書房、1980年、p.253。) それまでの「文壇」幻想を、それを支える集団の共同性と共に疑うことなく維持することが目的となって陳腐化していた地方の同人誌の旧態依然に対して、誰もが横並びの単なる発表の「場」として新たな活気をもたらし始めていた新しいタイプの同人誌とそこに集う作家と作品のありようについてのこの評言の炯眼には、当然、「論壇」ジャーナリズムの疎外と自閉を呈し始めていた情報環境と言語空間に対しても、同じ情況が裏返しにあてはまるように見えていたはずである。
*11:この14章の章立ては、その章題の選び方も含めて、柳田國男の『明治大正史世相篇』を彷彿させるものがあることは、先の講義でも繰り返し言及してきている。「陽気な人びと」という当時の庶民・常民層を中心とした日本人に対する外形的な観察の類から入り、「簡素とゆたかさ」「親和と礼節」などでそれら人々の間に宿っている感情や気分のありように眼を向けてゆき、「雑多と充溢」で彼ら彼女らが集団として社会的局面において見せる立ち居振る舞いから「労働と身体」「自由と身分」へと、いずれ動態的に動く生身の身体性の位相へと徐々に合焦、さらに「裸体と性」「女の位相」「子どもの楽園」と生物的な存在形態とそれに伴う性的領域も含めた生きものとしての〈リアル〉が当時の社会の裡にどのように定位されているのかという角度から、彼ら彼女らの生きていた現実の全体像へと視野をふくらませてゆく。当然、そこから先は風景や生きもの一般、人々もそこにあたりまえに包摂される「自然」の側へ視野を広げてゆき、最後は再び「信仰と祭」「心の垣根」と、それら「自然」との関わりを視野に入れることによって初めて十全に解釈され得るような、内面や精神生活に関わる部分にまで考察の足どりを伸ばしてゆく。眼による観察から始まり、「自然」の裡に生きる人間という存在のありようについての視野を獲得してゆき、それらを足場に再び最終的に人々の意識、内面へと向かうこの組み立ては、柳田が近代化の過程を〈いま・ここ〉からとらえなおそうとした『明治大正史世相篇』の「おはなし」としての誘導の手つきと共通する、ある方法意識が見てとれないだろうか。
*12:註5に同じ、p.10
*13:註5に同じ、p.16。
*14:註5に同じ、pp.16~17。
*15:註5に同じ、p.17。
*16: 文化人類学が自文化を対象として相手どるようになったのは、概ね先の大戦後、それまで研究対象として想定されていたアジア・アフリカ諸国が独立するようになり、それに伴いいわば研究対象だった側から文化人類学を学ぶ者が増えてきて、彼らが自らの属する文化を対象とした研究を行うようになってきた経緯があると言われる。自文化研究と呼ばれたそれらの流れはその後、応用人類学や都市人類学、医療人類学など、いずれ〈いま・ここ〉の社会的な問題や課題に積極的にアプローチする方向を産み出し、北米などで顕著なようにいわゆる社会学などその他の人文社会系領域との棲み分けも、研究対象的にも、そして方法論的にもどんどんなし崩しになくなっていった。 「自文化研究、という文化人類学にとって新しい流れが顕在化してきたのは、80年代だった。北米の人類学が大学や大学院で勢力を拡張してゆくに連れて専攻する学生が増えたこと、それに伴い大学院を出た彼らの就職先が少なくなっていたこと、などが理由とされているし、そのことは本稿でも概略触れられている。だが、そもそも大前提としてあったのは、世界から「エキゾチック」な「未開」が失われてゆくという、文化人類学という学問領域自体の来歴に本質的に関わる事態が前世紀半ば以降、地球規模で進行していったことだったのは言うまでもない。そんな中、アカデミックな仕事以外に自分たちの専門性を活かした職を求める若い世代の中から、敢えて「自文化研究」に赴く者たちが出てきた」(拙稿「解説 D.A.メッサーシュミット「「手もと足もと」での人類学について――文化人類学における「自文化研究」の今日的意義」」、『札幌国際大学紀要』、2015年、p.※※※)
*17:註5に同じ、pp.18~19。
*18:70年代あたりから、文化人類学(民族学)はわが国の「論壇」ジャーナリズムにおいても、人文社会系の領域を中心にそれまでと異なる新たな認識枠組みをもたらす知的領域としてもてはやされるようになっていたし、それはまた、当時新たな内実と広がりを獲得し始めていた一般的な読書市場にも浸透していた。殊に、いわゆるマルクス主義的な認識枠組みを良くも悪くも自明の前提に展開してきたところのある戦後の言語空間に対して、あるカウンターとなり得る認識や視点を提供してくれそうな領域として迎え入れられていたところもあった分、当時の彼の匿名の読書人としての「読み」の傾きにもなじんだのだろう。
*19:彼自身がそのような同時代の裡に生きていたこと、そして一般的な読書市場の匿名の読者のひとりとしてそれらの知的モードを受け止めていたことと共に、しかしそのようなモードを生み出してそのかりそめの熱狂に共に身を投じる同時代の読者の趨勢に対しては、その「おりる」方法意識をしぶとくも駆使していたらしいことは、同じ頃、長崎大学の新入生に対する講演「ポストモダンの行方」(1988年、『荒野に立つ虹』(渡辺京二評論集成Ⅲ)所収、葦書房pp.26~60)などにも鋭角に示されている。 「人間は自然と距てられた本能を喪った動物だ、ゆえに欠陥動物だというのは、実は裏返された巧妙な人間市場主義であることに注意していただきたい。ポストモダニズムは自然による拘束あるいは規定からのがれたいという欲求の明白な表現です。その意味で彼らはまさにウルトラモダニストであります。」 「こんなことを言うと笑われるでしょうが、私は隠者の思想はマルクスの思想であると思っているのです。マルクスは資本制社会では、人間関係はすべて商品に媒介されて現われると考えました。そして、そのような社会的関係性をひっくり返したところに、人間の類的存在としての本質が顕われるのだと考えました。(…)人間の社会的存在を仮象とみなす視点、その存在形態からわが身をひき離す視点は、それこそ日本の隠者と通底するところでありまして、来るべき未来を考える上で手放してはならぬ思想なのではありますまいか。」
*20:このような社会史に対する彼の理解やその上での同情的解釈(「声援」とも彼は書いている)については、「社会史の帰趨」(『毎日新聞』西部版、1983年6月~9月。『隠れた小径』(渡辺京二評論集成Ⅳ)所収、葦書房、pp.31~34)その他の文章で当時、随時あらわされている。それは、同じ頃に出された社会史に関連する一般的な人文書よりは学術的な色合いの濃い書物、たとえば、ジャック・ルゴフ他、二宮宏之・編訳『歴史・文化・表象――アナール学派と歴史人類学』(岩波書店、1992年。ただし所収の講演やシンポジウムなどは70年代半ばから80年代にかけて行われたもの。)、関一敏・編 川田順造・関本照夫・野村雅一・福井勝義・著『人類学的歴史とは何か』(海鳴社、1986年)などに見られるような専門的な研究者たちによる理解や議論の水準とは良くも悪くも異なったところがあるし、またそれは当然のことなのだが、しかし、それら社会史の仕事を共に「読む」という一点において、そしてその「読む」を介して読み手としての自分自身もまた自省の相に繰り込まれ続けるという態度において、最も良質な、そして言葉本来の意味での批評的読み手であるような主体の輪郭を立ちあらわすものになっている。すでに古びかかっている語彙を敢えて使うならば「歴史と文学」といった命題にも重なってくるような、しかし言葉と現実の間に紡がれざるを得ない関係に常に宙吊りになりながら何らかの記述や叙述を続けなければならない書き手にとってかなりの程度普遍的であろう問いについて、方法としての「おりる」を前提としながら誠実に考えようとする主体のあり方はここでもまた、彼のその書いたものを読むこちら側の裡にまで否応なく食い込んでくるものになっている。その限りにおいては、「歴史」「文学」と「思想史」のあわいの居心地のあまりよくない領域についても、そのような主体のありように見合った程度には、あるすわりの良い了解の座を与えてくれるものになっていると思う。
*21:註5に同じ、p.20。
*22: 「思想」という言葉に彼が込めてきたものも、おそらくそのような知的誠実さが必然的に主体に実装させてゆくことに伴って整えられ得るような、ある「個」の輪郭と共にあるだろう。「文学にとってまた思想にとって」といった言い方を彼は好んでするところがあるが、よくできた物語としての結構を備えた作品に対して「しょせんこれはお話ではないのか。私たちが文学を必要とするのは、こういうお話が必要だということなのか」と反語的に鋭く問いかけるあたりを見ても(「何が文学なのか」)、それらは共に、表現としてある定型となっている水準を他ならぬ自分自身の手もと足もとの生活意識の宿る現実、「風土の肉体性、その肉体性に包まれて存在せざるをえない人びとの暮らし」(「もうひとつの〈アジア〉」)から出発する表現によって相対化してゆこうとする営みといった意味でほぼ同義でもあるらしい。そのことは、「われわれの所有する現実を再発見するということで、それがつまりは文学なのである」(「何が文学なのか」)「自分の気持ちと、自分の眼に見えているものに、どうすれば文章がうまく密着してゆくか、この作者はつねにそのことを考えているのだ。(…)文学とは何よりまずこういう文章の質感のうえにしか、成り立たぬのである」(「文学的根拠としての質感」)などのその他の言明などと併せれば、より明らかになってくるだろう。(カッコ内はいずれも『地方という鏡』所収、註1に同じ。)
*23:註5に同じ、pp21~22。
*24:この一連のくだりで彼が本質的に問うているのは、そのようないまどきの日本語環境の、それも一般的な読書市場のその他おおぜいの読み手の下支えを喪失して自閉を露わにするようになっていたアカデミズムとジャーナリズムの癒着・複合的言語空間において、「思想」本来の十全な「読み」もできなくなっている知識人たちのリテラシーであり、それに対する疑念と不信感である。それは期せずして当時の、80年代から前景化してきた「ポストモダン」と称されてもいたわが国のそれらジャーナリズムを中心とした言語空間に対する本質的な批判になっている。またそれは、先に触れた「文学」に関して彼が見た、当時すでに現前していたある頽廃のありようともおそらく通底している。
*25:そのような意味では、この「思想史」という言葉は「思想」の「歴史」という字義通りの平板な意味ではなく、「思想」と「歴史」を共に主体の手もと足もとに制御できる限りにおいて統合しようとし、それを「文学」の相にできる限り開いてゆくような表現に託してゆく、そのようなアウトプットへの志向性をはらんだ内実も持っている。それは、橋川文三を評して中村雄二郎が「史談家」と、いささか雑な言い方で表現しようとしていたこととも、どこか通じているはずだ。 「橋川文三は稀有の史談家だったと思う。史談家という呼び方は、彼の持ち味と仕事にぴったりする呼び方はないだろうかと探してきて、なんとか見つけたものだ。つまり、独特な語り口をもった歴史家ということである。」(中村雄二郎「史談家橋川文三」、『橋川文三著作集』第2巻月報、筑摩書房、1985年3月) ただし、これが「史談」というもの言い自体に内在している歴史性についてまでも意識した上でのことだったかどうかは、判断を留保しておきたい。
*26:「悲哀と放棄」、『橋川文三著作集』第2巻月報、筑摩書房、1985年9月。『隠れた小径』(渡辺京二評論集成Ⅳ)所収、葦書房、2000年、p.331。
*27: 「歴史と日常――橋川文三氏によせて」『九州大学新聞』1966年1月~2月号、『新編 小さきものの死』(渡辺京二評論集成Ⅱ)所収、葦書房、2004年、pp.354~369。 「六〇年安保と吉本隆明・谷川雁」『伝統と現代』31、伝統と現代社、1974年11月。『小さきものの死』所収、葦書房、1975年、pp.11~28。 「わが谷川雁」、谷川雁『原点が存在する』しおり、潮出版社、1976年。『新編 小さきものの死』(渡辺京二評論集成Ⅱ)所収、葦書房、2000年、pp.305~328、など。
*28:橋川文三とは『日本読書新聞』の編集者として、吉本隆明とも同じく編集者として行き会っていることを明らかにしているし、谷川雁とも地元熊本の小さなサークルを介したやりとりなどがあった。また、上京して編集者になる以前、『日本読書新聞』に載った彼の原稿に対して投書したものが掲載され、それに対して橋川から実名入りの返信原稿が掲載されたこともあった。いずれにせよ、彼ら「長兄」たちに対して、読者としてだけでなく現実にも末弟のようにつきあってもらえる関係をそれなりに持っていたことがうかがえる。このあたりのことは、最近でも『朝日新聞』連載インタヴュー(「語る――人生の贈りもの」欄、2018年12月)で語っている。
*29: 註27の3番目の資料に同じ、p.306。
*30: 註27の3番目の資料に同じ、p.316~317。
*31:註27の2番目の資料に同じ、p.11。
*32:註27の2番目の資料に同じ、p.12。このあたり、個別具体の半径等身大の〈リアル〉から何らかの普遍へと抜けてゆこうとする、それこそかつての花田清輝などにも通じる方法意識も感じられなくもないが、ただ、彼にとっての彼岸としての「普遍」の輪郭や手ざわりもまた、それら構築的な言語の作法によって現出されるものではないだろう。そのあたりは、“盟友”石牟礼道子の仕事に対する彼の「読み」の内実などにも関わってくる問いになる。一昨年、彼女が逝去した後、さまざまにコメントや評言を彼に求めていたいまどきのメディア界隈の動きは、彼のそのような「読み」についてどこまで理解した上でのことだったのか、傍目にもはなはだ心もとないものだった。
*33:このような「思想」を手がける主体は、その輪郭を自ら確かめつつ明確にしてゆくために〈それ以外〉の足場を必然的に設定せざるを得なくなる。そこに同じく抱かれながら、しかしそことの断絶も同時に鋭く意識し続けざるを得ないような主体の意識。先に触れたような彼がその主体の重心をかけて繰り返しこだわった「文化」と「文明」の、それ自体としては一般的にちょっと理解しにくいような使い分けにしても、コミットメントとデタッチメントを分離的な過程としてではなく、常に同時進行の現在として内在化する、このような主体の意識を成り立たせている構造と密接に関わっているだろう。
*34:「民衆論の回路」、『終末から』9号、1974年10月。『日本コミューン主義の系譜』、葦書房、1980年。『新編 小さきものの死』(渡辺京二評論集成Ⅱ)所収、葦書房、2000年、p.35。
*35:註34に同じ、p.41。
*36:戦後の読書市場の拡大、殊に高度経済成長の「豊かさ」に下支えされた質的な変貌も含めたその過程は、その前提となった大衆社会状況を外来のものも含めたありあわせの概念の組み合わせで客体として把握し理解するのでなく、その内側から内在的に身の丈の間尺から乖離しない言葉で認識しようとしてゆく傾きを持つ主体を結果として広く準備することになった。それは、吉本や谷川などを「長兄」として読んできた未だ戦前生まれだった彼の世代からさらに下、戦後生まれのいわゆる団塊の世代あたりから一層広範な、同時代の世相風俗的なあらわれとしても顕著なものになってゆく。 「全共闘世代は大学進学率15パーセント前後。高等教育のエリート段階とマス段階の中間段階だった。いまやただのサラリーマンがかれらの未来になりはじめた。しかも、多くの大学生の親は高等教育を受けていない。大学第一世代である。大衆を啓蒙の対象とするような思想を欺瞞的にみる世代が大量に大学進学した。かくて大衆の原像をたえず思想に繰り込むことを提唱した吉本隆明こそが範型となった。啓蒙型知識人の道に予期できる未来を感じ得ないから、それでも知識人として生きていきたい中間期の学生たちには、山の手知識人の丸山眞男よりも下町知識人の吉本こそ自分達の範型であった。」(竹内洋『大衆の原像』、中央公論新社、2014年、pp.116~117。) そのような主体の特質のひとつとして「おりる」ことと密接につながる匿名性があったことは、身の丈の関係と小さな場に無意識裡にせよ拘泥してゆく心性と共に、この世代においてもはっきりと認められる。ただ、彼にとっては年下にあたるそれら団塊の世代に対する断絶の感覚は時代の変貌への違和感と共に、また根深いものでもあったらしい。 「私にとって若い人というのは武田さんの世代(対談の相手の武田修志。1949年生まれの団塊の世代……大月註)になるんです。水俣病闘争に関わった人たちですが、変わるんですねぇ、人って。彼等は「真実」という言葉を聞いただけでせせら笑う。マルクスも読んでいないし要するに無知なんですが、感性的には戦後の思想史をおさえているからいっぱしのことは言う。(…)彼らの中では左翼崩壊とポストモダンが重なっていて、いかなる言説も可能なんだ、と思っている。何もかもバカにしたような言説が通用していく。倫理とか生きるスタイルの解体の仕方は深いなあ、と思います。何か伝え損なったという気がしてならないんです。」(「知識人のあり方を問う」『読売新聞』西部版、2002年10月10日~18日。『渡辺京二対談集 近代をどう超えるか』所収、弦書房、2003年、pp.159~60。)
*37:註26に同じ。pp.331~332。
*38: 「戦後思想の行方」、『熊本日日新聞』1985年9月1日(原題「戦後相対主義の泥沼」)、『荒野に立つ虹』(渡辺京二評論集成Ⅱ)所収、葦書房、2004年、p.91。)
*39:彼の考える「個」とは、通例考えられるような近代的な「個人」のありようからは異なってくる。集団と個人という問いから始める立てつけは一見、同じに見えても、そのような問い自体が成り立つ前提や、それらの問いを発するこちら側の主体との関係から視野に入れようとすることで、われわれが日々「そういうもの」として生きてある身の丈の生きる関係や場に即した「個」のありようを、まるごとの歴史の相において思想の側へと解き放とうとしているように見えることがある。 「有史以来、人間がおのれの最後の砦としてまもり抜こうとしてきた個は、近代的価値としての個性とか独自性とは何の関係もなかった。個はつねに集団の中にあった。人間は集団の中に生きるように定められ、そのような運命のうちによろこびをも見出して来たが、それと同時に、集団にそむき群から離れようとするおのれの性(さが)を自覚し、その性をけっして手放そうとしなかった。そのような離群によって浮上する彼のおのれの側面こそ個であって、そのような個は集団とともに生きねばならぬ彼の生のかくれた核心を構成したのである。個とはむろん、俺はほかの者たちとは違うという感情であったが、それは決して個性とか才能とか独自性という観念を含むものではなかつた。他者が平凡であれば、おのれも平凡であった。ほかの者とは違うというのは差異を意味したのではない。根本のところで他者と切り離されることの自覚であり、従って個とは孤にほかならなかった。」、「いま何が問われているのか」、『望星』1990年11月号(原題「文明と人間の再生をめざして」)、『荒野に立つ虹』(渡辺京二評論集成Ⅲ)所収、葦書房、2004年、pp.21~22。
*40:吉本隆明「表現者にとっての現代」『写真試論』1号、劇書房、1979年5月。『大衆としての現在』所収、北宋社、pp.168~196。