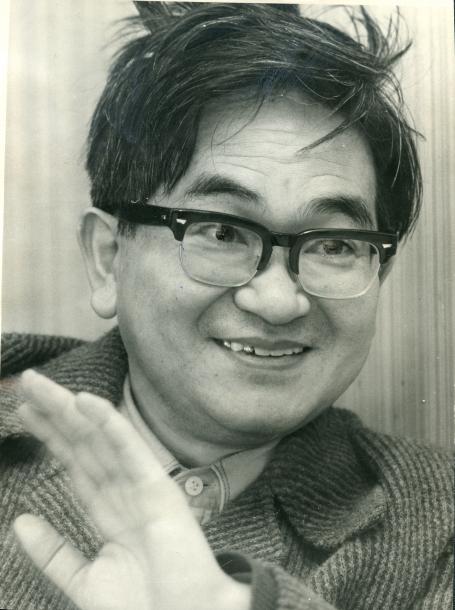
●
ものを書きそれをカネに替えるという営みに手を染め始めた頃のことだ。今すぐにとは言わないしその準備もない、だが、いつかきっと鶴見俊輔の仕事についてその功罪を含めて正面から論じてみたい、と言ったら、ある年上の編集者から「悪いこと言わないからやめなさい」と真剣にたしなめられたことがある。
彼がそう言った理由というのはおおむねこうだ。
出版業界大衆というものがある。編集者大衆と言ってもいい。それは七〇年代半ばあたりこのかた相当に増えた。君がこの先売文を稼業にしてゆく以上、好むと好まざるとに関わらずそんな彼らと顔突き合わせ、原稿の受け渡しをし、時には君が書こうとする内容について具体的な駆け引きをしてゆかねばならないだろう。何より、そのような彼らの棲息する場所以外のところから売文稼業の経験を積むことは現実問題としてほとんど難しい。その彼らの、全部とはもちろん言わないけれども、そして全部だったりした日にはたまったものではないけれども、それでもある部分を典型として濃厚に保有されている何らかの“気分”というやつがある。その“気分”を規定している最も要のところに、神話としての鶴見俊輔がいる。それは神話に過ぎないのだけれども、しかし神話だからこそ、彼の仕事の個別具体的な内容とはひとまず別に、そんな茫洋とした“気分”の中核になっているところはあるのだ。
当時まだそういうずさんな語彙を平然と持っていた、その程度にはクソ若かった僕は、うかつにも「それって、天皇制じゃないですか」と言ってしまった。そうだ、と躊躇なくその人は答えた。
「ある現実として確かにそうなのだ。だから……」
黄色いやにに灼けた右手の指につまむように持ったハイライトが、ぎゅっと灰皿の縁に押しつけられた。
「覚えといた方がいい。鶴見の仕事を批判するようなことを言ったり書いたりするってのは、どれだけ君が誠実にやったとしても、損することはあれ絶対にトクにならないよ」
●●
六〇年代にその社会的経歴の出発点を持つ思想家たちは、テレビが本格的に普及する以前ということでかなり下駄を履かせてもらってきた面があるな、と僕はずっと思っている。
三池の谷川雁が『ニュースステーション』で全国にその姿をさらされ、『朝まで生テレビ』に『試行』同人時代の吉本や鶴見や藤田が並んでいたとしたら、その後の彼らの思想そのものも大きく変わっていたに違いないと思う。たとえば、なんだただのクラいオヤジじゃんかよ、という水準での「理解」が公然と、それこそテレビの規模と普遍性とでたちどころに発動されることがなかったことでいくらかでも保証されていた神話性というのも、彼らにはあったはずだ。とりわけ、直接的な実践の場を離れたその後の過程で活字を介して良くも悪くもそれまで以上に広汎な影響力を持つようになった鶴見と吉本について、その傾向は強いように思う。
今、鶴見俊輔の書いたものを年代を追って読み返してみると、そんな神話的存在としての鶴見をめぐる“気分”の共同性があるはっきりしたかたちをとるようになってきたらしい七〇年代半ばから後半、たとえばあの『がきデカ』をダシにものを言おうとし始めたあたりから、あれま、このオヤジ本当に「現在」から置いきぼりを食い始めてんだな、という印象もはっきりしてくる。あの時、彼がひねり出した「がきデカ民主主義」というスローガンは、少なくともその『がきデカ』を生のまま呼吸していた僕の世代からは「ただのサブカルチュア贔屓のオヤジのたわごと」以上には受け取りようのない水準の代物だった。
もちろん、同時代の空気を同時代として呼吸しているということを根拠にしてそこに抱かれる感覚こそが常に最も正当なものだ、などとは全く思わない。そんな薄っペらな感覚など超えたところの真実を発見してゆくからこそ「思想」なのであり「学問」なのだ。だが、そのような留保を越えてなお、そのような「オヤジのたわごと」感覚がこちら側に確かに立ち上がったことというのは、サブカルチュアをダシにして何か思想を語る、という、それまでは充分あり得てきたある種の市民臭い“誠実さ”なり、あるいはそのようなカルチュアとサブカルチュアとの間の落差を当て込んだ発言の政治なりを留保するやり口が、「現在」の速度から決定的に落伍し始めていたということでもあったのだと思う。
もちろん、それは鶴見ひとりに還元されるべき問題ではないし、さらに誤解のないよう捕捉しておくと、ひとまず悪いことでもない。「現在」の速度に同調することだけで思想が自動的に構築できるという妄想にとらわれた八〇年代の方こそ妙なのであって、その妄想は、サブカルチュアの表層を表層としてのみ知っているということだけで思想の水準での批判を蒙らないですむ、という頽廃の方にいとも簡単に横転していった。だから、そういう「現在」の速度からの落伍を鶴見が体現し始めたからといって、それをそのものとして非難することはまず意味がない。
だが、その落伍についての自覚を他でもない当人が自身の思索の場に繰り込めなくなったまま、その落伍の現実からなおそれまでと変わらぬモードでものを言い、ことばをつづり続けるということの頽廃については、方法意識という角度から正しく批判の対象にせねばならない。眼の前の現実に対してどうしてそのような読みしか発動できなくなり、そしてその発動できなくなったことをどうして自分自身でほどけなくなっていったのか、という問い。少なくともそれまではそんな無惨はあまり曝さないですんできたはずのあの鶴見俊輔さえも、という芝居がかったため息のひとつも奮発してやってもいい。その問いは“いま・ここ”にたたずむ僕たちの「現在」にまでまっすぐ貫かれるべきものだ。
今にして思えば、大塚英志などは絶好のリトマス試験紙だった。彼をある典型として現われたことばの水準に対して批判力を発動できず、それ自体として文脈も背景も抜きに「評価」しようとした知識人たちは、その後軒並み足もとをすくわれた。彼らは大塚のことばと身ぶりに自分たちが自前ですでに捕捉できなくなった「現在」をもっともらしく教えてくれるかのような幻想を勝手につむぎ、およそ手もなく飛びついた。鶴見を筆頭に、宇波彰、小倉利丸、芹沢俊介など、それまでサブカルチュアとメディアまわりの現象について積極的に発言してきた、まずは“リベラル”で“誠実”ではあるはずの人々がそのように軒並み醜態をさらしていったことは、個々の思惑や関心を越えたところで八〇年代の「思想」の場そのものが当時すでにどのようなところに持っていかれていたのかについて考える上で象徴的なできごとである。顔ぶれを眺めてゆく限り、どうも吉本隆明に発するいわゆる自立派系の言説に対する違和感の多寡が、大塚に象徴されることばの水準に対する抗体形成に密接に関わっているようにも思えるのだが、そのことについてはここでは深入りしない。ただ、いずれにせよそれは、鶴見が「現在」の速度から決定的に落伍してなおそのような“気分”の共同性の中に宙吊りにされ続けており、なおかつ、鶴見自身その場所に安住しているとしか思えない状況の背後にあるものと確実に連動していること、最低限そのことは指摘しておいていい。
●●●
「萎えた人が、萎えたまま椅子からずりおちるように、わたしは、男らしさからずりおち、こどもらしさからはなれた。こどものころ、眼を自由にして、ただあけはなしておくと、それぞれの眼がおちつくところにおちつき、ゆったりした景色がひらける。写真にもない、教科書にもない世界。それは、世界から一皮それた所にあった。そこにながくいることは、許されなかったが、そこにいることは、何とやすらかだったか。そこからは、およそ何ものも生まれないという安定感があった。」
一九六八年、「退行計画」と名づけられた鶴見の文章の一節である。
彼にとっての切実な「私」とはそのような社会的な制約、この場合は鶴見の幼少時の世間があたりまえに共有し要求していた「男らしさ」であり「こどもらしさ」なのだが、何にせよそれらを超えた「世界から一皮それた」場所に存在するものだったらしい。
眼の前の現実からのこのような深刻な疎外感を、たとえばサブカルチュアの揺籃で補填してゆこうとする主体回復のやり口は、確かにひとつあり得る。しかしそれは、その疎外感を抱えるに至った源である「現在」の速度から、意識はともかく方法としては未だ落伍していないという保証の下に初めて本来の実効性を持つはずのものである。ひらたく言えば、こりゃもう俺にはついてゆけねェ、という感覚を眼の前の現実に対して抱いていたとしても、その現実に向かい合い何らかのことばをつむぎ出してゆくための方法は冷静に確保しておけるだけの自覚があれば、ということだ。その現実が好きでなくてもいい、なじめなくてもいい、どのような水準であれそこに正面から対峙してゆく方法意識さえ平衡を失っていなければまずは大丈夫なのだ。
しかし、戦後、サブカルチュアに対する発言は「好き」という感情を神聖不可侵の大前提としたところから行なわれるのがあたりまえになってきた。感情を持つことは正当である、というテーゼはそのようなサブカルチュアをめぐるもの言いの変遷を規定している。そして、そのこと自体に異議はない。だが、その「好き」が所与のものであり、方法意識以前のものであり、だからこそその後も圧倒的に自明のままにされ続けていた分、ひとたびその前提が崩れたとしても自分以外の誰か他人の「好き」に依拠してさえ発言の場は延命できるという倒錯までがたやすく繰り広げられることになる。サブカルチュアを語り、論じるもの言いにまつわって常に発動されがちな奇妙な根拠なしの普遍性、なんとも言えない薄ぼけた民主主義“気分”というのは、このような漠然とした感情の癒着状態を前提にしたところからしかことばを組み立てられなくしてしまったサブカルチュアを語ることばそのものについての歴史に深く根ざしている。
で、そのような無惨と頽廃へと転落してゆく萌芽というのは、何も八〇年代まで引っ張らなくても、それ以前、すでにあの「がきデカ民主主義」と言い放った段階の鶴見に象徴的に現われていたと僕は思う。あの時点で、鶴見のことばはひとつそれまでと違ったシフトに確実に巻き込まれ、ある臨終を経験していたはずなのだ。しかし、じゃあそのシフトとはどのようなものか、という次なる重要な問いは、その鶴見のことばの無謬の連続性を信じ、“気分”の共同性の内側にいぎたなくたむろする限り、誰にとってであれ絶対に切実なものとして立ち上がってはこない。
かくて、鶴見俊輔の仕事はその未発の可能性――それはまだ確かにある――も含めて、およそ前向きならざる“気分”に今や生きながら葬られつつある。そのような終焉を鶴見自身密かに望んでいるのなら、それもまたひとつの選択だ。外野がとやかく言うことでもない。
だが、もし本当にそうだとしたら、今はまだひとつの仮説にしか過ぎないそのことがあからさまにわかったら、どこかで僕は必ずこうスゴんでやる。
「おうオッサン、あんたそんなにエラいエラいと祭り上げられたまんま、あの世に行きたいんかい?」