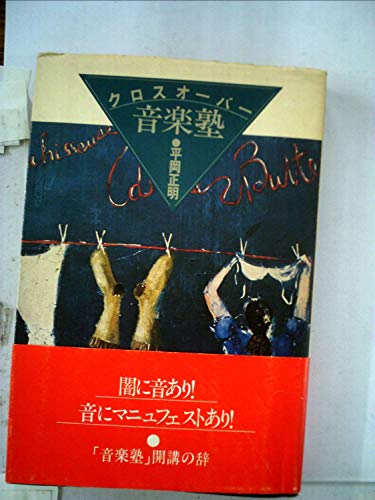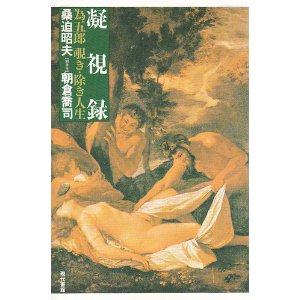●
手もとに一枚のLPレコードがある。
タイトルは『東京殴り込みライヴ/河内音頭三音会オールスターズ』。まるで屋台のエスニック料理のような河村要介の“濃い”イラストの描かれたジャケットの表に、マジックで走り書きされたサインに曰く――「ドツボ家家元 朝倉喬司」。
錦糸町の河内音頭、まだ駐車場がコンクリートで覆われてしまわない頃、砂ぼこりと共にザッ、ザッ、ザッ、という踊り手たちの足もとの響きが確かにあった八六年の遅い夏、生身の朝倉喬司と初めて言葉を交わした日のささやかな記念だ。ああ、ミーハーだったのね、オレ。●●
さらりと「ルポライター」である。この、さらり、の感じが実はかなり貴重だ。
「ノンフィクション作家」のどっちつかずの卑しさもなければ、といって、ひとりよがりな「正義」を背負って思い込む「ルポルタージュ」の呪縛が背後霊のようにとりついたいわゆる「ルポライター」にありがちなダサい暗さもない。まして、「ジャーナリズム」などという他人ごとの能書きとは縁がない。そんな希有な自然体を身につけた書き手、それが朝倉喬司という人だ。
思えば、「ルポライター」という肩書きがこのように自然体で似合う人も、いつの間にか本当に少なくなってしまった。仕事についての一般名詞をまるで自分のために仕立てた固有名詞にしてしまえるだけの器量がある、そんな生身。独断と偏見で言わせてもらえば、かつての竹中労とかにはそれがあった。
そんな「ルポライター」としての朝倉喬司のキャリアは、七〇年代前半の『週刊現代』から始まっている。彼以外にも、もの書きとしての原体験をこの時期の出版社系週刊誌に持つ人はこの世代には多い。最近大暴れしている『突破者』の宮崎学しかり、橋本克彦しかり、佐野真一しかり、猪瀬直樹しかり、吉岡忍しかり、全盛時の『別冊宝島』の仕掛け人だった石井慎二しかり……おおざっぱに言って、いわゆる全共闘世代の食い詰め者たちがそのままのノリでなだれ込み、ヤケクソの心意気で「社会」という化物にかぶりつき、「世間」の事情の間で七転八倒しながら食いつないでいった、そんなアホな渡世が幸せにも可能だった時期、朝倉喬司もその最も急進的かつ革命的なアホのひとりだったはずだ。
その頃の彼のたたずまいを、平岡正明が書きとめている。
「昔、よくサウナに誘ったんですが、あいつは熱がダイレクトに骨にくるから、砂時計一回分熱気浴ができたためしがない。腰骨と恥骨をカタカタ鳴らして出ていく。黄色いタオルを腰に巻いて熱気にたえている姿は、鮒忠のローストチキンそっくりなんだ。」
(平岡正明『クロスオーバー音楽塾』)
ローストチキンはひでえな。でも、それから二十年あまり、五十台半ばになった今も朝倉喬司は見事にやせている。やせてはいるが、しかし不思議にパワフルである。
と言って、いわゆる「力強さ」というのではない。むしろ全く逆だ。一見、ふらりふらりと風まかせ、腕力沙汰なんかわし知りまへん、といった感じの中に、すっと一本、匕首のような鋭さをはらんだ剣呑な「力」が宿っているのだ。よく知らないが、太極拳の達人なんてのはきっとこういう感じなんじゃないか、と思ったりもする。実際、彼と呑み屋になだれ込んで、「全関東河内音頭振興隊隊長」として十八番である河内音頭や江州音頭から西条八十の童謡、さらにはいきなり転調してリパブリック賛歌まで入り乱れて延々と続く名唱(?)「犬殺しの唄」というラインナップの絶倫ぶりに悩まされなかった編集者が果たしているだろうか。いや、断じているはずがない。こと“うた”や“はなし”に関して、本当にその「力」はいきなり全開になるのだ。
●●●
とは言え、世間一般の本読みの感覚としては、朝倉喬司という名前には『犯罪風土記』のシリーズ(秀英書房)のような一連の犯罪ルポの印象が強いかも知れない。とりわけ八〇年代始め、グリコ・森永事件に代表される、増殖してゆくメディアの網の目と度を超えたつけあがりを見せ始めた消費社会を背景にした「劇場型犯罪」の輪郭を描き出す手腕は、今読み返してみても確かに舌を巻くものがある。方法意識もないまま「事実」カルト、「ファクト」信仰にはまり込み、しかもそのままどんどん言葉をやせさせて恥じなくなっていった「ルポ」や「ノンフィクション」の惨状を尻目に、「犯罪」を糸口に同時代の想像力の地平にすっと身を寄せてゆくその作法は当時、実に際立っていた。
だが、それら世間的な看板とはいささかずれる朝倉喬司の本領というのもある。それは、“うた”や“はなし”にうっかりと同調してしまうような、そしてそのことであらぬ「力」の気配までもおのが身体と眼の前の現実との関係から引き出してしまいかねないような、そんな言わば民俗学的な身体による歴史的リアリティへの指向性の部分だ。そして、いささか先回りして言ってしまえば、むしろそちらの方が核になってこそ、先の犯罪ルポも成り立っていたのだと僕は思っている。
それらの経緯は、世間的な看板とは別に、いずれささやかな彼の著作をひとつひとつ尾根道をたどるようにして読んできた者にはよく見える。
『芸能の始源に向かって』(ミュージックマガジン 八一年)で単著デビュー。『バナちゃんの唄』(情報センター出版局 八三年)で一躍、新しい境地を開く。北九州に残るバナナの叩き売りのせり唄から発して、一見ふらふらとした千鳥足で未だ語られぬ日本の「近代」の想像力の地下水脈の方へどんどん勝手に進んでゆく、その道往きの魅力は、すでにこの頃からいわゆる「ルポ」だの「ノンフィクション」だのの貧血し硬直した方法意識や文体を、それ自体で笑い飛ばして相対化してゆくような質を持っていた。ミーハーついでに白状すれば、当時、やくたいもない三流大学院に籍だけ置いてふて腐れながら、寝藁まみれの地方競馬の厩舎でトドのように寝転がっていた僕は、その後ろ姿を遠く眺めてひ
そかにあこがれていた。
●●●●
実際、そのような“うた”や“はなし”と同調した時の朝倉喬司の凄味は、八五年に出された三波春夫、平岡正明、岡庭昇との座談をまとめた『遠くちらちら灯りがゆれる――流浪芸の彼方に転形期が見える』(らむぷ舎)などにはっきりと現われている。河内音頭に入れあげて、年に一回東京に櫓を建てるといういささか無茶な興行の勧進元の中心として東奔西走していたことによって、もともと持っていた“うた”への感覚がこの時期、みるみる開いていったのだと思う。この一冊には、僕は民俗学者として大きな影響を受けた。その後、及ばずながら浪曲のまわりをゴソゴソと手さぐりで掘ってゆくようになったのも、この時期の朝倉―平岡ラインとその周辺から発信される近代民衆文化論の見通しの良さに衝撃を受けたからだ。
この『凝視録』(現代書館 九三年)は、もう一度〈いま・ここ〉の言葉に立ち戻ろうとする、そういう新たなシフトに移行してゆこうとしていた時の朝倉喬司の、ひとつポンとはじけたような仕事だった。何も解説だから提灯をつけているのではない。これは、ルポライター朝倉喬司の代表的な仕事のひとつと言っていいと思う。
何がそんなにいいのか。当時の書評に僕はこう書いている。今の時点での解説としてもこれでいいと思うので全文引用しておく。
これから先、人間と社会について「関係」の相において考えようとする知性が必ず玩味熟読すべき書物である。その意義を述べる。
①「犯罪」とひとくくりにされる現実の向こう側にたたずむ等身大の人間の内実を、社会的な広がりを伴った歴史性の中で肉付けしてゆこうとする試みにおいて。
②「聞き書き」とひとくくりにされる手法に「場所」の具体性を介在させた解釈の過 程を導入し、眼前の不定形の意識の流れを可視化しようとする意志において。
③「映像」とひとくくりにされる現われとそのイデオロギーに個別の視線の主体の位置から遠近法を与えて相対化し、「文字であること」の足場を確保しながらなお、「映像」イデオロギー独裁下にある現在の読者を誘惑する効果において。
以上三点、素材よりもまず方法的次元から、この書物はこれまでのノンフィクションやルポルタージュや、あるいはその他何であれ、人間と社会についての真実を文字の側に抱き寄せようとする欲望から発した同時代のテキストたちから屹立している。その屹立の明快さは、たとえば、うわずった声でフェミニズムを標榜する者たちのその“イズム”の質と水準を根こそぎ問い返す鋭敏な試薬たる内実を獲得していたりもする。
語るのは桑迫昭夫。俗に「のぞきのタメさん」と呼ばれ、新宿の公園に出没する「のぞき」の頭目的存在。とは言え、これまでテレビや週刊誌などにも紹介され、著書すらある人物。そのタメさんの語る生活歴を、彼が経めぐってきた具体的な「場所」に共に身を運びながら聞き取り、折り重なった記憶に耳澄ましながら言葉を編み直して、眼前の東京の風景に重ね焼きする新たな地図に組み立ててゆくのが朝倉喬司。世界の始まりから悪意ある視線にさらされ「余計者」として自己形成してきた意識の網膜に、果たしてどんな風景が像を結ぶか。まずは純粋の“視線”となって「場所」を遍歴する二人の道行きは、しかし熱を帯びてくるにつれて散策の呂律を越え、徐々に内的な“対話”の相に移行してゆく。
「眼の欲望を放恣に発露することが、現代人の条件であるかのような、消費・情報社会の成り行き。しかし、そのような世の中に、受苦の体験にせかされて「見つづけねばならない」、視線の強迫の道筋があることに、いったいどれほどの人が気づくのだろう。この道筋にある人は、世の凡百の消費者たちのように、視線の欲望をほしいままにして、ちょっと疲れたから今度はグルメを気取って舌の欲望を、それにも飽きたからもうひと眠りなどという太平楽は、しようにもできないのである。」
タメさんにとってはもちろん、朝倉喬司にとってもこの“対話”は至福だったはずだ。茫漠とした不定形の「記憶」に同調した窃視の内実と速度とでひりつくように流れてゆく文字の表層。まさに凡百の消費する「映像」として風景は流れているのだが、その流れのこちら側で“視線”の意志はまた別の、ゆらゆらたゆとう速度を獲得している。そのズレ一点に全体重を乗せて眼前の風景をたよりなげなものにするという戦略は、ひとまず成功している。持ち前の“千鳥足”をここまで確信犯でやるようになった朝倉喬司のその方法的達成に深く敬意を表する。さて、どんな読み手がこのたくらみに感応するか、楽しみだ。
『週刊読書人』九三年三月※日号
その後、朝倉喬司はますます確信犯に磨きをかけ、天下御免、めでたく極上の千鳥足へとかろやかさを加えていった。勝手なことを言ってしまえば、一応は「ルポライター」という看板を掲げているけれども、その実体はすでにもう当代一流の“野”の知性、まごうかたない民俗学者である。現代書館という『マージナル』以来の版元との腐れ縁……もとい、同志的友情によって、『遊歌遊侠』『走れ国定忠治』と立て続けにいい本も出している。いずれも「書評にこれほど取り上げられながら、これほど売れない本も珍しい」と担当編集者自らボヤくようなものだが、なに、気にすることはない。ご本人と版元には申し訳ないが、朝倉喬司の新刊本が何万部もドカドカ売れるような世の中になったら、そっちの方がよっぽどおっかない。
そう言えば最近、彼は『SPA!』で中森明夫だの石丸元章だのという生態系の違う下等生物のバカタレ共から出会い頭にからかわれる一瞬もあった。今どきの下半身雑誌のルポ仕事でちょいと接触があったらしいのだが、彼ら三十代のサブカルチュア原理主義者特有の無礼でちょこざいなからかいに対して、馬鹿正直にも朝倉喬司は真正面から相手になってやり、なんと着流しに日本刀という素敵極まりないいでたちでグラビア撮影にまで応じて「小僧、たたっ切ってやる!」と見得を切る大盤振る舞い。なにもそこまでサービスせんでも朝倉さん、と頭抱えた心ある知り合いは少なくなかったはずだが、しかし、変に居丈高な「抗議」とか「批判」でなく、こういう“ノリ”で切り返そうとしたあたりがやはり朝倉喬司なのだと、妙に納得してしまうところも、僕には正直あった。
戸隠で彼が谷川雁にからむ場に居合わせ、あげく何のはずみでかしんしんと冷える一一月夜の戸隠から歩いて上田の町まで降りる羽目になったこと、赤松啓介宅からの帰途、これまた冬の京都駅で半ば野宿したこと………朝倉喬司がらみのアホな話は他にもいくつかあるけれども、それはまた将来、著作集でも出た時の月報にでも書かせていただくことにしよう。えっ、著作集が出るのか、って? 出るに決まってらい。いつとは言えないけど。いや、これだけの仕事をしてきている極上の千鳥足のこと、いつか必ず出さずにおくべきかっての。万一出ないその時は不肖あたくし、その他の心あるアホの末裔をかき集めてぜひともその勧進元にならせていただくことを、謹んでここに宣言しておく。