*1
*2
●
初めてご尊顔に接した時の印象は、「うわっ、な、なんなんだ、こいつ」だった。
忘れもしない、いまから十年ほど前のこと、当時十万部以上を売るベストセラーになった『知の技法』だった。名前からして堅苦しさバリバリな東京大学出版会が珍しく商売っ気を出してこさえた本。なにせ、東京大学教養学部「基礎演習」のテキスト。現役の東大のセンセイ方その他が腕まくりして、世の善男善女に「当代、ガクモンのススメ」を懇切丁寧に手ほどきしようとした、つまり90年代に入ってこのかた雪崩を打って世間の信頼を失っていったいわゆる文科系、大学で言うところの一般教養まわりのガクモンのありようをなけなしの「東大」ブランドふりかざして何とかしようと獅子奮迅、まあ、その意味では志そのものは悪くない企画だったのだけれども、そんな中、やっこさんだけはすこぶるつきに浮いていた。
書いた原稿の中味が、ではない。巻末、ずらりと並んだ著者紹介の、その顔写真が、である。
だいたい著者紹介に顔写真をくっつけて麗々しく並べる、というのも、タレント本や作家本といった書き手自体を売る了見の本ならばともかく、少なくともお行儀いいガクモン系の本としてはそんなにあることでもない。しかも、ひとりの著者によるものではなく複数の、それもいずれ肩書き的には「東大」系金看板バリバリのインテリ、ないしはインテリ幹部候補生ばかりが寄ってたかって書いた本のこと。お約束でくっついてくる詳細な経歴だけで十分おなかいっぱいのはずが、さらに加えてひとりひとりに顔写真がくっついていた、そのセンスもまた、しつこいと言えばしつこくはあったが、それは版元の売り方だろうから、まあ、それはそれ。問題はその売り方の中での、身ぶりのコントロール具合だった。
カメラに向かってしっかり目線をくれて、しかもその目線のありようが「ほら、ボクって他の連中なんかと違ってただの東大クン、そこらの勉強できるだけのありきたりな優等生じゃないんだよね、うふふふふふ」と、今にも言わんばかりのたたずまい。口もとなんかもビミョーにゆるませてあって、そのゆるみ具合から察するところ、何やら「ものわかりのいいセンセ」を漂わせたがっている始末。髪形も髪形で、その頃売り出し中だった俳優、江口洋介まがいな真ん中から分けたストレートの長髪。「ロンゲ」というもの言いはすでに流通していたけれども、そこまで流行りに媚びた感じというよりも、むしろ何というか、第一印象からうけたのは「あ、こいつ、自意識に少し前のミュージシャン入ってる」といったオルターナティヴな気取りっぷり。それも70年代フォーク王道な吉田拓郎あたりというよりは、当時からマイナーだけれども一部マニアに評価の高かった大瀧詠一から、直近は出てきた頃の山下達郎といったあたりのシュガーベイブ系ご一同を下敷きに当て込んだ雰囲気。いずれシンガーソングライター系の、自前で曲もこさえりゃ楽器もこなし、歌も歌う、といって、ストリート系やパンク界隈の髪振り乱し汗飛び散らせる心意気一発な暑苦しくもアタマの悪い感じではなく、さらりと才気でスタジオワークをこなします、的一手販売、アートでポップでカウンターカルチュアな(このへん適当)才能のありようを当て込んだ脂っこい自己演出の匂いが、まるで場違いなところでいきなり嗅がされたトンコツラーメン臭よろしくプンプンしていた。
あたりまえに背広を着てネクタイをしめた履歴書の顔写真みたいな定番ショットでなくても、ちょっとカジュアルなシャツを羽織ったくらいのものならば、他の著者にもあったはずだが、単にそういう姿かたち、見てくれの格好だけの問題ではなかった。顔つきが情報としていまどきの情報環境に流通されてゆく時の解釈のベクトルがいまや常にそうであるように、そういう格好、そういう顔つきを敢えて選んで露出させているこのボク、というその先回りした自己演出へ大きく傾いた自意識の過剰なありようそのものが、モノクロの小さな顔写真の面積いっぱいから放射能のように放射されている、その感じこそが「うわっ、な、なんなんだ、こいつ」の正体だった。
●●
やっこさんの名前は小熊英二。そう、『単一民族起源の神話』『〈日本人〉の境界』そして『〈民主〉と〈愛国〉』と、このところやたら分厚い本を繰り出して、ながらく酸欠状態が続く論壇まわり(そんなものがまだあると信じている界隈があるらしいのがすでにすごいのだが)で少しは話題になっている御仁である。最近では、おのれのゼミの女子学生を手先に使い、くの一よろしく新しい歴史教科書をつくる会に潜入させるという『噂の真相』並みな品性のレポートをご大層にも「フィールドワーク」「実証的研究」と銘打ってでっちあげた『〈癒し〉のナショナリズム』なども出している。
いや、そんなもってまわった言い方せずとも、ありがてえ、これもお天道さまのおぼしめし、今回この原稿を書いている締め切り間際に発売された週刊誌『AERA』10月20日づけの表紙にやっこさん、でかでかとフィーチュアされてござったのでそちらを見ていただければ、その「うわっ、な、なんなんだ、こいつ」感は即座に実感していただけると思う。

いちいちマメにフォローしているわけではないけれども、このテのインテリ幹部候補生クラスでめでたく『AERA』の表紙を飾った物件には、確か東浩紀がいたはず。あの時も肩書きが「哲学者」になっていたのでそのセンスに腰砕けになった覚えがあるけれども、それも「哲学者」という肩書きそのものが悪いんじゃない。いまどき「哲学者」一発の肩書きにくっついてきていたそのご本尊の顔つきや自意識のたたずまいとのマッチングが何ともいたたまれなかったということだ。十中八九、かつての久野収や鶴見俊輔あたり、いやいや、あるいはまさかとは思うが洋モノ信仰丸出しにジャック・デリダなんかを当て込んでのことだったのかも知れないが、何にせよそういう意図がありありと透けてみえる自己演出の匂いが何ともみっともなかった。それと同じくらい、今回の小熊英二の表紙もある意味、お宝モノである。

あるいはいまどきのこと、パソコン叩けてインターネットに接続できるくらいの読者諸兄姉ならば、悪いことは言わない、ご面倒でもぜひこちらを一度ご覧あれ。
http://web.sfc.keio.ac.jp/~oguma/top.html
臆面もなく「小熊英二研究室」と銘打たれたやっこさん自前のホームページであります。何も能書きはいらない、まず何より、このトップページに大きく貼られているセピア調の画像を虚心坦懐に一瞥していただきたい。

おそらくはどこぞのライブハウスか、それに準じた小さな空間。生ギター抱えて演奏中とおぼしき小熊センセが左方向、カメラに向かって軽く顔をこちらに向けている。右後ろにはどうやらドラムセットだが演者がいる気配はない。センセの弾き語りのパートということだろうか。手前はマイクのブームスタンドを前ボケにして臨場感を醸し出し、センセの後ろ上方にはバンドアつきのフラットな照明を逆光であしらって、これまたいかにもなステージライトのお約束。中望遠くらいのレンズで絞り開放近くで狙ったものと推測されるが、この写真この画像をわざわざホームページのドあたまに貼りつけてくる感覚が、いや、もうすさまじくも痛々しい。
でもって、その下にいきなりこれ。
小熊 英二(おぐま えいじ)
1962年9月6日生まれ、男、既婚
生年月日まではいい。だがその後にくっつけられた、この「男、既婚」というのはどういう意味があるのか。もちろん、わざわざくっつけてあるのだからご本人的に意味はたっぷりあるはずなのだが、それをいちいち読み解いてやるほどあたしゃ親切じゃないのでここではやらない。それより、できればこの画像をもういっちょクリックしていただきたい。またすごい画像が現われる。アメリカンショートヘアーとおぼしきお値段かなり高めな洋モノネコを抱いた小熊センセの写真。「自宅にて」とあるからご自分の部屋なのか。うしろはお約束で書架。こげ茶の、なんだろうちょっとテカった生地のタートルネックに、おそらくはコーデュロイの同系色のパンツ。先に触れたビミョーな口もとのゆるみ具合はここでも見られる。あと、髪形の異様さもこの画像がわかりやすい。ほんと、なんていうんだろ、この髪形。誰か教えてくれ。
その下に先のライブ画像がまたあってキャプションが「キキオン・ライブ」とあるから、そうかやっぱりどこぞのライブなのだな。聞けばこのキキオン、ってのはなんと、女房と仲良く組んでるバンドの名前らしい。*3 ごていねいにインディーズ市場で自主制作なCDも出している様子。そうかそうか、この東大卒にして元岩波書店編集者の慶応義塾大学総合政策学部助教授サマは、おのれのホームページのアタマに大学の講義でも研究室のゼミでもなく、まずギター抱えたおのれの道楽、夫婦善哉なシロウト楽団の学芸会での気取った画像をあとさき構わずでかでかと貼りつけてみせる、そういう「寝床」(古典落語だ)の旦那みてえな自意識の持ち主なのだな。もったいないもったいない。
本人の仕業じゃない、「このホームページは小熊英二研究会の学生によって運営されております」と明記してあるじゃないか、という言い訳は却下する。だって、実際の運営は学生でも、ご本尊がそういう画像をそういう文脈で塩梅することを容認してるってことだもん。なにせ学生である。それに対するセンセイである。画像や写真はおそらくその取り巻きの学生連中が撮ったものだろうけど、そういう撮られ方をし、そういう使われ方をしてしまうことについてご本尊が全く関知していないわけがない。逆に結構うるさくダメ出ししてわざわざこんな画像、こんな表出を選んでさらしている可能性すらあるんじゃないかとさえ、あたしゃ邪推している。
●●●
そんな顔つきや自意識の表出の仕方ばかり言ってて何になる、学者や言論人は書いた中味、発言の内容こそが勝負、見てくれや格好は二の次でそんなものは本質的な問題じゃない、と言われるかも知れない。うむ、至極まっとうなご意見だし、総論ではあたしもそう思う。思うし、未だそうあれるものならばそうありたい、とさえしみじみ思う。
しかし、である。いまの情報環境はそんな牧歌的な「言論」空間、「議論」の無菌室をたとえ虚構としてでも許容するようなものではなくなってしまっている。80年代以降、ギリギリ手前に見積もっても90年代、かのオウム真理教の事件このかたの「言論」の棚落ち、「論壇」の事実上の溶解といった現象の背後には、そのような「書いたこと、言ったことだけで勝負」がどうにも成り立たなくなっていった情報環境の変貌が横たわっている。それはある意味で「活字の没落」といったもの言いでくくってしまって間違いでもないのだが、しかし、ことはそんなに単純なものでもない。今や言説の内容ではなく、それらを表出する見てくれや格好こそが本質かも知れない。そのことについての認識がまずあるかないか、あったとしてもそれがどれだけ「言論」や「批評」にとって深刻、かつ致命的な変貌になっているのか身にしみて自覚できているかどうか、そのへんがおそらくいま、言葉で現実と関わろうと実際にしてゆく時の、看過できない試金石になっているのだ。
事実、一部で結構話題になった小熊の『〈民主〉と〈愛国〉』にまつわる書評や批評の類も、全てと言っていいほどそういう姿勢――「書いたこと、言ったことだけで勝負」というひとまずまっとうな、しかしいまどきの情報環境においてはやっこさんみたいな物件の思うツボなスタンスに立ってのものだった。朝日系を筆頭にこのところ旗色はなはだ順調によろしくなくなっている〈リベラル〉系メディアでおおむね好意的に受けられられたこの『〈民主〉と〈愛国〉』に対して、いまのところほぼ唯一、正面から敢然、例によって力こぶ丸出しで異を唱えようとした論文と言っていい西尾幹二の批評「〈癒し〉の戦後民主主義」(本誌9月号掲載)も基本的には同じこと。そこで言われていた「名だたる戦後進歩主義者、左翼主義者、マルクス主義経済学者ね歴史学者の屍のごとは言説を墓石の下から掘り起こして、埃りを払い、茣蓙を敷いてその上にずらっと並べて天日に干して、もう一度眺められるようにお化粧をする。若い人は名前を聞いているが、読んだことのない昔の思想家の言説を次々と眺められる便利を与えられる。その分量は膨大である。しかも注をつけて学問めかしている。著者は引例した思想につねに距離をもっていて、全部に賛成しているわけではない振りをしている。けれども、引例している大部分は戦後進歩主義者であり、さながら他の思想家は存在しないかのように振舞っているから、何も知らない若い読者はこれが戦後の思想史のトータルな姿だと思うだろう。たまに保守派の論客の名を出しても、それは脇役か刺身のつま、あるいは左翼進歩派の論を補強する引き立て役としてである」という評は、『〈民主〉と〈愛国〉』のみならず小熊の、そして小熊に象徴される偏差値世代の「若手」(と、未だにくくられてしまうあたりも大問題なのだが)インテリの自意識と手癖に対する違和感を表したものとしてひとまず的確、かつ端的なものと思うが、しかし、この正当な違和感は残念ながら、おそらく本人には届かないし響かない。アブラギッシュな論壇熱血オヤジが何力んでんの、てなもんで、ひたすらカジュアル、いつまでもスナフキンでピーターパン、かろやかにしなやかに知的世界を浮遊してみせるボク(ここ、笑うところ)の方が絶対にアタマいいし、何よりイケてるんだもん、といった根拠なき優越感はこれっぽっちも揺らぎようがない。
なぜか。そこで縷々述べられている言説そのものは、生身のやっこさん自身と乖離したところでお手玉よろしく弄ばれている寄せ木細工に過ぎないからだ。「表象」と、ここは彼ら好みのもったいつけてやってもいい。手続きとしては精緻に誠実に資料にあたり、学校的世間でボロを出さない程度に抜け目なく目配りをしてみせていても、そのような作業とやっこさん自身の実存との間には必ず一枚、何か緩衝地帯がかませてある。決しておのれは傷ついたり、挫折したりしないための姑息なアリバイ、と言ってもいい。「全てわかってやっている」「しょせんプロレスですから」といった彼ら定番のけったくそ悪い言い訳はその典型だ。
だから、やっこさんらの「書いたこと、言ったこと」だけを青筋立てて相手どってみても、彼らの主体の側には絶対に響かない。痛くない、のだ。小熊が主要な素材として依拠した大塚久雄、丸山真男の虚妄性を同時代を生きた感覚をテコに指摘しようとする西尾のその姿勢は誠実でも、そんな誠実さそのものさえも鈍重なオヤジぶりとして相対化しているつもりのご本尊はこれっぽっちも痛くも痒くもないこと、申し訳ないがあたしゃ断言できる。今や思想や言論にとっての本質的な問題とは、表出された文字ヅラの思想でも言論でもない、それらの表出を具体的に実現させている身振りやもの言い、それらも全て含めた言説生産のモードそのものが焦点になっていることであり、それこそが、言葉を介した言論と批評という営みにおいて、主体相互の深刻な違和感と断絶の根源になっているのだ。
西尾のとった、彼らの信奉する神をこそ撃て、という戦術は、それがほんとにそいつにとって神なのかどうか、という判断があって初めて有効なものになり得るわけで、無慮966ページ、束にして五センチジャスト、この出版不況になんとも無駄に分厚いこの本に含まれる注記ベタベタ、ひとまず膨大と言っていい戦後思想史上の固有名詞のそのどれに対しても、書いた本人は神などとはこれっぽっちも思っていない。右であれ左であれ、大塚久雄であれ福田恆存であれ、全く等しく平等に、信奉などしていないし、まただからこそここまで意味なく無駄に膨大なものにめでたく成り得ている、そのあたりのからくりについて、いまや言説の中味ではなくその手法、上演の仕方や表出のやり口こそがことの本質として認識されている難儀さについて、西尾に代表される「旧世代」インテリ――未だ活字がまっとうに正統であり得た世界を呼吸していた記憶に忠実な知識人たちは、ああ、未だ哀しいほど素朴で鈍感で、まさに文字通り少年のようにすっぽんぽんにナイーヴなまんま、なのだ。
●●●●
このあたりの深刻な落差について、あたしゃそれこそあのオウムの事件の頃から繰り返し語ってきた。語って、こいつら甘やかしたまんまほったらかしとくと、この先もっと難儀なことに必ずなりまっせ、と警告してきた。
あの上佑史浩を覚えているだろうか。かつてのオウム真理教広報部長にして、当時はテレビを始めあらゆるメディアで「ああ言えば上佑」と揶揄されるほど、口八丁手八丁の麻原彰晃擁護を展開していた御仁。結果、それは口先だけの空虚なもの言いであったことが後にバレるわけだが、彼が絶好調でメディアに露出していた頃、世間が察知した「うわっ、な、なんなんだ、こいつ」という感覚。「ああ言えば上佑」というのもそんな感覚に依拠して出てきたもの言いだったわけだけれども、あそこで察知された違和感というのは、ひとまず説明してしまえば、言葉と身体、もの言いと実存とが肉離れしたまんま平然と恥じないニンゲンに対する居心地悪さ、といったものだったはずだ。

学校の教室での「優等生」と呼ばれるようないわゆる勉強のできるやつ、の立ち居振る舞いの記憶がそこに重ね合わされてゆく。けれども、かつての「優等生」ならばそれに見合った責任、教室の自治に関するとりまとめも同時に、たとえタテマエとしてでも背負わされるものだった。「級長」というもの言いが輝かしかった頃。しかしその後、クラス委員や生徒会役員は単なる雑役、いやいや押しつけられる損な役回りでしかなくなっていった。学校空間ですらそんな〈公〉が保証されなくなっていった中、「優等生」とは単なる勉強の領域で抜きん出ているだけで、その群を抜く力を媒介にクラスの共同性の中で何らかの役回りが保証されるような存在ではなくなっていった。それは「優等生」に対するカウンターとしての「ガキ大将」なり「スポーツ馬鹿」なり「不良」なり「ナンパ野郎」なりといった多様な〈それ以外〉が、教室の中で居場所を失っていったことと、おそらく対応している。かくて、〈公〉なき「優等生」はその能力を社会的に認知され保証される機会を教室の中でさえも見失ったまま、ただいたずらに〈私〉の領域に自閉してゆく。
オウムの一件よりさらに少し前、89年の幼女連続殺人事件をきっかけに世間に取り沙汰されるようになったあの「おたく」というもの言いにしても、その内実をつぶさにほどいてみれば、多様性を具体的にはらんだ〈公〉を喪失して〈私〉の領域に自閉してゆくしかなくなっていった偏差値世代の、そんな新たな情報環境における「優等生」のありようとオーバーラップしていた。あらゆるアイテムを単なる素材として等価に、そして文脈を考慮せずに効率的にのみ処理してゆける情報処理能力の異様な、かつ均衡を失した突出ぶりをその特徴とする彼らの「優秀さ」とは、あの上佑以下のオウム幹部たちに象徴的だったように、まさに偏差値教育の中で純粋培養され、自ら制御する知恵も宿らぬままいたずらに肥大してきたものだった。歴史も経済も、いずれ蓄積した知識に立体的な社会性を与え、世間の具体性の中に役立つように放流してゆくためにあるはずのそのような文脈から引きちぎられた、あらかじめ閉じたまんまの「優秀さ」。おのれが立脚する社会という文脈さえも見失ったそのような「優秀さ」は、いとも容易にグロテスクなものへと、自ら気づかぬうちにその姿を変えてゆく。ゆえに、いまやその顔かたちや見てくれ、身振りやもの言いなどから直感的に察知される印象の集積は、「書いたこと、言ったこと」という表象の水準を解釈してゆく時に切り離せない情報となっている。
○
いま、偏差値教育、とおおざっぱに言った。ここでの文脈に即して言えばそれは、いわゆる共通一次世代――大学入試に際して共通一次試験を課せられるようになって以降の世代が施されてきた教育のありようと考えてもらえば、事態はよりわかりやすくなる。
共通一次試験が大学入試に具体的に導入されたのは昭和54年度入試からだから、生年としては昭和35年度生まれ以降、1960年代生まれということになる。平成2年度以降はセンター試験に移行しているから、その間10年ちょっと。今、浪人や留年コミで概算した実年齢でいうと、およそ30代始めから40代始めまでがまさにこの共通一次世代、ということになる。
高度経済成長の「豊かさ」を自明のものとして生まれ育ってきた第一世代――「豊かさ」のもたらした現実が育んだ、それまでとは確かに異なる輪郭の自意識をはらんだニッポン人。彼らの世代にとって、その自閉してゆく先の〈私〉とは、かつてのインテリのように抽象的な概念によって構築されてゆくものでもなく、おのが呼吸する消費社会の現実で仕掛けられたさまざまなアイテムの具体的な組み合わせとして表現されるのが最もなじむようなものになっていた。たとえばファッションであり商品音楽であり、映画でありマンガであり、いずれそのような日常に偏在する微細な文化の領域に関心の焦点が不断にあわされてゆき、それらを手もとに引き寄せて愛玩することによって〈それ以外〉は見えなくなっていった。巷間言われる「戦後民主主義の下で肥大した個人主義」の内実というのは、ほどいてみればそのような「豊かさ」の懐で育まれた〈私〉の成り立ちの変貌と密接にからんでいる。「好きなこと」の独裁、「自分の興味」の絶対的肯定、それらの必然としての「センス」の優越。それまでならば「趣味」とひとくくりにされて、まさに「余暇」の範疇に収納されてよかった領域がとりとめなくふくれあがってゆく。
そんな彼ら彼女らが成年に達し社会人となった段階では、そのような〈私〉を「仕事」の文脈に還元してゆくことの正義が無条件に肯定されてゆく。いわゆるバブル期にみるみるうちに増殖し、それを支える経済環境が崩壊した後も意識の上では未だ根強くはびこるいわゆる「ギョーカイ幻想」の核心にある「好きなこと、キモチいいことだけして暮らしたい」という欲望は、このようなポスト高度経済成長の仕掛けの中で、半ば同時代の公理となっていった。
世間一般の「仕事」ならば「プライベートの充実」として落ち着かされるべきものが、偏差値教育の熾烈なふるい分けをかいくぐり、大学や研究所などに居場所を獲得できた「優等生」たちならば「研究」の場がそのまま、その正義の実現の場になったし、メディアの生産点に身を置くことになった「優等生」たちにとっても「クリエイティブ」がその幻想を具体化する舞台になった。かつてのようにメインカルチュア/サブカルチュアの対比構造が明確な状況からすでに遠く、あらゆるものが消費文化としてサブカルチュア化してゆく中、それらを「仕事」として特権的に取り上げようとしてゆく流れが顕在化した。高度経済成長以降、現実との乖離がすでに明らかになっていったにも関わらず、いや、だからこそ、偏差値世代にとっては学校、および一部のメディアなど学校に準じる言語空間で最も効率的に流通してゆくことのできる「政治的に正しいもの言い」として延命することになった〈リベラル〉言説のモードと、「豊かさ」を現実化した日常におけるおのれの実存に関わる〈私〉の領域とが野合してゆくのは、その意味である種必然だった。「カルチュラルスタディーズ」と称する外来の意匠がその本来の文脈を無視したところで、おおむね90年代に入って以降、「役立たず」の烙印を押されつつあった人文系学問のスキームにとって、何か救世主的な勘違いと共に受け入れられるようになったのも、そのようなわが国固有の事情が介在している。
たとえば、彼ら彼女らがいわゆる保守派の歴史観に対して好んで使う「オヤジの慰撫史観」というもの言い、あれなどは実に象徴的だと思う。
巷間、社会学者の宮台真司あたりが流布させたということになっているが、もともとのオリジナルはというと文芸評論家の斉藤美奈子。それもティーンズ少女向けの雑誌『Pink』の連載で、あたらしい歴史教科書をつくる会に代表されるいまどきの草の根からのナショナリズム復権運動について例によって揶揄的に言及した、それを読んだ中森明夫がファックスで宮台にご注進、それをそのまま文脈抜きに流用したというのがことの真相らしいのだが、それはひとまずどうでもいい。問題はこの「オヤジ」という部分だ。
「オヤジ」というもの言いには、それをあげつらう自分たちはそんなものとは違う、という前提が無条件に含まれている。これが単なる生物的年齢をものさしにしているわけではなく、本質的に何らかの価値判断が介在してのことは明らかだ。この場の文脈に即して微分してみると「そのような保守的思想信条になおうっかりと影響されてしまう、未だ開かれていない遅れた意識のかわいそうな土着ニッポン人たち」といったものだろう。それに対置される自分たちは特権的な鳥瞰者、ひとり覚醒している聡明な存在、つまりは「新人類」であり「ニュータイプ」というわけで、何のことはない、これはかつての「前衛」であり「インテリ」であり「進歩主義者」であり、いずれ明治このかたわがニッポンの知的風土に連綿と宿ってきた近代主義的インテリのあの鼻持ちならない選民意識とありようとして変わるところはない。
その意味で、やっこさんたちの自意識は構造としては「オヤジ」インテリたちと実にきれいに連続している。『プロジェクトX』に感動する意識を「オヤジの慰撫史観」の延長で安易にバカにする彼らが、同じくアニメを語りマンガを論じ、広告やメディアをもってまわって取り沙汰することに血道をあげる。「オヤジの慰撫史観」に対する彼ら「飽食優等生どもの自慰史観/世界観」というのもすでにあったりするのだ。
○●
にも関わらず、彼らのその選民意識の成り立ちは、それまでの「オヤジ」インテリたちのそれとはまた違う様相も呈している。
彼らの優越感を保証してくる光源=価値の源泉が、今やかつての「西欧」や「マルクス主義」のように一点に収斂できるものではなくなっている分、「どうやら選ばれてあるらしいことに対する根源的不安」は必然としてつきまとってくる。それは曲がりなりにも80年代の価値相対主義の嵐をくぐり抜けた、その痕跡なのだが、しかしその不安を癒してゆくためにはどのような形にせよ「他とは違うボク/ワタシ」の証明を不断に、周囲に対してしてみせなければならない。それは時に実利とかけ離れたトリビアルな知識や情報の集積ぶりであったり、場違いな身振りやためにする奇矯なもの言いであったり、異様に攻撃的で独断的な「論争」の作法だったり、その現われはさまざまだが、しかしその背景にあるモティベーションは基本的に共通している。
小熊だけではない、このような「他とは違うボク/ワタシ」を表出することにあらかじめ強迫観念を持たされてしまった偏差値世代「優等生」たちの、ありていに言ってけったいな、末梢神経むき出しの過剰な自己表出は、実はもうメディアの舞台のあちこちでその実例が確認できるようになっている。
「フィールドワーク」を隠れ蓑に、おのれの性的実存の葛藤を解消するためのテレクラ三昧を「研究」と称し、著書の中表紙には茶髪に上半身裸体で乳首まで見せたカメラ目線のバストショットを臆面もなくさらし、雑誌グラビアでは女装企画まで披露したた社会学者宮台真司。ダテ眼鏡とリカちゃん人形由来のペンネームというキャラづくりのまんま、臨床で得た知見までも平然とエッセイに書き散らして恥じるところのない精神科医香山リカ。いや、表出として「左」に分類される論者だけではない。静かに眺めてみれば「保守」と認識されている者たちの中にも全く同じような自意識の身じまいの悪さはあたりまえに観察できる。さらには、世代的にはやや上に属するものの、昨今、そのメディア露出の頻繁さに応じて大きく顔写真をフィーチュアした出版物や企画がまかりとおるようになってきた姜尚中や、オウム事件における最も重要な思想的責任を負うべき立場にありながら口をぬぐって未だに空虚なコピーライティング的もの言いを垂れ流す中沢新一なども、それら偏差値世代的「優秀さ」に苛まれた自意識の七転八倒の事例に列しておいていい。


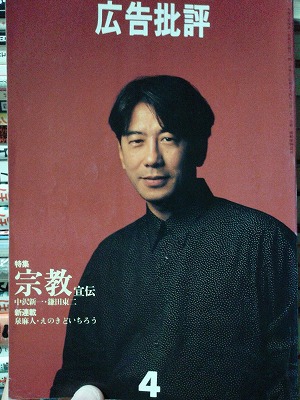
『〈民主〉と〈愛国〉』以下の小熊の著作のあのとりとめない膨大さ、あるいは、宮台真司のあのモノマニアックなまでに「自分が正しい」ことにだけ執着してゆく閉じた饒舌さなどは、彼らのそのような類の「優秀さ」の証明であり、偏差値世代「優等生」としての聖なる痕跡に他ならない。彼らは間違いなく「優秀」ではあるのだ。一元的な偏差値的世界観に律せられた学校の教室のような空間にある限り。そのことを彼ら自身、動物的な本能で察知している。だからこそ、彼らは自分たちの〈私〉をそのままに甘やかしてくれる偏差値的世界観の効かない〈それ以外〉の現実と、決して身体を張って対峙しようとしないし、そのような自分など考えたこともない。
そして、そんな彼ら彼女らのある部分は、今やすでに教育機関に教員として居場所を獲得し、あるいはまた、メディアの生産点で影響力を具体的に行使できる地位についている。いや、医者や弁護士、官僚などについても事情は基本的に同じのはずだ。「豊かさ」の中で滲み出してきた、未だその輪郭も自覚されない新しいエリートカルチュア。その主体からあらかじめ切断された言説をほんとうの意味で批判の対象にし、同時代の役に立つようにしてゆくためには、その「書いたこと、言ったこと」とご本尊たちの実存との間をもう一度、腕づくで関係づけて見せてやること、見せて、そしてその異様さみっともなさを誰にもよくわかるように示してゆくこと、そのプロセスが不可欠である。やっこさんたちの「優秀さ」がそのままで受容され、許容されるわけではない〈それ以外〉からの誇りある失地回復運動の必要。旧来のインテリ作法としてはほとんど外道、あり得べからざる反則技であることは言うまでもないが、しかし、いまやそのような反則技を平然と行えるだけの器量も持ち得ないままでは、このますます難儀さの増してゆく情報環境においていっぱしの思想も言論も批評も、再び輪郭確かなものとして立ち上がることはできないだろう、とあたしゃ確信している。
*1:『諸君!』掲載原稿。表向きも水面下でも、まあ、それなりに物議を醸したみたいだけれども、「顔や容姿のことに触れるのはルール違反だ」的嫌悪感ベースの否定や黙殺、罵倒の類は別にして、ここで俎板に乗せようとしたことの本質、同時代の日本語環境での〈知〉だの何だのに否応なくついてまわっている自意識のありようとそれがいわゆる偏差値的世界観価値観と骨がらみになっているらしいことや、それらと「おたく」的心性との関係などについて正面から言及したようなものは、見聞きする範囲ではなかったように思う、その後も含めて。
*2: 今にして改めて振り返れば、これ、昨今の「キャンセルカルチャー」の萌芽的あらわれ、だったのかもしれんな、と、ふと。いや、20年近くたって気づくあたりがわれながらのボンクラぶりに笑っちまうんだが、この原稿を書いたことで、ゲラにまでなっていた単行本を新曜社の社長じきじきの「命令」で「なかったこと」にされた、という顛末があったわけで。そのへん、同じ原稿が夏目書房の侠気で陽の目を見た『全身民俗学者』の「あとがき」でわかりやすく事情説明していたのだけれども、もちろんそれらも含めて「なかったこと」にされたのは言うまでもない。その「あとがき」のデータが例によってどこぞに埋もれとるのだが、まあ、まあそのうちひょっこり出てきたらアップさせてもらうことにしますので、ご容赦ご容赦。……221205
*3:この奥サマも確か元岩波の同僚だった才媛(だろう、普通は)だったはず。で、あたしゃこの奥サマとも編集者としてなにげにバトった経緯があったりして……240301