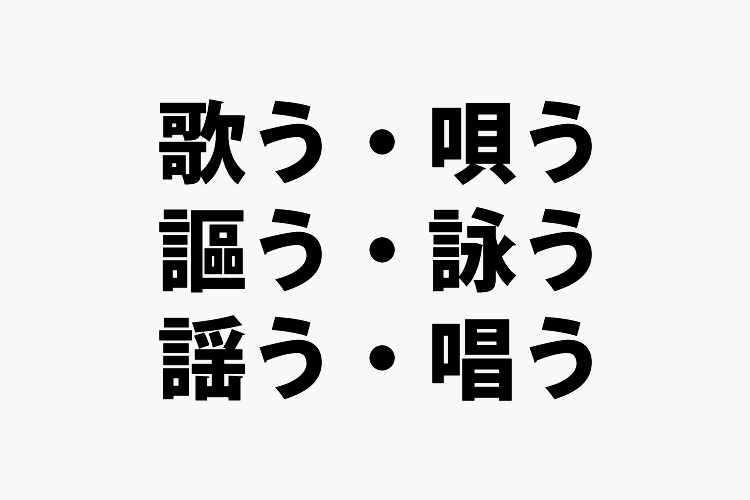
「うた」というもの言いがある。
「歌」でも「唄」でもいいし、場合によっては「詠」や「謡」、「唱」なども、表記にせよニュアンス的にせよ、そのカバーする意味あいのうちに含まれてきたりする。不思議なことにそれらの一部はまた、「よむ」の方にもひっかかっていたり。
国語辞典でも漢和辞典でも引いて見ればそれなりに定義や意味、その来歴などについて教えてくれるのだろうけれども、それら外から押しつけてみる既成の枠組みとは少し別なところで、他でもない現在、〈いま・ここ〉を日々生きている自分たちの身の裡の感覚として、この「うた」というもの言いがどういう位置づけになっているのか、そのあたりがとりとめないことながら、ずっと気になっている。
「うたわせたろかい」というタンカがあった。
これはもう相当にガラのよろしくない、大阪やその界隈に棲息するある種の人がたがある究極の局面においてうっかり繰り出すような常套句。最近もまだ活きて使われているのかどうか、少なくとも自分自身、ナマで耳にしたことは現実にほとんどないようにも思うのだけれども、それでも確かにある感覚と共に、こういうタンカがうっかりほとばしり出てしまうような局面が日々の暮らしの裡にあり得ること、そしてそれによって喚起される「あ、これはヤバい」という総毛立つような感覚もまた、なぜかこの身の裡に抜き難く〈リアル〉なものとして刷り込まれている。
「うたわせの三兄弟」というのもいた。
あれは70年代は『週刊漫画アクション』連載、どおくまんの出世作『嗚呼、花の応援団』、例によっての大阪はミナミを根城にブイブイ言わせていた名物三人組というキャラクター。もめごとから喧嘩になってゆく過程で、ある決定的な局面で「うたわせたろかい~」と3人揃ってタンカを切る。もちろんタンカだけでなく、三人三様それぞれの流儀で暴力的に「うたわせる」ための手練手管を存分に持ち合わせているわけで、だからこその通り名であり、対峙することになった相手の意志や意向など一切お構いなく、暴力的に強制的にこちら側の都合と意図でとにかく「うたわせるぞ」、「音を上げさせるぞ」という意味のこのタンカの凄みも増すというもの。
そうだ、「音を上げさせる」と言えば、「キャン言わせたれ」という同工異曲なもの言いもあった。
これは中場利一の『岸和田少年愚連隊』、井筒和幸がまだ正気だった頃に映画化された往き脚満点な作品のワンシーン、喧嘩に負けて帰ってきた主人公チュンバがリベンジへ出向こうと何か「道具」を家の中で物色、当時流行っていたペラペラにのした学生カバンに鉄板焼きの焼き板らしきブツを潜ませて再度出撃しようとしてゆく際、「それ、あとで返してや、イカ焼いたりするんやさかい」と故笑福亭松之助師演じる半ばボケたようなジイちゃんがいい味のからみ方をした後に、同じく茶の間で漠然とテレビを見ていたかに見えた石倉三郎のオヤジが、出てゆく息子チュンバのその背中に一転、表情をキメて声かける、あの場の声色でいつも再生される。
それが犬の鳴き声としての「キャン」であることは言うまでもないのだが、しかしそのようなもっともらしい理にかなった説明以前に、野良犬同士の組んずほぐれつな喧嘩が路上にあたりまえにあり得た時代、先に声をあげて鳴いた方が負け、という彼ら生きもの同士の日々の掟もまた、われら人間世間の側にも同じ生きものとしてまっとうに認知され共有されていた状況だからこそ、のっぴきならない皮膚感覚と共にしみじみと〈リアル〉に響くもの言いだったはずなのだ。声をあげる、たとえキャンという畜生の肉声であっても、生身の発声をすることの意味が、生きもの同士ののっぴきならない関係における感覚と結びついてあること。それらを媒介するもの言いとしての「うた」であり「うたう」であるらしいこと。
あるいは、ああ、これもまた漫画表現の記憶を介してのことになってしまうのだけれどもお許しあれ、青木雄二の傑作『ナニワ金融道』の桑田あたりの、いずれゼニカネ絡みの抜き差しならぬ路上稼業の手練れが、不動産の登記書や戸籍謄本、裁判所の命令書などのいずれ「公」の「文書」を手にしながら、その一部をはっきり指し示しつつ、「ここにはっきりと、うとうてあるんや」と宣言してみせる時の、あの「うたう」に込められた気分なども、また。
紙の上のしるし、単なる記号に過ぎない文字の連なりによって構成されているそれ自体なんでもないどこにでもある文章の、そのある一部分だけが突如「うたい始める」。文字の、それも公的な文書が主体となって「うたう」という事態のこのただならなさは、まさにこの「うたう」というもの言いを介しているがゆえに、ねっとりとからみつくような感覚を伴ってこちら側に否応なく思い知らされることになってくる。その間の機微にもまた、この「うたう」というどこかなまなましくもあやしい、手もとで制御不能な事態をうっかりその場に引きずり出してしまうかに思えるもの言いが、間違いなく作用しているのだと感じる。
しかも、ここはしつこくこだわってみるのだが、この場合のブツは文書である。しかも公的な文書である。それが「うたう」ことを始めるとなると、「公」の強制力が必然的に併せ技で立ち上がる。もうそうなったらどうしようもない、それまでは眼前の生身同士の関係、日々の暮らしの中にいくらでもあり得る交渉ごとやもめごとでしかなかった現実に、突如それらと異なる水準、予期せぬ位相からのただならぬ事態がみるみるうちに出来してしまう。いや、実際にそうなるかどうかはまだその時点ではわからないにせよ、少なくともそうなることについての予感だけは間違いなく、そのうたい始めた文書の一行なり一文の界隈から濃厚にたちのぼり始める。いわば呪いの言葉、魔界召喚の呪文みたいなもので、そこから先の事態はどのような方向にせよ決定的なものになってゆかざるを得ないだろう。少なくともその場に関わる当事者たちの間にはそうなる必然が半ば諦めと共に、その場に居合わせてしまった者たちである以上等しく受け入れなければならない宿命のように共有され、浸透してゆく。「縁」というもの言いもまた、こういう局面により深く響いてゆくようなものなのだろう。
「ここにはっきりと、うとうてあるんや」という宣告は、それがこの場の状況をある方向に一気に確定するための決定的な切り札であることを思い知らせるだけの内実を伴っているし、ただの記号に過ぎない文字の群れが「うたう」ようになる事態をある種の比喩として使うことで、その内実を相手の身の裡により直接的に、肉感的にめりこまれてゆくような効果を持たせることになる。ことほどさように、「うたう」というのは剣呑でもある。
敢えて表明する、力を込めて負荷をかけ、こちら側から向こう側へ、此岸から彼岸へ、ある意図と意志とを確実に込めながら、ぎゅっと押しつけるように何かを伝える、そういう意味あいを確かに込めなければならない時に使われる「うたう」。これもまた「うた」の動詞化、生身に「うた」が宿ろうとする時の気分をことばに乗せてみた表現のひとつではあるらしい。いずれそういう現実をうっかりと引っ張り出してしまい、日々の日常の流れの中に「公」のような全く異なる水準のからくりを介在させ、起動させてゆくためにも、この「うたう」は日常のなにげない連続の中にふいにさしはさまれてくる。また、だからこそ畏れも伴うし、それだけのリスクや危険性を引き受ける覚悟のある立場にある者でない限り、おいそれと使い回していいものでもなかったのだろう。
改めて思う。この「うた」というのは、いや、単に名詞としてのそれだけでなく動詞となって生身と紐付けられる「うたう」も含めて、果たしてどういう歴史なり民俗なり記憶なりを介して、いずれ生きものとしてこの世を何とかやりすごしてゆくしかないわれわれの身の裡にわだかまる何ものかと紐付けられているのだろう。おそらくそれは、単にひとつの楽曲や唱歌、楽譜なり記録媒体なりにかたちあるものとして定められる対象物としてなどでは到底なく、もっと広大な、とりとめない人間世間の広がりの中で確実に今もなお、〈いま・ここ〉に現実に作用するだけの力を宿した領分でもあるらしい。でなければ、「うた」が、生身と紐付けられた「うたう」を介してこうまで何か決定的な局面で、定型的なタンカや決め台詞のような形でひそんでいるはずがない。
日々の暮らし、日常の流れの中でかわされることばやもの言い、普段の肉声とは違う音声を介して立ち現れる「うた」の〈リアル〉。それは通常のことばやもの言いによって媒介され流通する意味とは別の、音そのものの響きや調子自体が異なる水準の意味をはらんで「場」に浸透してゆき、ただごとならぬできごととしてその場にある人々の生身を共振、共鳴させてゆくような効果を生んでゆく。われわれ人間世間の側にある者だけでもない、畜生たちも「うたう」し、山川草木もまた同じ。いや、何も生きものだけでなく、時至れば万物全て「うた」をはらみ得るし「うたう」こともある。紙に書かれた文字ですら「うたう」「うたわせる」、そういう容易ならざる事態をあたかも現実にあり得るかのように思わせる、聴かせる、そんな生身の技術や技芸、おそらくは芸能と呼ばれてきたような領分とも通底してゆく何ものか。そのあたりの気配に〈いま・ここ〉を生きるわれわれの生身がすでに反応しなく、できなくなっているのだとしたら、そしてそうなってしまっている可能性は実はもう十分過ぎるほどあると思っているのだが、しかしだからこそなおのこと、未だこの世の人間世間を生きながらえているこの自分自身の身の裡に、そのような「うた」と「うたう」感覚の痕跡みたいなものを、まだあるものならば少しゆっくり探してみるようなことを始めてみたい。


