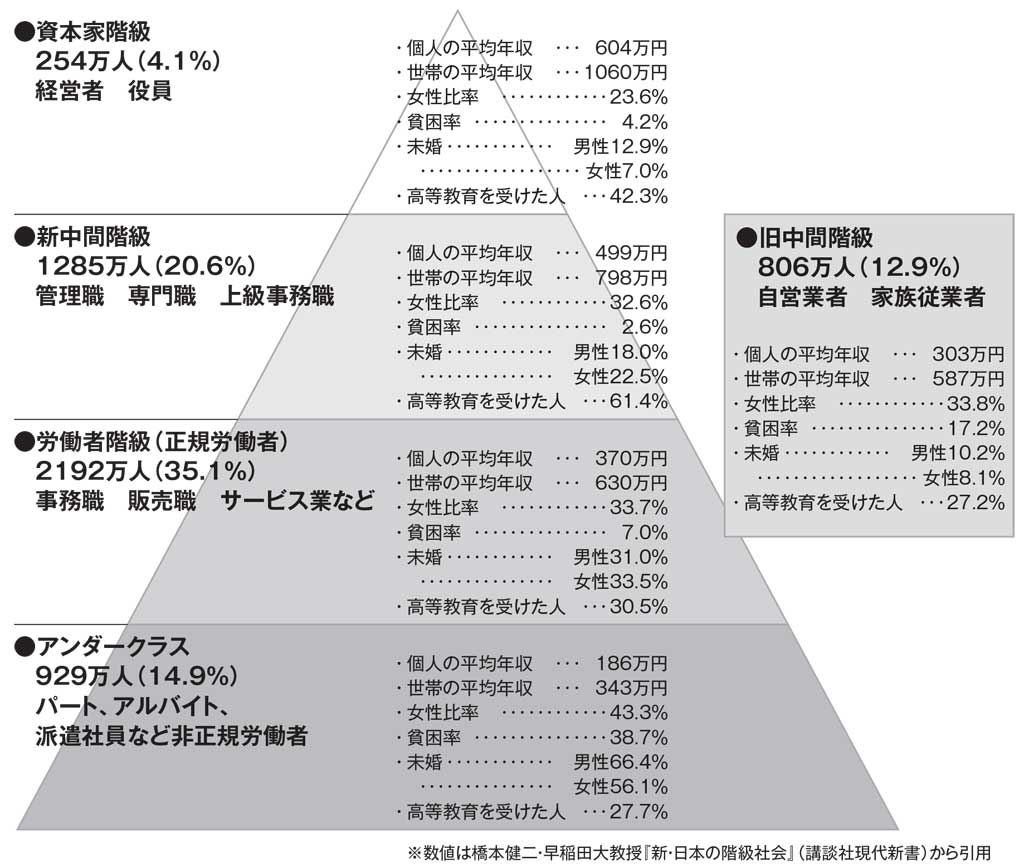
●
「格差」ということが、あたりまえのように言われるようになった。
言葉自体は、岩波新書から出た『格差社会』あたりが一応、火付け役ということになるのかも知れない。もともと経済学者の橘木俊詔が書いたものだったから、経済学のバックボーンを持つ術語。ただ、民俗学者として焦点を合わせてしまうのは、その「格差」というもの言いを喜んで持ち回っている手合いやメディアの現場の立ち居振る舞いのうさんくささの方だ。
そのうさんくささの拠って来たる所以というのは、思い切り刈り込んで言ってしまえば、その「格差」なり「格差社会」を持ち回って騒ぎ立てようとする動き方が、いわゆる「新自由主義」的な政策、もっとはっきり言ってしまえば小泉内閣時代にとられていたさまざまな政治的経済的方向づけについて文句をつけるためのダシにしているに過ぎない、というのがわかりやすく見えてしまう、その点にまつわっている。要するに、あらかじめ結論ありきで、その結論に都合のいいコピーライティングとして「だけ」持ち回るようになっているんじゃないの、ということだ。
あるいは、今年の春先から、『蟹工船』が「若者」(このもの言い自体、すでに「戦後」の文脈で精神史的に反省されるべき頃だと思うのだが)に静かに読まれて時ならぬベストセラーになっている、といった「報道」もされるようになっている。なるほど事実として、半ば忘れられていた数ある古典のひとつに過ぎない『蟹工船』の売れ行きが最近、少し目につくくらいは増えていて、文庫の版元である新潮社の編集部が宣伝になれば、と仕掛けたのが始まりだったようなのだが、その理由づけに「格差」を短絡させてしまったのは最初の段階では想定外だったらしい。ましてや、それに『赤旗』がまっさきに飛びついて、だから共産党に「若者」が関心を持つようになっている、といった「誘導」までついていたりするようになると、すでにシッポ丸出し、お里が知れるというものだが、総選挙をにらんだプロパガンダの一環だとしても、そのような〈おはなし〉をこさえてしまう雰囲気自体がすでにある種の情報環境に共有されているということでもあるわけで、それらの雰囲気の由来にはやはりこの「格差」というもの言いが根深くからんでいる。
●●
「格差」「格差社会」自体は、新書のタイトルに使われたことで注目されたものの、それでも、本自体を注意深く読んでみても、筆者の橘木自身が使っている文脈に即して言えば、そんなある一定の方向へのフレームアップを意図したところはあまり感じられない。まあ、当然だろう。著者の橘木は六十代。日本経済学会の会長まで務めたこともあるというから、経歴的にも世代的にも「学問」がまだきちんと「活字」との関係で質量が保証されていた時期に知的形成を行ってきた御仁ということになる。
けれども、その後ある種の流行語として、同時代のある気分と関連づけるような方向に流されてゆく過程で、この「格差」はどんどんそういう本来の輪郭をくずしてゆき、「とにかくこう言っておけば何かもっともらしいことを言ったようなことになる」もの言いの方へと姿を変えられてゆくことになる。
言葉自身の出自というか素性からすると、おそらく「下流社会」あたりがそういううさんくささの露払いというか、下地作りをした形になっていて、「格差」「格差社会」の方はむしろそこに巻き込まれたというか、とばっちりを受けたような印象もある。
この「下流社会」もまた、新書のベストセラーが発火点と言われている。著者の三浦展は1958年生まれ。もともと『アクロス』の編集部から三菱総研を渡り歩いた御仁で、一橋大学在学中には当時の学生雑誌『一橋マーキュリー』の編集に携わっていたというから、申し訳ないがもうこれだけでおおむねどういう手癖、どういうフィルターで目の前の現実を都合よく変形させてゆく類の手合いか、ピンとくる。実際、『格差社会』と比べても『下流社会』の方には、当時ざっと一読しただけで、ああ、言葉と現実に対する関わりをこういう具合にしかとらえられないまま生きてきちまったやつの書いたもんだな、という「いやな感じ」が漂っていたのを覚えている。
ことばと現実とののっぴきならないつながり方が、そしてそれと同じ位相でことばとおのれ自身の身体や実存という領域との関わり方が、共にかつて80年代前後の情報環境で刷り込まれた初期設定のまんま、その後あたりまえに年を食い、情報環境の激変もくぐり抜けて生きてきたはずの現在においてなお、どういう理由でかわからないが、まだそのまま世渡りできると思い込んだままでいる鈍感具合のやりきれなさ、とでも言えば、わかる向きにはわかってもらえるだろうか。いまのこの状況でなお、このような便利にメディアの表舞台で使い回されるだけのもの言いを臆面もなく再生産して恥じない反省なき同類としては、最近のわかりやすい形としてなら、たとえば斎藤貴男や森達也などをあげてもいい。
いまだと「プロ市民」とか「サヨク」とか、まあ、ものの言い方はそれぞれでも、今のマスメディアが現実と乖離したまま再生産しているある情報の系列についての違和感というのは、以前と比べてずいぶんと理解が広まっていると言っていいが、これだけネットを中心にした新たな「世間」の側から「なんだかなあ」とあきれられているにも関わらず、当のメディアの現場に生きている者たちの側がその乖離をいまどきなお維持していることの謎のある部分には、こういう鈍感さとそこから発するうさんくささが根深くからんでいる。
思想的なもの言いとして、それこそ表象としての「プロ市民」「サヨク」「リベラル」らしき言葉の羅列がある種のメディアで今もなお再生産され続けているのが事実として、いまなおそれを肯定的に鵜呑みにしてしまう読み手の側も含めて、同時代の情報環境において情報の送り手と受け手の間に共有されている秘密の約束、プロトコルみたいなものがあって、それがおそらく、ここで言っているようなことばと現実、ことばと我が身との間とのつながり方のある不自由、ということなのだ。
●●●
それはおそらく、80年代頃にようやくはっきり形として見えてきたようなものだった。
それまでの社会にもあった不自由ではあったけれども、しかしそれはその頃以降のように全面化してゆくことはまだなかった。活字がまだそれなりに活字として情報環境の内側で安定していられた状況から、その地位を相対化してゆくような変貌が大きく始まっていった過程。あとになって、ああ、あれはそういうことだったのか、と思うような、でもその過程を生きている真っ只中ではそこにはらまれていた歴史的、文化的な不連続について気づかないような、そんなプロセス。
ネット以前にそんな大きな変化があったの? と、いまどきの若い世代ならいぶかるかも知れない。けれども、情報環境の変貌というのは案外、地味なところで、少なくとも情報の個々の消費者の側から見えにくいところから、重要な不連続が始まっていたりするものらしい。
活字から写植による版下づくりが普及してゆき、写真やイラストといった「ビジュアル」(このもの言いもその後一般化した)系の情報が活字の原稿と同等に、時にそれ以上に制作過程で重要なものになっていった。誌面づくりのプロセスが大きく変わっていった時期。字詰めいくらで「原稿」が発注されるそれまでのルーティンから、「誌面」単位での製作プロセスがあたりまえになってゆき、デザイナーにまず発注し、写真やイラストなど「ビジュアル」の手配をし、その残りの部分に「文字」を流し込んでゆくといった、ある意味それまでとは逆転した手順が一般化してゆく。少なくとも、そういうプロセスを採用してゆく雑誌に広告収入が集まるようになり、大手出版社からこぞってそういう広告の入りやすい誌面づくりをする雑誌へと転換していった。これを、「活字」の意味が変わっていった、と言うだけでは、しかしことの半分で、より本質的だったのは、そんな変貌によって「活字」とのつきあい方によって形成される知性のありようまで実は変わり始めていた、ということだった。
そういう時期に刷り込まれたことばと現実、生身の自分とことばとの関わり方の「歪み」(と敢えて言う)を、その後三十年近くたってなお、何の理由かは知らないが、未だ後生大事に保持している、そういう環境でまだ生きていられるような手合いが、メディアの生産点にまるで潮だまりに取り残されたフジツボやカメノテのようにへばりついていて、そしてそれら潮だまりの方にした現実がないと思い込めるような者たちも含めて、自ら新たな情報環境に適応しようという生きもの本来の意欲も衰え、その不自由に縛りつけられたまま、干上がるのを待っている。
だから、いま「格差」「格差社会」、あるいは「下流社会」といったもの言いを持ち回る言説の多くは、ほんとうに眼前の事実として起こっていること、〈いま・ここ〉の〈リアル〉からあらかじめ疎外されたところで自分のシッポを追いかけているようにしか見えない。