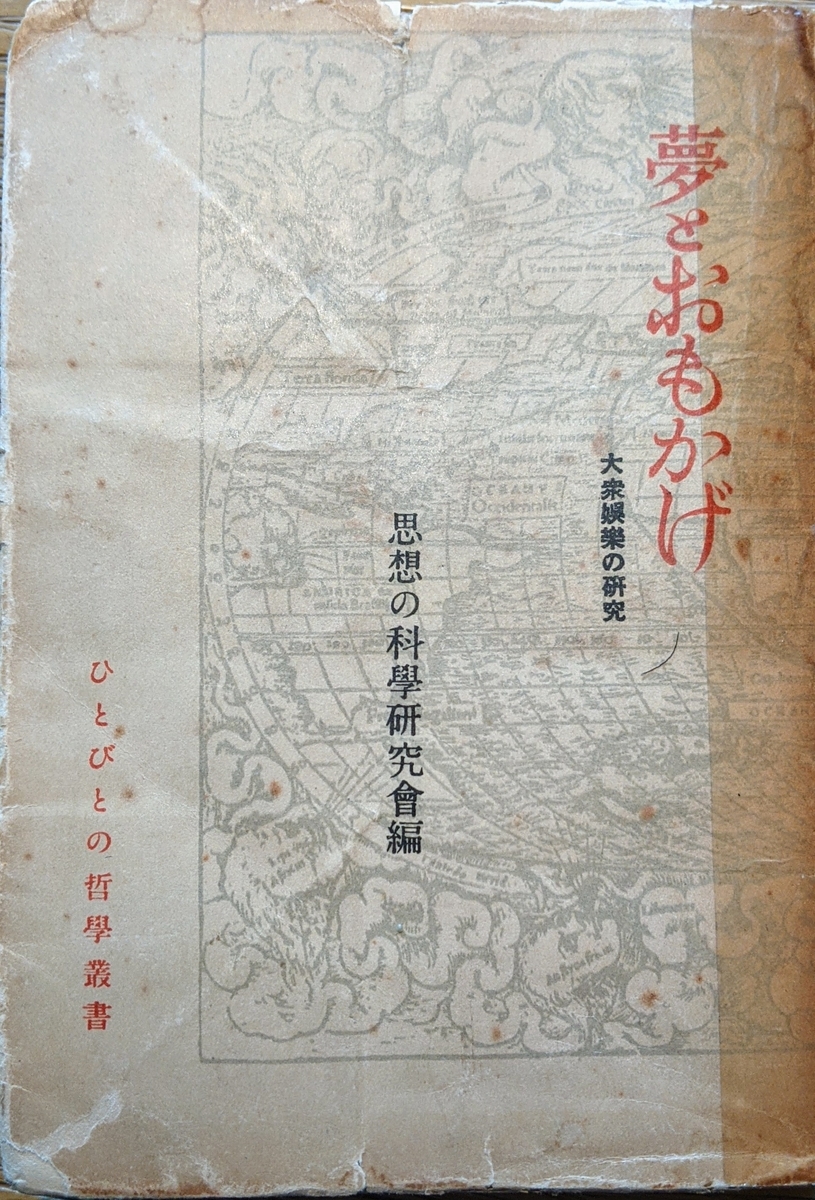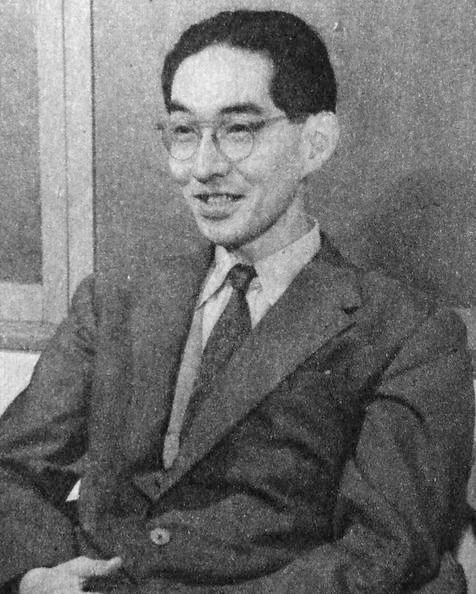*1
現代書館から『朝倉喬司芸能論集成』が刊行された。ルポライター・朝倉喬司氏(1943~2010)の芸能関係の文章を集めた968頁の大著である。刊行を機に、編集委員会のメンバーである、株式会社出版人代表の今井照容氏、民俗学者の大月隆寛氏に対談してもらった。(読書人編集部)
今井 私にとって、朝倉さんの命日というものがありません。大月さんは2010年の12月8日に、札幌国際大学主催の「こまどり姉妹とその時代」という催しで、朝倉さんとご一緒する予定だったといいます。その日が、朝倉さんの命日といっていいのかもしれません。そのあたりの経緯からお伺いできればと思います。
大月 もう10年以上前のことですね。2007年からご縁があって札幌国際大学という大学で教えるようになって、ご存知のように昨年6月に不当な懲戒解雇を喰らって裁判で係争中なんですが、ただ、当時はまだ先代の理事長が健在で、いろいろ好きなことをやらせてもらってました。「BSマンガ夜話」のメンバーを北海道に呼んでトークライブをやったりね。
当時、こまどり姉妹のドキュメンタリー映画『こまどり姉妹がやって来る ヤア!ヤア!ヤア!』(2009年)が完成したんですが、なぜか彼女らの故郷の北海道で公開されてなかったんで、制作のアルタミラピクチャーズと交渉して、こまどり姉妹の実演つきで札幌の道新ホールで上映会を開催することになったんですよ。だったらついでに、こまどりさん交えたトークショーもやろうと。それで朝倉さんと赤坂憲雄さんを呼ぶことにしたんです。

朝倉さんに電話で依頼したときは「いやぁ、こまどり姉妹! なつかしかね~ それはよかね~」と快諾してくれて、上映会の直前の12月4日ごろだったか、事前に「忘れてないですか?」と電話とファックスで確認したときにも、「大丈夫、行く行く!」と言ってたんですよ。
当日は、北海道中からお年寄りのお客さんたちが集まってきて、上映三時間くらい前から並んでて、「元気にしてたぁ?」と同級生か何かのように楽屋入りするこまどり姉妹に手を振ってたりして、かなり盛り上がってました。でも、お昼ごろになっても朝倉さんが来ない。こりゃしょうがねえな、と思って、司会の僕も会場のお客さんに謝りました。まあ、朝倉さんのことですから、どうせまた青森や函館あたりで飲んでそのまま沈んでるんじゃないでしょうか、と、その場はとりあえず収めたんです。
そうしたらその翌日だったかな、電話が入って、実は亡くなられてた、と。ああ、こういうことってあるんだな、と思いましたね。でも、やっぱり朝倉さん、会場に来てくれてたんだな、とも思った。ホールの最後方で腕組みしながら眺めてたな、と。その意味では、今井さんのおっしゃるように、12月8日が朝倉さんの命日だと思ってます。
今井 朝倉さんは飲みの席で、こまどり姉妹の「ソーラン渡り鳥」なんかをよく口ずさんでいました。彼女たちは東京・山谷をバックグラウンドにもっているから、そこをしっかり踏まえて聴かないとわからないんだ、と。
大月 いやぁ、ほんとに来て欲しかったですよ。だって朝倉さん、年寄りが好きだったじゃないですか、特にバアさんがた(笑)。実際その時も、またその後もこまどりさんには何度かお話を伺って、門付をしてまわっていたころの話、上京して山谷に住んで、お座敷の営業なんかにも声がかかって活動を広げていった話とか、そりゃもうたまらなかったんですが、ただ、もしも朝倉さんがいてくれたら、もっといろんな角度からもっとたまらない話をたくさん引き出してくれたんじゃないかなぁ、と。
今井 こまどり姉妹は、この論集のテーマである「芸能と任侠」とも接点があります。朝倉さんの語るこまどり姉妹をもっと聞きたかったですね。
大月 まったく。北海道じゃ稼ぐのは限界があるから、お父さんがこまどり姉妹を山谷に連れてくる。小学生くらいの女の子二人がドヤ街で門付をする。そのうち評判になって料亭なんかにも余興として呼ばれるようになる。そこで政治家の大野伴睦なんかに出会って引き立てられて……とかもう、そういう当時の世相含めての出世譚がほんとに面白かったです。
彼女たちは学校を出ていないし、三味線で歌を歌うことでお金をもらう「流し」だった、つまり乞食だった、これ、ご自分で悪びれずはっきり「乞食」とそうおっしゃってますから。だからレコード会社と最後まで正式な契約を結ばせてもらえなかったのよ、と。
こまどりさんの少しあと、北島三郎ぐらいから、「流し」上がりでも歌手として認められるようになったんだそうで、北島さんは「流し」の先輩の自分たちに対してとても礼儀正しくやさしく接してくれた、だからサブちゃん、サブちゃん、とすごく親しみを込めて呼ぶんですよ。それまでは戦前以来、音楽学校を出て楽譜を読める人たちが、正規の歌手、作曲家としてレコード会社と契約して雇われるのがあたりまえで、海のものとも山のものともつかない彼女たちみたいな存在は、まともに扱われなかったんだそうです。
今井 江戸期には「賤民文化」が花開きます。そういう芸能の歴史がこまどり姉妹には滲み出てきてしまうところがあります。朝倉さんはそういうものを掬うのがとても上手な人でした。いわば朝倉喬司という存在自体が市井の歴史を召喚してしまうような磁場をもっている。そして、ジャーナリストのように対象と距離を置くというよりは、むしろ融合しちゃうような面がある。渡世という言葉がありますが、渡世と芸能、渡世と漂泊は密接に関わっています。朝倉さんがずっと書いていたテーマのひとつですね。
先日、歌手の浅川マキのプロデューサー、寺本幸司さんが『音楽プロデューサーとは何か』を出しました。浅川マキもキャバレー回りをしていた。フォークでも演歌でもロックでも、日銭を稼ぐところからレコードを売るようになるまでの、渡世と漂泊の道がある。そのことをこの本から教わりました。
大月 そういう意味で言えば、たとえばあの暗黒舞踏だってキャバレーやストリップでどれだけ稼いでいたか。それを調べている知り合いがいるんですが、土方巽あたりが元締めになって、若い人たちをそういうところに回してたくさん稼いでいたみたいですね。ストリップの現場では知られている話らしいですが、演劇史などの分野ではそういう稼業、「シノギ」の面はほとんど語られていないですよね。
今井 なるほど。朝倉さんが芸能を見るときの視点は、縦にも横にも逸脱します。現代をひょろひょろ歩きながら見ていても、そこに落ちている江戸や中世のかけらを拾い上げていく。構造主義などとは関係なく、身体が共時性に反応するといえば良いのでしょうか。また歌と革命が結びついたり、ブルースと音頭が一緒になったりする。縦と横、歴史と情況を自在に逸脱していく。そこが朝倉さんの魅力だと思います。それは朝倉さんが柳田国男や折口信夫から学んでいたことなのではないでしょうか。
大月 朝倉さんって実は勉強家で、すごくブッキッシュな人ですよね。いろんな文献に結構ちゃんとあたって、相当調べている。いわゆる大学のお行儀いい学者の調べものとは少し違うけど、それぞれのテーマの勘どころというか、いいポイントを文献資料介しても案外押さえてる。その逸脱が活きてくるのも、実はそういうブッキッシュな部分の押さえが効いてるからだと思います。
で、そういうブッキッシュさには世代性もあるように思うんですよ。活字が良くも悪くも、もっとも信頼できるメディアだった、そういう情報環境のなかで育ってきた世代の一人なんだ、と。もちろん朝倉さんは週刊誌の記者でルポライターですし、僕にとっては同じく大事な書き手である平岡正明にしても音楽評論もやっていたわけですが、みんなそういう活字媒体の記録に対する誠実さがその仕事のベースにあると思ってます。少し上の世代だと、竹中労なんかもそう。デスクワークとフィールドワークは二分法じゃない。このへん、活字あっての現場の豊穣さみたいなのは、もっと意識されるべき論点のはずですよ。
ただ、朝倉さんが柳田と折口をどこまで意識していたかについては、本人からちゃんと聞いたことはないですね。てか、折口はいきなり古代に行っちゃうじゃないですか。薬屋の息子で、自前で歯磨きなんかもキツいの調合して、コカインまでやってて原稿用紙に血しぶきが飛んでた、とか。きっとクスリやらなきゃ『死者の書』なんて、ほんとのところはわからないですよ、あれ(笑)。なので、折口の仕事はある種トリップの産物、ドラッグ文学みたいなもんで、その意味でも当時の柳田も含めて、大正から昭和にかけてのモダニズムの産物だと思ってますが、朝倉さんはそういう意味では折口より、むしろ柳田に近かったんじゃないかな。梅棹忠夫は柳田の方法を科学だとして、文化を理解する方法には「つらぬく論理」だけではなく「つらねる論理」があると言ってましたが、これは卓見で、朝倉さんもそういう「つらねる論理」で文化を理解しようとした人かと。
今井 朝倉さんのあの歌い方は、その連関想起法なんだと思います。理屈ではなく、そういう身体として反応するところがすごい。だから、その文体は、ねじれたりうねったりする。
大月 なるほど。それは文字の連関想起ではなくて、むしろ音声や身体感覚も含めた連関想起だったんじゃないかなぁ。酔っぱらうとあの「犬殺しの唄」が飛び出して、でもそれが「ぐろーりーぐろーりーはれるーやー」とリパブリック賛歌にナチュラルに転調して、さらに野口雨情や西条八十、河内音頭や浪曲にまでどんどん脱線していく。まあ、ある種の痴呆老人みたいなもので、当人ののっぴきならない原体験みたいなものの周りをぐるぐる回っている。でもその動きの意図や背景も、見える人には見えるところがあった。
www.youtube.com
最初期の『犯罪風土記』や、これは割と見落とされてますが対談・座談集の『天覧思想大相撲』(平岡正明・上杉清文)とかでは、朝倉さんは本当に好き放題語ってて、ああ、気持ちよさそうだなぁ、ということがよく伝わってきます。
今井 『バナちゃんの唄――バナナ売りをめぐる娼婦やヤクザたち』もそうですね。
大月 あれはもう絶品です。お好きな方にはたまらない(笑)。ただ、そういう語りや文章に対して、読みの水準がうまくシンクロできるかというと、読み手を選ぶところはあるでしょうね。いまどきの若い衆世代じゃもう難しいかもしれない。何より、そういう朝倉さん的な身体をもった日本人自体が減ってきてるじゃないですか。とすると、その読み手もいなくなる。だからどんなにテキストの素材があっても、発見されることがないままになってしまう。朝倉さん的なテキストは、実にそういうふうに疎外されてゆくんだろうな、と。
今井 朝倉さんは現場にいくとよく踊っている。民謡を聞いて歌を合わせるというよりも体が動いていく。ふつうのルポライターやジャーナリストって、そういう反応をしないですよね。朝倉さんは積極的、攻撃的に反応していくから、その場がわあっと盛り上がる。
大月 あれは意図的なものではなく、反応してしまう身体があってしまう、ってことかと。 勧進元の錦糸町の河内音頭にもよく姿を現わしてましたよね。そういえば山口昌男も踊るんですよね。お世辞にも上手じゃなくて、見てられないんですが(笑)、それでもとにかくその場に身体ごと入っていきたがる。山口さんは東大の国史の出身で、もとはブッキュッシュの権化でフィールドワークなんてできない人だったのが、東京都立大の大学院に行って人類学を始めた。当時、都立大の社会人類学のトップだった岡正雄が沖縄に山口さんを修行に行かせた際、僕の大学院の指導教員だった野口武徳さんが同行、一緒に現地調査をしたそうで、面白い挿話もいろいろあるんですが、その山口さんや朝倉さんが錦糸町の河内音頭の踊りの輪にフラフラしながら入っていく後ろ姿は、僕の裡の同時代の記憶と共にある風景です。
ヘンな言い方になりますが、ああ、こういう人が字を書いたりものを考えたりしてもいいんだ、という驚きみたいなものがあって、ほら、ルポライターやノンフィクションライターって、たいていしち面倒くさいじゃないですか。溝口敦さんや佐野眞一さんなんか今じゃ偉くなりましたが、朝倉さんは資質的にそういうタイプの人ではなかった。個人的な印象としては、たとえば吉田司や関川夏央なんかに近かったような気がしてます。
今井 そうかもしれません。関川さんの『海峡を越えたホームラン』は、在日コリアンの問題を扱ったいい本ですね。
大月 あ、それなら根本敬さんらの『ディープコリア』も(笑)。まさにノリと身体の問題ですね。そういう人たちには関係と場に対して開かれた感覚があり、場のなかに踊り込んでいく身体、自分と他人の境界もわからなくなる瞬間がうっかり降臨してしまう、そういう身体がある。それでいてその身体を介した文字で表現できる。そのへんのバランスというものが、最近の日本語環境での優秀で意識の高い人がたから忘れられ、文化的資源としても失われている気がしますね。
今井 朝倉さんは初期には共同性という言葉をよく使っていました。いま大月さんがおっしゃったことは、朝倉さんが共同性という言葉で言おうとしていたことなのではないかと思います。その後、さらにアンダーなところに降りていく。もともとアンダーな人でもあったから、本来の場所に戻っていったようなところもあるかもしれません。
大月 ただ、朝倉さんの文脈だとそれは近代文学的な自我や自意識なんかじゃなく、そういう共同性の中ではじめて生かされている自分をつねに感じているような資質があったんだろう、と。柳田国男と近いところがあるとしたら、そういう部分も含めてなんだろう思います。
でも、ジャーナリズムの世界でああいうやり方が仕事として成り立たなくなって久しいわけですし、読者はもとより、ああいう才能を発見する編集者自体、おそらくもういなくなってるんでしょうね。
今井 目的をあらかじめ設定してそれに向かって進めるやり方はどうもつまらない。朝倉さんはそう思っていた。晩年には、どういう意図かはわかりませんが、クリプキとジジェクを足して二で割るというようなことも言っていましたね。
大月 そういう現代思想系のものもどこか読んでたんでしょうね。世代性を感じるのはそのあたりなんですよ。そういう関心もあったし、読んで肥やしにしようとする土台があった。平岡さんにもそういうところありましたね。極真の試合会場にも連れていかれて、「いいだろ、面白いだろ」というノリで熱く説得されましたが、何がいいのかは正直よくわからなかった(笑)。竹中労さんとは一度しかお会いしたことはありませんが、「たま」を語る『「たま」の本』を出した時の取材でうかがって、あれはどこかの喫茶店だったか、もうお身体が悪くて点滴のバッグみたいなの持ち歩かれてるような状態だったんですが、話の流れで、「たま」ってのは大正アナキストの末裔なんだとおっしゃるんで、それってつまりオタクってことですよね、と訊いたら、「そうです!!」と破顔一笑、熱く手を握られました(笑)。僕のなかではみんな同じハコの書き手なんですが、ライターであれ何であれ、そういう書き手がいなくなってきているのは寂しいですね。
今井 竹中労さんの言葉でいえば、えんぴつ一本で立つ「えんぴつ無頼」ですよね。「えんぴつ無頼」がいなくなってしまった。朝倉さんも、自分は筆一本で渡世の道を歩いている、どこかの組織に属して一定の収入を得ているサラリーマンではないと強調していました。
大月 「無頼」という言葉自体、もう通用しませんってば。それを支えていたダンディズムやら美学やら何やらも全部まとめて「昭和」の「おっさん」として笑い飛ばされて、そこで終わっちゃう。
今井 朝倉さんの取材の仕方は、社会学や人類学のフィールドワークと似ています。調査する地域集団、宗教団体に入っていってしまう。すっと入って、すっと出ていく。
大月 そうそう。そこに居着くことなく、結局は通り過ぎていく。「そうか、俺は無人の舟なんだと思う」とすでに『バナちゃんの唄』で言ってましたが、そういう「流れ」の意識がまずあって、そこに身をまかせざるを得ないというある種の諦念みたいなものが身に宿ってて、でも流れながらも考える、まわりを見ながら「自分」を意識し続けている。そこのバランスは生まれつきの性質か身につけたものなのか。どこまでもそこの人にはならない、あるいはなれない。宮本常一風にいえば「世間師」なんでしょうが、つねに自己疎外みたいなものを抱え込んだまま、でもその場で、その他大勢と自分はどこかでつながっているんだということを信じながら願っている。そういう意味では近代のインテリのある祖型でもあります。でも、なかなかそういうふうには読まれてきてないんじゃないかなぁ、これまでにしても。
てか、そもそもいまの若い人は朝倉喬司って知らないでしょ。平岡正明はジャズ評論などで再評価される動きはありましたけど、朝倉さんはまずもってその取っ掛かりからしてもう難しいでしょ。
今井 平岡さんも竹中労さんも有名どころのジャズや映画を押さえているけど、朝倉さんはせいぜい河内音頭ぐらいですからね。
大月 だからこそ別の味わいがあるんですけどねぇ。いまなら、ジャーナリズム方面から、別役実さんとの対談『犯罪季評』などが入口になり得るのかなぁ。でも、そういう取材や報道という間尺からみるだけでは、どうしても外れてきてしまうところが朝倉さんにはあって、で、その部分こそが魅力というか豊かな本質だったりするんですよねぇ。
『犯罪風土記』を書きながら、でも同時にその過程で変なものをいっぱい見たり聞いたりしていて、そっちの方が面白かったりする(笑)。あれは1990年前後だったかな、飲みの席で、最近の若い記者は真面目なんだか忙しいんだか、クルマで来て話を聞いて、すぐ帰ってっちゃう、とボヤいてましたね。一歩横に出たら見えるものが、あのサイクルにはまってしまうと見えなくなってしまうよなぁ、もったいないなぁ、としみじみ言ってた。名刺をもって、会社の旗を立てたタクシー乗り回して腕章をつけたりして現場にわれがちに陣取るのはいいけど、一歩横になんで出ないのか、と。僕の言い方だと、一歩下がって、その場にいながらいないみたいな、「おりる」立ち位置じゃないと見えないものがある。
今井 取材者が目的地にいくことを優先して、途中で降りてみたり道草を食ったりすることを惜しんでしまう。でも朝倉さんは違う。たとえば、いつも二時間ぐらい遅れてくる佐伯修さんと待ち合わせするときに、朝倉さんは嫌な顔をせずに、その間にあっち行ったりこっち行ったりしている。相手が遅れることを楽しんでいるんですね。終わる時間もかっちり決めない。目的から外れるそういう面白さをわかっていたんだと思います。
朝倉さんの目線は、けっして上から目線ではありませんでした。『凝視録 為五郎のぞき人生』という本では、そういう覗きの目線も獲得しようとしています。
大月 ああ、それは朝倉さんの仕事のなかでも特に異質な、とんでもない本ですね。「覗く」という行為が日本人にとって何なのか、という本質的なテーマに迫っています。セクシュアリティやメンタリティの問題も絡んできますし、そもそも江戸期からのぞきからくりという大道芸もあったりしますし、いろいろ奥が深い。
待ち合わせの話でいえば、冒頭触れたこまどり姉妹のイベントでも、彼が遅れてくるのは別にあたりまえで、まあいいや、どうせまたどこかで飲んでるんだろうな、と本気で思ってました。だから特に気にもしてなかった。でも、そういうのを許容する関係って、もうほとんどなくなってきてますよね。そんな関係は仕事はもちろん日常でも許されないし、まずそういう人間ごと「なかったこと」にされて排除される。まさに目的合理性最優先の論理ですよね。それは抗いがたい社会の変化でもあるんでしょうが、でもほんとにそれで世の中、大丈夫なのかなぁ、と。
どこに寄り道するかわからない、ゴールを決めない千鳥足の豊かさというものを身体でもって証明してくれている存在がいた、それが僕にとってはとてもありがたかった。だから、いまの10代、20代の若い人たちに、そういうヘンな大人がそういう豊かさを身体でもって見せることができるか。朝倉さんや平岡さんから僕が教わってきたことを、自分がバトンとして渡せるような年寄りになれるのかな、と、いまさらこのトシになってもまだ自問自答してます。
今井 まさにそうありたいものですね。朝倉さんの芸能論という形で今回の本はまとめられていますが、ぜひこの機会に朝倉さんの本を手にとってみてほしいですね。
king-biscuit.hatenablog.com



![<映画>こまどり姉妹がやって来る ヤァ! ヤァ! ヤァ! [DVD] <映画>こまどり姉妹がやって来る ヤァ! ヤァ! ヤァ! [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51pTGxlTnwL._SL500_.jpg)