

偉そうに「漫画時評」という看板で仕事をさせてもらっているくらいだから、この場では、たとえば「論壇時評」などのように、その時その時のマンガをめぐる状況的な話題を拾い上げてゆくことを求められているのだとは思う。昔、小林秀雄は時評の極意について「文壇的問題を捕えて、それを文学的問題に還元する術だ」てなことを言っていたと、どこかで読んだことがあるけれども、しかし、今どきかのブンガクの世界でさえそんな幸せな「文壇」など成立しなくなっているご時世に、ましてマンガなどという辺境に「漫壇」などあるわけもなし、こういう意味での「時評」など実はかなり強引な話ではあるのだ。
これはマンガ評論に多少なりとも関心を持つ人たちと話をする機会があると、よく話題になるのだけれども、どだい今、市場に出回っているマンガを全て読むことはまず絶対にできない、ということだ。いや、もちろんそんなものは今に始まったことでもない。敗戦直後の貸本劇画の全盛期にしたところで、それこそ玩具の流通経路に地方地方で流されていた貸本劇画を全て読みつくせた人間などいなかったはずだ。そういう意味での状況の一望透視が不可能なことは変わらないと言えば変わらない。しかし、それでも何が重要な作品で、何が今の状況を照らし出し、この先時代を超えてゆく内実を持った表現か、といったあたりの認識を、たとえできなくても何とか共有しようとする誠実さは、80年代前半くらいまでは、マンガ評論の世界でさえもまだあったように思う。
けれども、今やそういう「全体」や「普遍」への志向は、驚くほど衰弱している。いや、それどころか、そのような「全体」や「普遍」があり得ることさえ自覚していない者たちが平然と一人前の顔で、形だけは評論めいたもの言いを垂れ流していたりする。確かに、評論家にとりあげられがちな作家や作品というのはある。まして、今どきマンガを語ろうという意欲を持っているような人間は三十代から上が中核だから、彼らの眼にとまるのはどうしても70年代から80年代にかけて活躍した人たちが多く、逆に90年からこっちの〈いま・ここ〉の同時代的な動きについてはどうしても遅れてしまうということもある。事実、去年から不定期にやっていて、一部で意外に支持されている『BSマンガ夜話』(NHKBS-2 次は九月下旬です)にしても、そういう〈いま・ここ〉の読者の感覚に沿った作品の選び方がなかなか難しかったりする。にしても、だからと言って〈いま・ここ〉の速度にだけ同調しようとするあまり、マンガにとって何が重要なのか、というあたりの本質論をないがしろにしていいというものではないと、僕は思う。
たとえば、評論家筋では、去年あたりから松本大洋の『ピンポン』の評判がいい。あるいは、同じような評論家受けのいいものとして、文春漫画賞をとった西原理恵子の『ぼくんち』がある。もっと言えば、まとまった作品が描けなくなって久しいにも関わらず、江口寿史の動きはやはり評論家方面には注目されているし、関川夏央と谷口ジローという名コンビによる明治ものの連作も、やはり必ずそのようなクロウト受けしている。
けれども、それは言わば「純文学」としてのマンガなのだ、とも思う。たとえば、『コロコロコミック』などにずっと頑張っているような、あるいはまた、学習雑誌にあれこれ手を換え品を換え描き続けているような、そんな言わば「商売としてのマンガ」をじっとやっているような作家たちもまた、今のこの国のマンガの「全体」を支えているのだと僕は思う。純文学だけを文芸批評の対象として〈それ以外〉の大衆文学を添えものとしてしか見ない態度がどれだけ本質的な「批評」をやせたものにしてきたか。そんな近代文学をめぐる言説の七転八倒の歴史から学びもしない、できないサブカルチュア評論など、きっと今のブンガク程度の達成にもこの先、届くことができない。
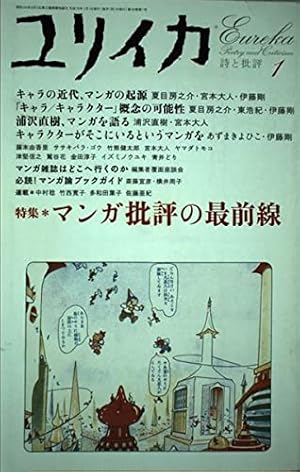
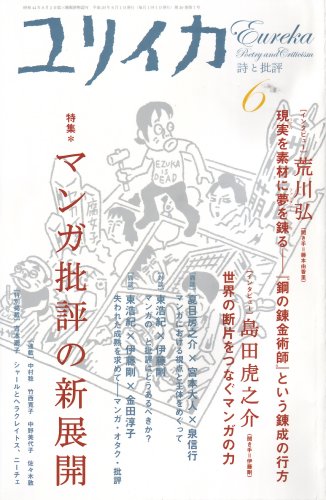
これから先、マンガというのはどんどんある世代にだけ熱烈に読まれるような、そんなメディアになってゆくのだろう。アニメ世代というのが今の三十代半ばから二十代半ばくらいまでの間に最も典型的に現われていると言われるように、マンガ世代というのもそれより少し上、四十代半ばから三十代いっぱいぐらいまでの幅の中に位置づけられるのだろう。これはきっとサブカルチュアのどんなジャンルでもそうなのだろうが、とにかくそのジャンルについて語りたい、という欲望が熱くふくれ上がる時期というのがある。とりわけ、そのジャンルが成立してゆく過程と共に成長してきたような世代にとってそれは切実だ。それよりもまた下にはゲーム世代というのもすでにあるし、逆にもっとさかのぼれば、新劇なんてのもそうだったろう。そして、それらのジャンルよりは寿命も長かったし、また世間的なステイタスも与えられたにせよ、きっと文学なんてのもそういうジャンルのひとつだったのだろう。
そう、それそれの世代にとって切実なサブカルチュアがあった。そして、テレビもなく、横丁の映画館で映画を死ぬほど見ることができた世代というのが生粋の映画ファンの中核で、その中からは、たとえば淀川長治さんのような映画の申し子のような評論家も出てくる。好きで好きでたまらない、ただそれだけで一生を通すことができる人間が出てくるためには、やはり個人の意志とは別に、いくつか幸せな条件が偶然に揃う必要もあるらしい。