
●
いまどきの情報環境のこと、無職で隠居に等しい身の上で、外へ出て人と会う用事なども基本的になく、それこそ日々ひきこもりに等しい生活をしていても、世の動きや動静は文字に限らず画像、映像、動画に音声、いずれそれら各種「情報」として平等に、なんだかんだ言いつつ四六時中行動を共にするようになってしまった手もとのちっちゃなハコや、世に生きる上でとりあえず持っていないと頬返しもつかない道具になっている電脳端末の画面を介して、あっちから勝手にどんどん流れてくる。
だから、ウクライナのことにしても、これまでそれなりに体験してきたはずの遠い国の紛争沙汰とは段違いに生々しく、かつ距離感のとりにくいいまどきの「戦争」の風景として、これだけ日々入ってくると、全く関係ないことにして日々の習い性、いつものように自分の仕事だけをすることも、案外難しくなっているところがあります。
「情報」の密度も速度も、そしてそれらの質も、みんなケタ違いにあがっている以上、致し方ないことであり、かつ、それらに対する個々の反応もまた、人それぞれのそのあり方自体も含めてつぶさに「情報」として投げ返されてくる。専門家と称する人がたから、会ったことも見たこともないどこかの無名の市井人、世間一般その他おおぜいのひとりひとりに至るまで、ほんとに誰もがあれこれ論じたり語ったりわかろうとしたり、そのさままでもが、いちいち小さな「情報」として手もとに送られてくる。なるほど、そういう時代、そういう情報環境を生きざるを得ない現在のこと、それはそれでどんどんやればいい。
ただ、そんな近頃の日々に、ふと、思ったことがひとつ。
あのウクライナの人がたもまた、かつてソ連軍として戦った世代は当然、ご存命のはずだし、実際いま、戦火の下にも生きとらすはず。モニタにいくらでも流れてくる惨状と現地の人がたの「情報」としての映像の中に、そんな経験もまた確かに織り込まれてある、そういう視点はどこかに担保されているだろうか。そして、他でもないこの本邦の国土にも、かつて満洲や北方領土から引揚げてきて、ソ連軍に蹂躙された体験ある方もまだご存命のはず。だったら、そういう人がたに〈いま・ここ〉のウクライナのことを、分断されたロシア軍に蹂躙されている現在のことを、たとえ断片の感想でも印象でも尋ねてみる、そんな発想の足場もまた、本邦いまどき商業メディアのどこかにまだ、確保されているのだろうか。

あるいはまた、国際政治や軍事戦略の専門家という人がたが、メディアの舞台ににわかに多く登場するようになっていて、またその多くが40代から50代そこそこ、いわゆる氷河期世代と呼ばれるようなあたりの年まわりで、これまで表に出てきてなかった新鮮な面々になっているのも、昨今ウクライナ情勢をめぐる新たな現象です。それは同時に、これまで連綿と惰性と共にメディアに登場し、コメンテーターとして単なる個人の感想に等しいことをもっともらしく垂れ流すのが仕事になっていたような文化人や評論家といった「タレント」立ち位置の人がたが、彼らの操ってきた言葉やもの言いなどと共に、一気にその信頼性を失い居場所もなくしつつあることと表裏一体らしい。いわゆる人文社会系とくくられてきたような学術研究、いや、そこまで大層なものでなくても、いわゆる「教養」と何となくされてきた知識や知見の群れが、もう〈いま・ここ〉を説明する道具として役に立たないものになっている、そのことが、このたびのウクライナをめぐる「戦争」という決定的な〈リアル〉を前にして、世間の眼に最終的にあらわになっているということかもしれません。
ただ、だとしても、ここでもまた、敢えての留保を加えておかねばならない。
彼ら彼女ら、ここにきて新たに姿を現わしてきた若い世代の専門家たちの知見には、世代性や育った環境――90年代の大学院重点化以降、海外の大学や大学院に留学して博士号を取得したような人がたが多いことなど――もあるのでしょう、旧来の本邦「教養」系の、それこそ「文化」や「文学」「歴史」といった要素を大黒柱と頼んだ戦前このかたのたてつけからは良くも悪くも自由で、解き放たれたような肌合いが強いように見えます。それは、同じ眼前の〈いま・ここ〉のできごととしてのウクライナをめぐる「戦争」についての彼らの理解や説明の枠組みには、こちら側旧世代的な「戦後」「昭和後期」設定の「教養」からは半ば自明であった補助線が、初手から引かれないままになっているような印象につながっています。
いや、もちろん優秀な彼ら彼女らのこと、「文化」も「歴史」も「文学」も当然、織り込んでいるでしょう、彼らの語彙において。そしてその語彙の文脈において、彼らの眼に映じている〈いま・ここ〉のウクライナ情勢もまた、いまどきの情報環境に見合った「そういうもの」としての〈リアル〉を必要十分なほどに湛えている。それはそれ、時代が変わり、それに応じて世界の現われ方、現実の輪郭もまた手ざわりと共に移ろってゆくことの表現でしょうし、それらがこれから先、新しい時代と情報環境における本邦日本語を母語とする間尺での〈リアル〉を紡ぎ出してゆく、標準的な文法になってゆくのかもしれない。いや、おそらくそういうこと、なのでしょう。
けれども、それらの前提の上でなお、確かに言っておかねばならないと思うのは、もはや旧来の枠組み、役立たずであることがあらわにされてしまっているらしい「戦後」「昭和後期」設定の「教養」の枠組みの側から、同じ眼前の〈いま・ここ〉を見てゆこうとした際に、やはり見えてしまう風景というものも、同時代の現われとして未だ確かに「ある」ということ。そして、それが見えにくくなってゆくだろう、その分「なかったこと」にもされかねない何ものかについてのさささやかな記述と、そこに託され得るだけの、それらを自明に生きてきた事実についての存在証明です。

●●
かつて敗戦前後、火事場泥棒のように満洲や北方領土に押し寄せたソ連軍の兵隊たちは、ズダボロの服でだらしなく歩いていたが、彼らが行軍しながら歌を歌い出した、その歌声がすさまじく力強く美しいものだった、といった趣旨のことを、どこかで誰かが書いていたような記憶があります。五木寛之だったかもしれない。でも、五木寛之の書いたものなどもうずいぶん忘れていたので、試しに手もとの雑書の山を、すでにおぼつかなくなっている記憶をたどりつつ、暇にまかせて少しあさってみていたら、ありがたい、出喰わしました、記憶そのものにあたるものかどうかはあやしいながらも、どうやら似たような記述に。

「私はあるひの夕方、宿舎に帰ってゆくソ連兵たちの隊列と出会った。連中は自動小銃をだらしなく肩にかけ、重い足どりでのろのろと歩いてゆく。服装は粗末を通りこしてボロ布にちかく、どう見ても物乞いの集団としか思えない一団である。」
この「物乞い」は正しく「乞食」と書きたかったところだろうな、と思いながら、肝心なのはその先。
「突然、その隊列のなかのいく人かが、低い調子で歌をうたいだした。すぐに何人かが加わり、たちまち全員がそれに和して歌声が大きくなった。」
ああ、こういう「うた」の歌われ方、「うた」になってゆく瞬間というのが、確かにあった、本邦にも。どうやら最近はもう、忘れられてしまった「うた」の宿り方なのかも知れないけれども、かつてある時期までは間違いなく。歌いながら歩く、遠足でもハイキングでも、あるいはそこまでゆかない少人数の散策めいた足どりの中でも。

ただし、五木は、こう続けていました。
「なんという歌声だったろう!それは私がかつて聴いたことのない合唱(コーラス)だった。胸の底から響くような低音。金管楽器のような高く澄んだ声。いや、声を通りこして心に響いてくるなにか奥深いもの。私は体がしびれたようになって、その場にたちすくんだ。」
合唱だった、もしかしたらハモりながらですらあるような、「行進曲とはまったくちがった哀しく暗い歌声」での。こちらがうっかり想起したような、歌いながら歩く時に歌われるような「うた」とは、少し違っていたらしい。
「私はあたりが暗くなっても、まだその場を動けないでいた。アタマのなかでえたいのしれない混乱と疑問が渦巻いて、いまにも卒倒しそうな感じだった。地面にひざまずいて祈りたいと感じた。そして同時に、こんなことがあっていいのか!と大声で叫びたい気持ちでもあった。そして、おれは絶対許さないぞ、と心のなかでくり返した。こんなことは認められない、と、私は感じたのだ。毎晩のように女たちを連れさりにくる強姦者たちが、こんな美しい歌をうたうことができるのなら、おれは絶対に歌なんて許さないぞ、と。」(五木寛之「許せない歌」『オール読物』2月号、1992年)

言うまでもなく、五木寛之はもともと「広告・宣伝」の場から、それも60年代の高度成長期、それら「広告・宣伝」の領分が世間に否応なく可視化され、具体的な影響と共に存在感を示すようになってきた経緯の中、世に出てきた書き手です。それこそ他でもない、あの三木鶏郎のまわりにも身を置いたこともありますし、ラジオの放送作家やCM制作の現場なども広く経験、作詞家としてクラウンレコード専属だったこともある。いわゆる「文学」前提の作家というより、自身認めているように「エンターテインメントとしての読みもの」のライター的な意味あいの強い書き手であり、広義のマルチ・クリエイターでした。そういう意味で「うた」については人一倍鋭敏ですし、また、プロとしての関わり方も含めて、五木寛之という書き手の経歴の裡でも重要な位置を占めてきています。
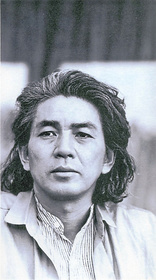

その彼が、この時のソ連兵たちの「うた」から受けた衝撃を、強く引きずっていた。
「その記憶は、いまだに消えないこだわりとなって、私のロシア民謡に対するルールとなっているらしい。私はある断念を誓ったのだ。歌をして抒情の域にとどめせしめよ、というのがその決心である。そこから一歩も踏みいるまい、と、きめたのだ。」
この「抒情の域」という言い方の、その内実とは何か。その後、職業的な作詞家として商品音楽の歌詞を、そしてCM制作の現場担当者としてそのコピーやジングルなどを、いずれ「広告・宣伝」を介したメディアと「大衆」という「市場」との関係を計測する作業として、それぞれやってゆくことになった彼のキャリアの裡において、日常的な間尺でのキモチやココロといった不定形な領域に、人々の手にあったノズルを与えるけれども、しかし決してそれ以上に踏み出させない制御の効いた範囲にそれら不定型な領域を収納しておく有用な道具としてのことば、といったものだったのではないか。だとすれば、それはまた、そのようなことばに付随する彼にとっての「うた」のイメージの原型にまでつながるものでもあったはずです。
「かつて〈うたごえ喫茶〉のブームがあった時代も、学生の私はついに一度もその種の店に足を踏み入れたことがなかった。いろんなロシアの歌を愛唱することはあったが、それはあくまで抒情の小道具として愛したにすぎない。」
高校時代からツルゲーネフなどロシア文学に興味を持ち、大学で露文科に属した彼が、しかしロシア民謡に対してこのような縛りを自ら課していたということは、「うた」をめぐるこの場の道行きにとっても、ちょっと備忘として加えておきたい示唆になります。

そう言えば、シベリア抑留から帰還した元日本兵たちが、みんなで革命歌を歌いながら上陸した、という話が、かつてありました。それもまた当時のニュース映像に残っているのだけれども、そして、その彼らの身ぶりや歌い方のたたずまいはその後、シベリアで「洗脳」されていたからだ、という説明で語られてもいった挿話なのだけれども、ただ、それらのことを別にしても、当時のその復員兵である彼らの、その「うたう」感覚の共同性とは果してどんなものだったのか。たとえば、旧軍の軍歌演習などでの「うたう」とどう違っていたのか、あるいは地続きだったのか。
「帰還者の中には、夢にまで見た帰国を果したにもかかわらず、岸壁で待っていた家族にも会わないで、赤旗を掲げて隊列を組み船を降りると、桟橋から東舞鶴駅まで「インターナショナル」や共産党の歌を歌いながら徒歩で行進し、列車で東京へ。そして代々木にあった共産党本部に行って全員が入党手続きをした集団もあった。彼らは「人民の敵である「天皇の島」に帰って来た」という意気込みで帰国したのである。」(細川呉港『舞鶴に散る桜――進駐軍と日系アメリカ情報兵の秘密』飛鳥新社、2020年)

これらの問いは当然、「うたごえ」運動など含めた戦後の「ロシア経由のうたその他、文化一般」の受容過程にも関わってきます。たとえば、こんな細部からでも。
「酒場「どん底」では、どん底歌集というのを売っていて、ある歌を一人が歌い出すと、期せずして若人の大合唱となる。喚声と音楽が一しょになって、なまなましいエネルギーが、一種のハーモニィを作り上げる。何んともいえぬハリ切った享楽場である。」(三島由紀夫「世界的水準」『どん底歌集』所収、1961年)
この「合唱」は、「ハーモニィ」と言いながらも、「一種の」と限定されているように、いわゆるコーラスではなかったようです。同じ頃、砂川闘争の現場で、警官隊と対峙していたデモ隊の隊列の中から、半ば自然発生的に「赤とんぼ」の歌が歌われるようになった、という挿話も、戦後の思想史的脈絡で繰り返し語られる定番のひとつになっていますが、この時の歌もまた、単に声を合わせて同じ歌を歌うという意味での合唱ではあっても、きれいに分節されたコーラス的なものではなかったはずです。なるほど、そんなことを考えてゆけば、ロシア民謡が戦後の本邦世間一般にとっての「うた」のあり方に与えたであろう痕跡、というのも、まだうまくとらえられていないのかもしれません。
いま、ウクライナに侵入してきた21世紀のロシア軍は、モスクワやサンクトペテルブルグその他の、彼の地の光り輝く「文明」の場所、マチからはるか遠い辺境から連れてこられた者が多いと言われています。どうかしたら少数民族なども混じると言われているあの兵隊たちは、かつて五木が平壌郊外で耳にした「うた」のように歌うのだろうか。いや、ロシア軍だけではない、かつて同じソ連軍でもあったはずのウクライナ軍の兵隊たちもまた、やはりそのように歌うのだろうか。

……などと、またとりとめないことを考えていたら、ウクライナ軍が歌っている映像がありましたよ、と教えてもらった。なるほど、あった。オデッサの、あ、今はオデーサと呼ぶようになったのか、港町の防禦陣地つくり、市民も共に混じっていましたが、土嚢を手に手に手渡してゆく、かつては本邦でも「天狗取り」と呼んでいたやり方で作業をしながら、何やら大きな声でみんなで歌っていました。それは作業歌になっていたように聞こえたし、何より、軽くハーモニーを取ったコーラスとしての合唱にちゃんとなってもいました。また別のところではchantから、サッカー場のようにcall and responseを促すシーンもありました。
なるほど、「うた」と「うたう」は、ウクライナの人々の間に、まだ確かに活きているようです。