

実は最近、本が読みたくなくてしょうがないんだよ。このところ母親の面倒を見たり、忙しかったりしているから余計にそうなってるんだろうが、でも、そんな中でも特に小説は読みたくない。するすると頭に入って面白いものはないかなと思って、あ、そうだと思いついたのが、足立巻一の『やちまた』。この間から読み出して、少しずつしか読まないんだけど、これが楽しくてねえ。


――呉智英さんから足立巻一の名前が出てくるのは、やっぱりと思うと同時に、なんかうれしいですね。あたしなんかは立川文庫の研究の方でよく知っている人ですが。大学の講座の○○学といった枠組みとは別に自生してきた民間の知性、のひとりですよね。まあ、作家ですから当たり前なんでしょうけど。
できれば何もしないでこれだけ読んで人生を終わったらいいな、なんて思わせられるね。三十一年前に出ている本だけど、でも、気をつけないと、人生を誤らせる。私がこういう評論の道に入ったのは、この本のせいだよ。当時からプロ筋ではものすごく評判がよかった。でも、私が編集者なんかに「何か面白い本ないですか」と言われれば勧めるんだけど、それから少しして会って「どうだった?」と聞くと、たいてい、いやー、と生返事が返ってくる。うっかり感動してしまったらえらいことになる、というか、だいたい感動できないらしいんだな。でもね、これを読んで面白いと思えるような人はそれだけで異常な人だと思うよ。
いくつかの話が縦糸に三つぐらいあって、そこに横糸が織りなすように進行していく。だから、なまじ学者の本より難しい。しかも文法学の本だから、「江戸時代に文法学?」と、普通の人は五ページ読んだら投げるだろうね。でも、私的にはサプライズで、舞台が三重から静岡まで、それこそ松坂辺りから環伊勢湾的に、だいたい静岡の辺までつながっているから、学者があちこち行ったり、子供が病気になって医者に連れていったとか出てくると、余計面白い。
著者はもともとはビデオ系のジャーナリストだ。どこかのテレビ局か映画制作会社で飯を食いながら本を書いていた。こんな作品が書ける人は今いないよ。素養がないと書けないんだから。で、そういうものが書ける人がない。若い人にはもうこういう素養がないからね。それはとても寂しいことだと思う。

大正の初め頃の生まれで、これを書いた時点で六一歳、八十歳になるかならないかで亡くなっている。これは彼の集大成、つまりこれを書くために生まれてきたような人なわけだ。『立川文庫の英雄たち』、『夕刊流星号』、『虹滅記』、みんな名著なのだが、『やちまた』は名著ではない。そういうものを超えた異常な本なんだよ。ところが、もう絶版になって久しい。こういう本が評価されるのは、芥川賞、直木賞じゃなくて、基本的に大佛賞、毎日出版文化賞で、これは芸術選賞なんだね。一冊の本が、人生を変えるメディアになり得たんだから。

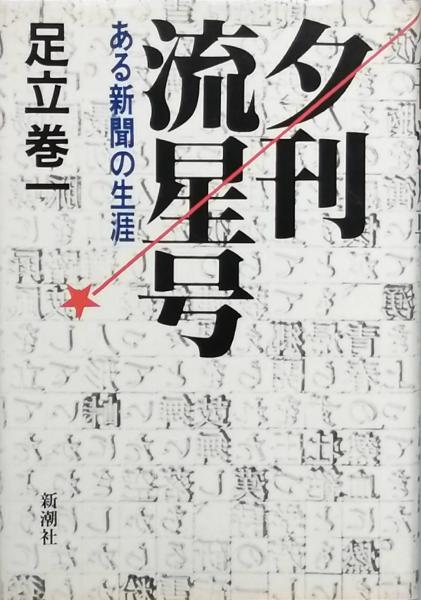

――本で人生が変わる、というもの言いも久しぶりに聞いたような気がします。これもう、今やギャグにしか聞こえないというのも、考えたら情けない話なわけで。
そういう意味じゃ、民俗学者の大月君におもねるわけじゃないけど、『月と不死』(東洋文庫)も面白いよ。ニコライ・ネフスキーは亡命ロシア人。一時民俗学で話題になったが、もう誰も興味を持たない。歴史に翻弄された人物というのはこういうものかなと思う。この本の解説を大きく書いたのが加藤九祚で、それを基にして『天の蛇』という伝記を書いた。

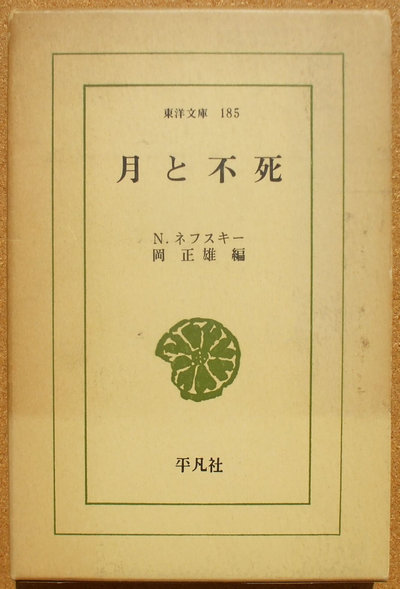
沖縄とか民俗学に興味がある人には、今も面白いはずだけど、これも「知識人像」が見えていた時代の本だと思う。ネフスキーの面白さはというと、革命前のロシアの知識人の話なのだ。青年たちは理想を持ち、しかも自分の知識を社会に生かすのが役割だと思って頑張っている。そしてシベリアの小数民族の伝記などを研究し、民俗学的な関心で、次に日本に渡ってくる。日本の、たとえば北海道のアイヌの小説だとか、あとは沖縄/琉球だね。沖縄は特殊な神話、伝承があるから、その研究をやった。柳田國男らとも付き合いがあったしね。
ところが一九一七年、ロシア革命が起こる。すると「先生方、申し訳ない。私はロシアに帰ります」と言い出す。「こんな混乱期に、ロシアに帰ってどうするつもりだ」、「いえ、われわれロシアの青年は、この革命を待ち望んでいたのです」と言って帰国するんだけど、結局は数年後には粛正にあって死刑になっちゃう。
彼は日本で正式に結婚している。現地妻じゃない。その日本人の奥さんもその後子供を連れて向こうへ行き、殺されてしまう。その遺児はすでに八十いくつ。その人のインタビューも含めて、これはいい本だよ。天の蛇というのは沖縄の虹のことだけど、蛇が水神系だから、雨とも通じていて、また沖縄だからニライカナイ(常世)の関係が出てくる。、一冊の本が人生を変えるメディアになり得た、そんな時代の一冊だと思うよ。

――あと、これは個人的な関心で聞くんですが、竹内好はどう見てましたか? あたし的にはかなり好きな人で、今のこういう状況でもっと読み直されていい人だと思ってるんですけど。
竹内好は小説家ではないが中国文学者だね。右翼の人などは今、批判しているし、批判はもちろんあってもいい。しかし、こういう素養を持った知識人が、最近は思想家の中でも出てきていないのも確かだね。インターネットで資料を集めて、どういう資料があってと列挙することはできるが、この時代にそれを自分の中に組み込んで思想として再構築して唱えたというのは、やはり竹内たちだった。つまり、本と活字によって自己形成、知的構築みたいなものをゆっくりとしていった、そういうやり方しかなかった世代だったんだよ。

――そのネットに代表されるような、ここ十数年ほどの情報環境の変貌が、それまでも見えてきていた知性の世代間落差みたいなものを、より一層はっきりと際だたせていると思いますね。思いっきり図式的に言えば、いわゆる「おたく」の問題の使用前/使用後、という感じになるんですが。
「おたく」は高度成長の「豊かさ」の中で育った世代のある部分に典型的に宿ったものであり、それは大きく言えばもちろん、近代化の過程でさまざまに転変を繰り返してきたニッポンの知識人のココロのありようとも連なっていて、その限りで歴史的な連続性の中にあるわけですけど、でも、と同時に、呉智英さんが今回もずっと説いてきているように、まさに「戦後」の、とりわけ高度成長の「豊かさ」のもたらした急速な大衆化ゆえに特化された特徴という、それ自体限定的な性格もあると思うんですよ。それが前世紀末、九十年代になってネット環境が出現して拡大してゆくと共に、「おたく」が成り立っていた文脈とはまた違う位相での大衆化が始まってゆく、と。いわゆる「教養」、文科系的な世界観自体その中で溶解してゆくわけで、「おたく」がそれ以降の新たな位相の大衆化によって出現し始めた新たな常民像みたいなものに包囲され、呑み込まれてゆく過程というのが、少なくとも前世紀末からこっちの状況だと見ています。これは唐突に聞こえるかも知れませんが、大学の解体、特に「教養」を支えていたさまざまな幻想が制度ごとバラバラにされていった過程は、そういう意味でかつてトンガっていた「おたく」のありようが、ネットの出現を媒介にした情報環境の変貌によってなめされて埋没していった風景と重なるんですよ。
結局、ネットの普及によって情報処理は加速されたし、それこそそこらのシロウトでもそれまでとはケタ違いに効率的に検索できるようになったわけですけど、でも、その便利さをうまく使えるのはやはりそれまでの活字がドミナントな情報環境で知的形成をしてきた経験を持つ世代なわけで。最近よく言われるネット掲示板その他でのやりとりにしても、中核になってそのカルチュアを形成してきたのは明らかに活字世代のリテラシーですよ。それがここにきて携帯電話を介してネットにアクセスしてくる新たな若い世代が進出してきて、また違う意味でのディバイドが見え始めていると言われてます。
ともあれ、活字がドミナントであった頃の、言わば自分が生きる速度で情報を血肉化してきたのがかつての知識人だったのが、今のこういう情報環境ではそのような知性の形成は良くも悪くももう望めないでよすね。単に活字世代、ネット世代、という図式的な分け方でなく、少なくともかつて知識人と言われていたような知性のありように連なるような自意識、自己形成がどういう条件、どういう環境であり得るのか、またもうあり得ないのか、というあたりを広く見渡した上での論議というのが必要だと思います。