

――三島なんかとは格が違うとは思うんですが、未だに朝日新聞以下、後がなくなってるリベラル陣営の守護神というか貧乏神みたいになっている、大江健三郎はどうでしたか?
大江健三郎は、私たちの頃は尊敬の対象ではなかったし、私も大江健三郎を読んで、一度として面白いと思ったことはない。
ただし大江健三郎は、いま君も言ったように戦後の、今はもうほとんど崩れ果てかけている何ものかの、最後の拠り所にはなっている。何と言ってもノーベル賞をもらったのが大きかったんだと思うけどね。
――というか、それがほとんど全て、という認識なんですが、あたしなんかは。何より、大江の本を読んでいる人ってのを見たことがない。
大江の本はどんどん売れなくなってきたんだよ。それは、本人もエッセーで書いてる。ある時期から、自分が新刊を書いても、昔なら三万とか五万とか売れたのに、最近では八千ぐらいしか売れない、と。ところがノーベル賞を取ってから、突然それが、二、三万ではあるけれど、売れるようになったらしいんだな。つまり、ノーベル賞を獲らなければ、彼は戦後の一時期少し人気があった作家、で終わっていたよ。
――そう思います。うっかりとっちまったから勘違いが増幅されたわけで。
もしもノーベル賞を獲っていなければ、彼の講演料は五十万円程度だったはずだけど、それが今は百万円だ。でも私は、これをもってして大江はいけない、などと言う気はないよ。そんなことを言えば、欧米のノーベル賞作家、たとえばソルジェニーツィンなら、日本に呼んだとして百万じゃすまないと思うし。南米の『百年の孤独』のガルシア・マルケスが来たら、やっぱりギャラは百万どころではないだろう。だから大江の講演の相場の百万円に関してはおかしくないんだけど、ただね、それによって彼が生き延びてしまったのが残念なんだよ。ほんとに、彼の言っていることはどうでもいいことだけで、また、巷間よく言われもするけど、大江健三郎を引用して何かものを言ったら、それだけでバカにされるだろ。大江がこう言っている、などと引用して何か言おうものなら、それだけで「こいつはバカだ」にしかならないのに、その彼自身は生き延びている。それはまあ、無惨だよね。


もう一つには、特に七○年代以降の、村上龍や村上春樹などの新しい傾向の文学の流れがあるわけで、彼らは団塊後期から団塊の嵐が過ぎる頃の世代だけど、昔ながらの、それまでの教養としての文学とは全然違うところから出てきている。漱石、鴎外を読むとか、きちっと独文の教養小説を読むとか、ではない形で、戦後のアメリカ的な文化から出てきたわけだ。たとえば、小島信夫の『抱擁家族』(講談社、一九七○)が最後の私小説だと言われてるんだけど、実際谷崎賞を獲ったはいいけど、二百人ぐらい集まった授賞式の関係者で、その作品を実際に読んでいる人は一人もいないのではないか、と噂されるような代物になっちゃってるんだよね。

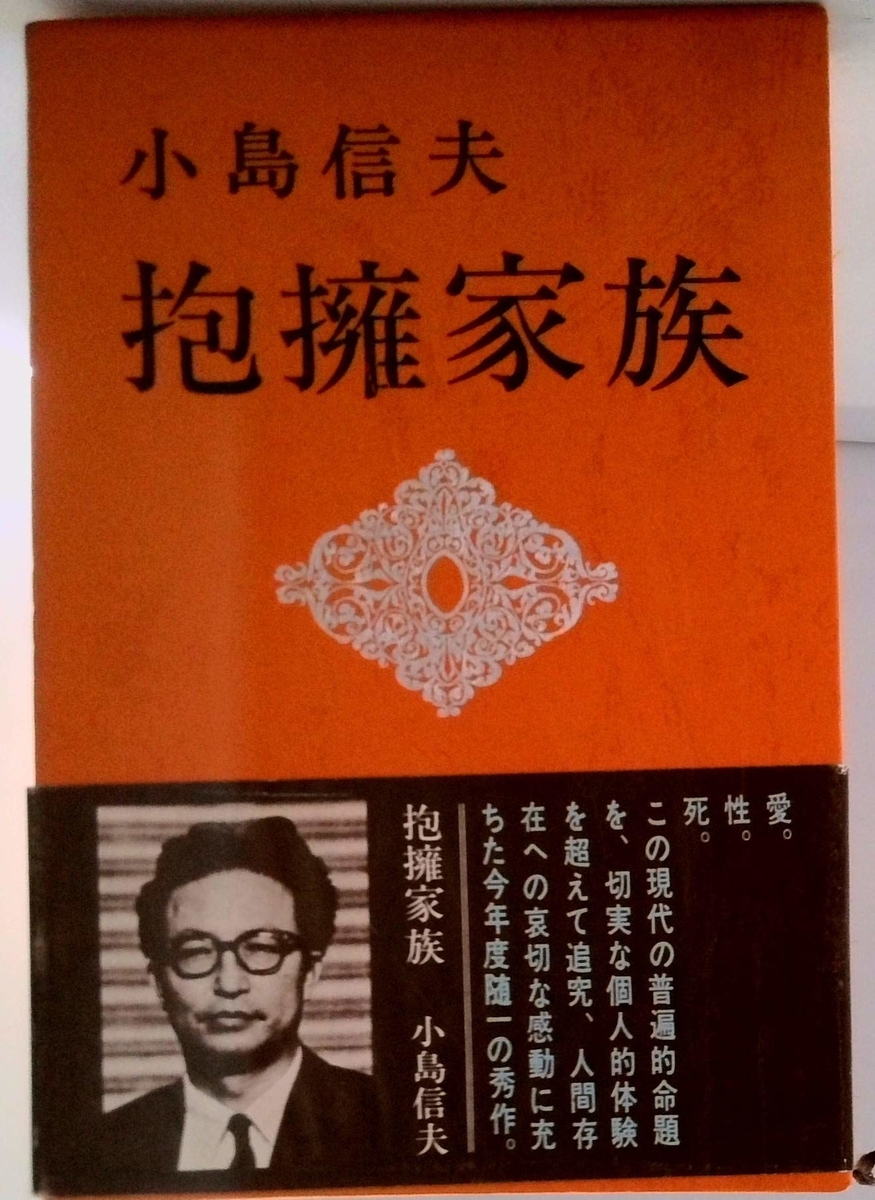
――まあ、ミもフタもなく言ってしまえば、文学自体がもうそういうものでしかなくなって久しいですからねえ。
かつて文学は、教養の代表だった。履歴書の趣味欄に堂々と「読書」と書けたし、恥ずかしくもなかった。そういう状況を前提とすれば、大江もまあ、権威であったわけだ。彼だけじゃない、石原慎太郎もそうだよ。石原慎太郎は、古い権威に対して対抗意識があった。それらに対する挑戦として、障子に男根を突き立てるような、「古い文学者、何するものぞ」と刀で斬りつけるような意識があったわけだ。
でも、それがある時期から変わり出す。文学のパラダイムが変わり、小説は教養ではなくなってしまう。また、その頃から出てきた村上龍たちには、それを崩してやろうという意識もあまりないしね。

king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
king-biscuit.hatenablog.com
――いわゆる文学がその命脈が尽きてしまっても、なんというか、さしたる自覚もないままにうっかりと自意識を持った、持たされてしまった近代常民のその自意識のもだえ具合を吸収してゆくメディアというのは、どこにでもあり得たわけで。良くも悪くも日本の近代文学のある中核に位置してきたとされる私小説なんかまさにその典型で、それこそマンガでも音楽でも、ですよね。
そうそう。面白いもので、そういう私小説的なメンタリティーは、私小説が消えるときに、生きた化石のようにマンガに残ったところがあるんだな。そのひとつがたとえば、つげ義春だ。つげの『無能の人』なんか典型的な私小説だよ。現に彼は、嘉村磯多や葛西善蔵なんかを読んでるわけで、それが実に伏流水のようになって見えないまま、十数年して表にわき出てきた。




本家の文学、特に日本の場合は私小説が文学の王道だと言われていたのが完全に崩れて、私小説以外でもいろいろなものが出てきた。たとえば、野間宏の社会派長編『青年の環』みたいなものもあるけど、あれだってもう誰も読まないよね。結局、あれは部落解放同盟とくっついていることで利権屋さんなんだよ。だから、押さえのために野間先生の本を出しておけば、解同から抗議が来ても安心だ、というわけで、思えばあの時期、野間宏全集という売れない本が出たのは異常な事態だった。それも講談社と筑摩の二社から出ているんだよ。つまり、部落大鑑みたいなもので、買ってくれれば文句は言いません、という要は一種の同和利権だ。

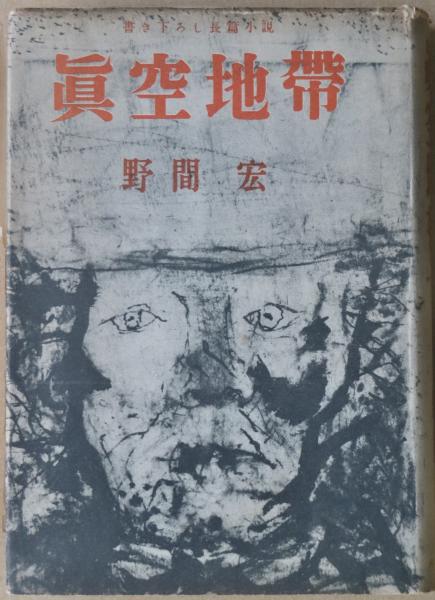
――芸術一般も(文学も映画も音楽も演劇も踊りも)、左翼パラダイムで価値づけられていた時期があったわけですよね。でも、それももう実質崩壊してしまった。
日本の場合、その崩壊の第一段階は、六○年代後半の高度成長とアメリカ文化的な享楽主義でガタガタッっと来る。次が、七二年の連合赤軍、それから、その後の石油ショックによってまたぐらぐらになり、最終的に八九年のベルリンの壁崩壊、でとどめをさされたわけだ。
戦後、荒廃した日本にあって、通産省が産業界を優遇して経済成長を成し遂げたように、左翼思想が一つの大きな支柱としてあって、文化、芸術を庇護して進むという一種の護送船団方式が功を奏していたんだね。時には石原慎太郎などの批判もあったけど、でもこれも、この軸はおかしいでしょう、という批判だから、こういう軸自体はまだ立派に存在し機能していたわけだ。
ところが七○年代を過ぎると、アメリカ的な、別の言い方をすれば戦後的な文化をみんなが身に纏っていく過程で、その軸自体を無視するような連中が出てくる。戦後=左翼護送船団体制であったということが、やがて忘れられ、それに気付かない世代が出てきたってことだね。これは何も政治の話だけではない。芸術全般が、そういうフィルターを通して描かれていた、それこそが戦後という時代だったんだと思うよ。


●高橋和巳
――さらにもっとマイナーというか、今や忘れられている名前ですが、高橋和己なんかはいかがでしたか?
高橋和巳は文学の例として挙げておくけど、世代的には大江健三郎と近い。一九七一年に三十九歳の若さで死んだけどね。団塊の私たちから見れば完全におじさん世代で、生まれが昭和六年。考えたら私なんかより十五歳も上になる。京大で、助手共闘をやっていて、立命館に行って白川静先生の弟子になったりしていた。全共闘側に味方して、同時に、中国文学で李商隠の研究などをしていた人だ。高橋和巳全集の別巻でも李商隠研究が収録されていて、その研究は専門家の間でも評価が高いようだけど、中身が専門的なので私には正直、よくわからない。と同時に小説も書いていたわけで、小説の中でも、私が大学時代に『朝日ジャーナル』を読んでいた頃には『邪宗門』だな。学者で小説を書くという手すさびでは柴田翔なんかもそうだったけど、柴田のは非常に恥ずかしい青春小説だしね。今になるととてもじゃないけど読めたものじゃないし、当時学生時代に読んでさえ「何だかなあ」としか思えなかった。その程度だよ。


でも、高橋和巳の場合には、もう少し小説としての結構がはっきりしている。『憂鬱なる党派』だったら、共産党批判がきちっとあるし、共産党員の人間像でも陰険なやつ、官僚的なやつ、わりとさばさばしたやつと、いろいろ出てきてテーマもはっきりしている。それから、その『邪宗門』の場合には、これは大本教をモデルにして、大本教と二・二六事件を絡めた一種の社会派歴史小説だし、堂々たるもんだよ。
しかもこれは、高橋和巳のうちが天理教だったということもあって、天理教とアナロジーする形で大本教の話が展開するから、土俗的なものと西洋的なもの、自分自身の体験と近代国家との葛藤など、さまざまなものを入れ込んで、大げさに言えば一種の全体小説のような趣があるよ。
――その「全体小説」ってもの言いも最近ではほとんど使われなくなってますねえ。
確かにそうだね。私自身この間、大西巨人の本がマンガになったんで発言を求められて、二十年ぶりぐらいに使ったくらいだ。それはともかく、まあ、かつてはそういう大きな構成の文学があったわけで、でもそれは今ではまったく見られない。小説的なメンタリティーは取りあえず崩れて、ただし伏流水のように、ぽこっぽこっとマンガとか、音楽とか、そういう分野に出てくるけれど、でも、全体小説的な結構、大きく社会とか歴史を語るとなると、それはもう出てこなくなってる。


司馬遼太郎的なものでは、たとえば宮城谷昌光みたいな形のものはあるけど、あれは別として、自分の訴えるものを明らかに持ちながら、全体小説的に仕上げた作品となるとやはり見あたらないよね。だから、野間宏的なもの、それから大西巨人的なもの、それから、ここに述べる高橋和巳は若くして亡くなったが、素養があったから、それを書けた。でも、今ではそういう素養は本当になくなっている。だから、私は、近頃の小説など読む気がしないんだよ。素養がないから内容がない。あるのは私小説としての自意識がぽろっと出るという程度のもので、そんなものはマンガや他のジャンルにひょっこり出てきたものの方がまだはるかに質の高い表現の場合が多いから、そっちをちゃんとフォローしていればいいや、と思ってるよ。