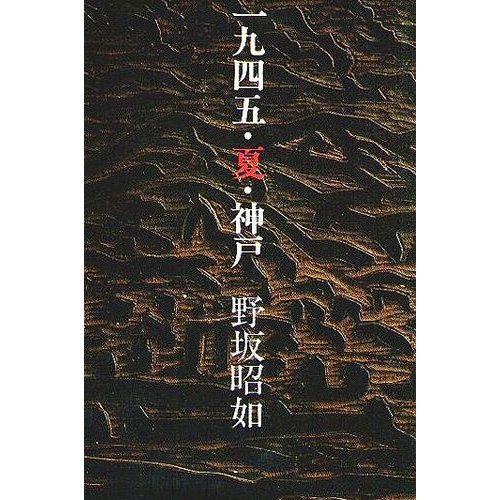「空襲」がどれだけこわいものだったか、という話がある。天変地異の新たなヴァリエーションとして、戦後半世紀の間、さまざまに語られてきたはずの「空襲」。
けれども、その「空襲」というひとことの向う側に、具体的にどのような暮らしの詳細があり、どのような気分、どのような感覚、どのような当たり前が横たわっていたのかについて、われわれはもう思い起こすこともしなくなっている。
同じように、「あの暗いファシズムの時代」といった型通りのもの言いが、どれだけその「ファシズム」の内実をうまく〈いま・ここ〉に伝えようとする志にとって、障害となり、抵抗となり、時に抑圧にさえなってゆくものだったか。「近づいてくる軍靴の響き」といった未だに繰り返される陳腐な表現が、実際のその「軍靴」とはどのような“もの”で、どのように扱われ、どのような手ざわり、どのような匂いを持ち、何よりそれで当時の舗装もされていない地道の上を歩いてゆく時にどのような音を立てたものか、そんな最も五感に則した部分の伝えるべきことをものの見事に覆い隠してゆくものだったか。難しいことでなくても、こと言葉や表現に関わるのが稼業の者ならば、謙虚に反省してみて然るべきだろう。
そんな反省に立とうとするならば、たとえば、こういう表現が素朴に身にしみてくるのではないだろうか。
「近畿地方に防空演習が、はじめて行われたのは、昭和九年七月のことで、これはまだ、仮想敵機に扮した複葉陸軍機のページェント、また爆弾落下地点をしめす発煙筒も、なにやらお祭りのにぎやかしの如くで、誰も熱を入れず、しかし、日支事変がはじまると、少しは本腰を入れ、その直後に、二回目の、全市的訓練があって、はじめてバケツリレーが登場したのだ。これ以後、防火のためといっても昔ながらの火消し道具だが、火叩きバケツ鳶口梯子水槽砂袋スコップを、各家庭で常備するようお達しがあり、デパートで防空展が開催された。人口十万の都会に、十燭光の裸電燈がただ一つ灯されている時、上空からは、どう見えるかとか、爆弾が投下された時にえがく放物線や、爆風の進行方向、いかにも粗雑な展示だったが、満員の盛況で、しかも、観客が階下へ降りるとそこには、防空七つ道具の売場があり、むしろデパートの商魂が先走っていた。」
「昭和十三年四月四日、「灯火管制法」が制定され、屋外灯、門灯、広告電飾灯、公園庭園社寺広場の灯も、日没以後常に警戒警報発令時の光度に落し、各家庭で、防空カーテン、電球遮光用おおいを用意することになる。だが、空襲を受ける実感はまったくなく、というのも、支那大陸から直接本土に飛来いるような航続距離の長い爆撃機が支那軍にあるはずないと、皆信じていたし、また、当時アメリカと戦端を開くなど、まだ考えられなかったが、もしそうなって、敵の航空母艦が日本近海まであらわれるようなら、これは敗け戦に決っている。」
「だが、町内単位の防空組織は、幼稚ながら日一日と進み、水の便の悪い目抜き通りに、防空井が掘られ、中でもその大型の戦防用と称する直径四メートルのものが、三宮近辺に四個所でき、各家庭にも、ほぼ一立方米の水を汲み置くコンクリート製の用水函が、配られた。月に一度、各種用具の点検、用水にわくボウフラ退治を義務づけられ、それでもなお(…)皆なおざりにすませ、第一、防空というならまず先立つべき、高射砲部隊さえ、まるで阪神地方には備えられず、むしろ戦意高揚のための、小道具のおもむきだった。」
「日米開戦以後、いくらか緊張したけれど、それでも待避場所には、壕よりも、一室をそれに当て、まるで物置きの如く、壁に本棚や箪笥をならべて爆風除けとするよう指導され、町内会事務所の前に、壕が掘られていたが、単なる素掘りで、雨水溜るにまかせ、いち早くコンクリート製のものを、庭に造る者も中にはいたが、むしろ臆病者視される始末、エレクトロン、黄燐、油脂と、三種類あるらしい焼夷弾、そして二百五十キロ爆弾の威力については、簡単な図解でしか示されず、ニュース映画で、皇軍荒鷲の、爆撃ぶりはよく知っていても、わが身を、その下に置きかえる想像力は、いずれにも不思議なほど欠如していた。」

野坂昭如『一九四五・夏・神戸』(中公文庫)である。七〇年代初めから半ばにかけて、断続的に文芸誌『海』に連載されたもの。文庫版は初版七七年である。とは言え、今となっては文庫でも絶版になっているのだろう。暇な時に文庫本をていねいに集めているような古本屋を少しまめに歩いてみれば、ひょいと見つかるかも知れない。
「戦前」の神戸の、とある街の暮らしがていねいに描き出されてゆく中で、「戦争」がどのように日常に浸透し、人々の中の「当たり前」として共有されてゆくようになるのかが、妙な先入観や思い込みを抜きにして、実に淡々と語られてゆく。“同じ戦争の被害者としての庶民”といった思い上がった立場から読むのでなく、当時どれだけ「戦争」が「当たり前」だったか、そしてその果てに「空襲」という現実があったのか、そのなだらかなつながりについて〈いま・ここ〉からゆっくり受け止める必要があるのだと僕は思う。小説もまた、読み方ひとつで「歴史」をほどいてゆく大きな武器となり得る。
*1