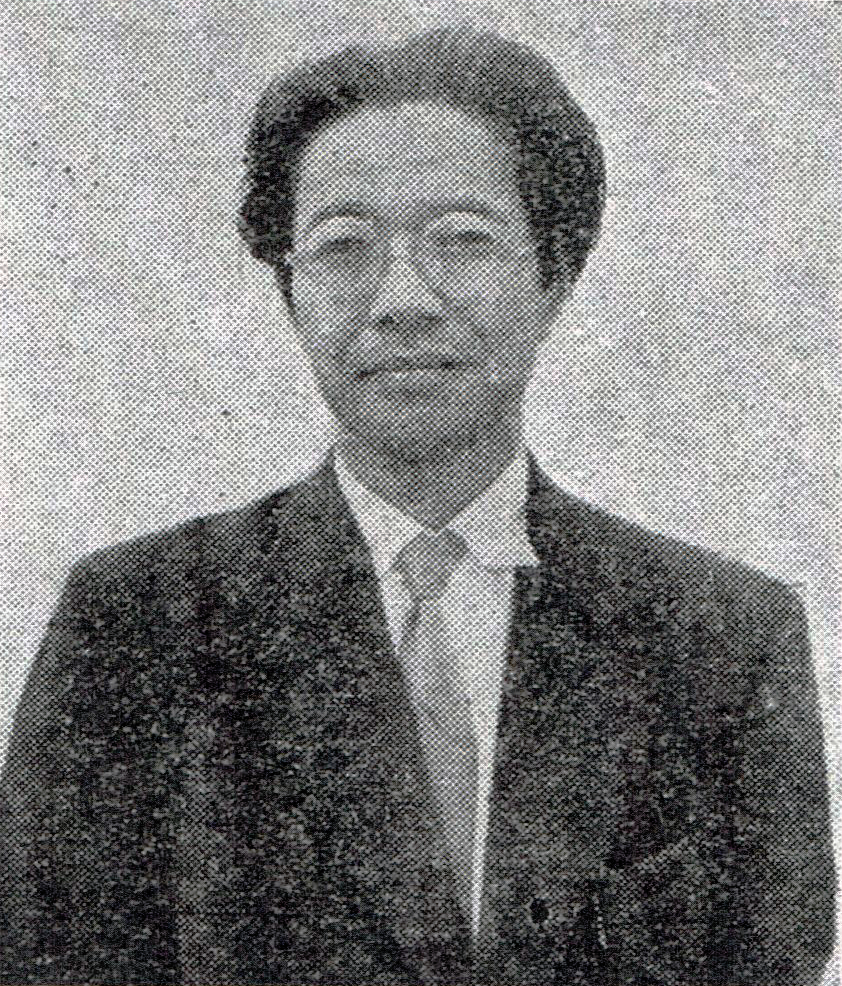宮本常一が、また静かに注目されている、そうである。
民俗学者の宮本常一、である。〈あるく・みる・きく〉の実践者である。近年改めて注目されるきっかけになった佐野眞一の評伝のタイトルにならえば、『歩く巨人』。文字通りに足で「歩く」ことでしか地方の〈リアル〉を自分のものにすることのできなかった時代、それだけ「日本」という広がりもまた、いまよりずっととりとめなくも広大無辺であった情報環境で、大文字のもの言いでない「日本」をあるく速度で自分のものにしようとし続けた野の知性――ひとまずそんな説明が一般的だろう。
その場合の「日本」とは、農山漁村が大部分の「日本」であり、未だ人口の多くがムラの住人であり、百姓であり、漁師であり、鎮守を敬い、先祖を祀り、神と仏を素朴に信じていられることのできたような、そんな国柄の島国、だった。歴史的には近世中期におおむねその輪郭がかたちづくられ、明治以降、疾風怒濤の近代にも有為転変しながら、その匂いや手ざわりは痕跡としてまだかろうじて日々の暮らしの中に残り続けていた、そんな「日本」。柳田国男という固有名詞の制御下に語られてきた日本の民俗学とは、意識的にせよ無意識にせよ、そんな「日本」に焦点をあわせる性癖を共有してきた。あれは学問ではない、文学でありロマンである、と言われ続けてきたのも、その抜きがたい性癖、習い性のゆえだ。
宮本常一も例外ではない。そういう「日本」を彼もまた語ってきていたし、事実、彼の書いたものもそのように読まれてきた。その意味で確かに、民俗学者、ではあるのだ。
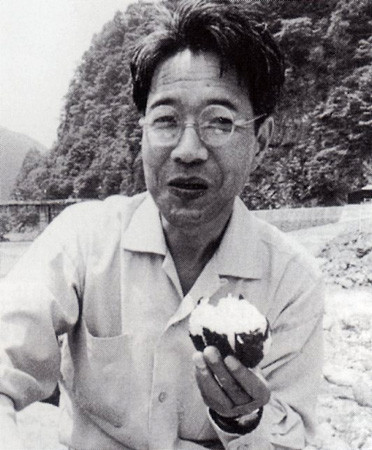
ただ、彼は多くの凡庸な民俗学者と違い、常に変貌の相から「日本」を見ようとしていた。〈現在〉=〈いま・ここ〉という問いを鋭敏に察知せざるを得ない、その意味で〈あるく・みる・きく〉を介したジャーナリズムと民俗学的身体との方法的ハイブリッドの気配があった。
そんな彼の語るその「日本」が最も人々になじまれるようになったのは高度経済成長期、この国が未曽有の変貌を遂げて行き、そんな「日本」がもはや痕跡としてさえも眼前から消え去りつつある時期だった。晩年まで定職につかず、一本どっこのもの書きとして宮本が書き綴った一般向けの読み物の多くは、そんな高度経済成長期に人々に広く受け入れられた。
その頃の日本人にとってどこか郷愁を感じられるようになっていた「日本」。それは、宮本が若いころ、具体的には昭和初年から二十年代にかけての時期に得た見聞をもとに組み立てられている。そして、その間に「敗戦」も、「占領期」も、それらもひっくるめた「戦後」も、全部さしはさまれた上で、高度経済成長期にようやくテキストとして、当時の日本人の前に差し出されている。そのことの位相や同時代的意味は、いまの「歩く巨人」のレッテル任せの“再評価”の視線からはあらかじめ隠されたままだ。
何より、宮本のように「あるく」ことは、なにも彼だけでなく、彼の時代の日本人の多くがまだ自分ごととして可能な営み、でもあった。その後、もたらされた「豊かさ」は、そのように「あるく」ことを遠く離れ、鋤や鍬のようにクルマをあやつり、スーパーに買い物に行き、田畑を見回る新たな常民を大量に産むまでになった。いまや、新素材の服や靴を取り揃え、バックパッカーよろしく身を固めた今様、宮本常一を夢見る者も出てきているだろう。日本の中だけにとどまらない、国境すらうっかりと超え、いまどきのこと、地球市民の夢にまどろむ者さえいて不思議はない。だが、言っておく。それは、宮本の願ったような「あるく・みる・きく」の志とは、断じて似て非なるものだ。
「あるく・みる・きく」というインプットの系列に、アウトプットの「よむ・かく・はなす」も加えて、初めて宮本常一的な民俗学的主体は〈いま・ここ〉に役に立つものになる。農山漁村の自然環境だけでなく、書庫を、アーカイヴを、時にバーチャルなネット空間でさえも、そのように遠近法確かな主語の制御の下にゆったりと関わってゆくことができるような身体をこそ。そんな民俗学的身体の戦略的意義を〈いま・ここ〉で方法的に自覚した主体にこそ、宮本常一の志はまた宿る、降臨する。二一世紀の宮本常一には、「巨人」になどなる必要は、きっともう、ない。