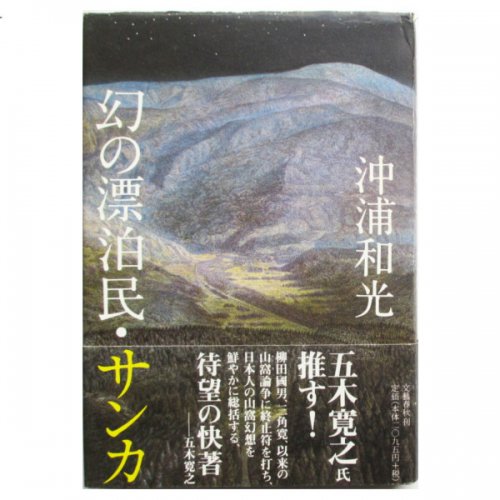
「サンカ」と聞いてピンとくる人は、ある意味要注意。さらに「漂泊」「異人」「異界」「周縁」「闇」なんてもの言いにもうっかり眼輝かせちまうようならなおのこと。そういう性癖を持っている向きにいきなり冷水をぶっかけるような本、なのだ、ほんとは。
山野をすみかとする一所不住の漂泊集団、竹細工などを生業としながら時に窃盗など犯罪にも手を染める「闇」の一族――そんなイメージで「サンカ」は語られてきた。昭和初期、三角寛の手による一連の小説がそのイメージを流布し、あやしく増幅してゆくのに大きな役割を果たした。戦後も何度か訪れた「サンカ」再評価の波も同じこと。かくて「サンカ」は落ち着いた学術的タームというよりも、日本人の社会的想像力のからくりの中でやりとりされるもの言い、日本人が日本とは何かを語ろうとする時に好き放題に引用され、使い回されていいパッチのひとつとなった。学術論文や専門書などにおいてよりも、むしろ小説や映画、その他さまざまなジャンルのサブカルチュアでこそ「サンカ」が最もいきいきと語られてきたのは、実にそういう理由からだ。
著者はこれまでも遊芸者、香具師、生地屋、家船など、まさにそれら「漂泊」民と目されてきたマージナルな集団を研究してきた文化史研究者。当然、被差別部落との関わりなどにも造詣が深い。そういう蓄積の上に、これまでの「サンカ」研究をその広大なイメージ形成と流布の経緯も含めてバランス良く誠実に総括しようとしている。その手さばきは、七十代半ばになるとは思えないほど的確で冷静だ。サンカは古代はもちろん、中世にさえもさかのぼれるような「伝承」を持っていないことを文書資料から検証し、せいぜい近世末期の農村共同体解体期に大量に出現した「無宿」のなれの果て、と位置づける。イメージとしての「サンカ」にいいように振り回され、あやしげな幻想や妄想の領域に容易に足とられてしまいがちな俗流の歴史理解、日本文化早のみこみ――昨今の「歴史認識」騒動でもこの傾向は百家斉放、何でもありの様相を呈したのは記憶に新しい――をも相対化するこの見解は、民俗学者の眼から見てもまず穏当なもので高く評価できる。
ただ最終章近く、三角寛のテキストの位置づけから現存する「サンカ」伝承のあたりに踏み込むと一気に矛盾が現われる。戦後の「部落解放」幻想に規定されて〈いま・ここ〉に出現してしまった「サンカ」伝承のありよう(「観光化」し、あらかじめ制度に埋め込まれた「サンカ」言説とそれに翻弄される現在)への相対化の視線は全くない。著者の経歴自体を相対化する作業になるとは言え、それまでの誠実な分析の手つきが〈いま・ここ〉には適用できないこれまでの活字の知性の限界も、奇しくもまた現われた形になった。そう言えばタイトルもオビ(五木寛之の推薦文つき)も、それら「サンカ」幻想との距離を測りかねたようなものになっていて、冒頭述べたような性癖の衆が間違って買うのでは、と、あたしゃちょっぴり懸念したりするのであります。
